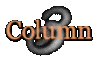
数秘術関連等ツイート(2020年12月分)
でもそんなの関係ねぇ! (2020.12.31 14:36)
「8」:「ちゃんと計画立てなきゃ…」
「1」:「でもそんなの関係ねぇ!」
「6」:「ちゃんと責任負わなきゃ…」
「3」:「でもそんなの関係ねぇ!」
「4」:「ちゃんと習慣続けなきゃ…」
「5」:「でもそんなの関係ねぇ!」
「2」:「ちゃんと応答返さなきゃ…」
「7」:「でもそんなの関係ねぇ!」
自分の中の「叫び」 (2020.12.29 23:32)
自分の中の「8(制御)」マインドが「計画があまり進まない…」と嘆いた時、同じく自分の中の「1(無視)」マインドが「でもそんなの関係ねぇ!」と叫んでくれることで取れるバランスもあるね。
分析と分類 (2020.12.29 23:24)
「分析」より「分類」を優先することで、人間関係構築のための「答え」を迅速に用意する「2」の強いヒト。
「分類」より「分析」を優先することで、相互誤解を防ぐための「問い」を慎重に用意する「7」の強いヒト。
「あのヒトは○○だ!」と決め込む前者、「あのヒトは○○か?」と決めかねる後者。
城壁 (2020.12.29 22:17他)
「4」のヒトは、自らの些細な「ルーティン」すらも、自己を守る「城壁」の一部として利用するイメージ。
もしも一個でも「ルーティン」が欠けたなら、ガラガラと音を立てて「城壁」全体が崩れ落ちてしまう。
たとえどんなに不要と思われようが、その「ルーティン」を無くすわけにはいかないのだ。
そんな「城壁」を他人によって外側から壊されるくらいなら、自らの中に眠る逆数「5」を発揮させ、半ば自爆的に「城壁」を破壊することを選ぶだろう。
「これは外からの力によって破壊されたわけじゃない!自らの意思であえて壊したんだ!」などと嘯くことで、箱庭の中のプライドを守っているのだ。
恒常性 (2020.12.29 15:23)
それにしても四年に一度の「4(ルーティン)」すらも取り止めることができないとは、つくづくヒトの持つ「4(恒常性・ホメオスタシス)」の強さたるや。
まぁその機能があるからこそ、コスモス(秩序)が保たれるわけだが。
自らへの「赦し」 (2020.12.29 14:40)
奇数(動的・混沌・チカラ)的に「怒る」のにも疲れ果てる。
偶数(静的・秩序・カタチ)的に「叱る」のにも呆れ果てる。
そんな先に偶奇両有の「9」的な「赦し」が訪れる。
この「赦し」は相手だけではなく、散々に「怒る」と「叱る」を繰り返してきた自らへの「赦し」でもある。
怒る、叱る、赦す (2020.12.29 12:40)
怒る奇数(動的・混沌・チカラ)。
叱る偶数(静的・秩序・カタチ)。
赦す「9」。
行っちゃった (2020.12.28 21:03他)
毎年恒例「年始の小田原行き」を占ったら、全て奇数(動的・混沌・チカラ)とな。
毎年恒例というルーティンを偶数(静的・秩序・カタチ)とするならば、奇数だらけのこの出目は「殿!ご再考を!」って感じにも読める。
でも僕はバカ殿だから、ラストの「1」が「行っちゃえ後藤!」って見えるんだ。
ダブルで「7」が出てるから、自らの体調を逐一確かめながら、かつなるべく群れずに行動しなさい、と読むのが妥当かな。
メリットの「5」が「いつもと違ったやり方や行き方を選べ」とも読めるから、ちと検討してみるかねぇ。

時間感覚の差 (2020.12.28 18:34)
こちらの「待っている」と、相手の「待たせている」。
こちらの「待たせている」と、相手の「待っている」。
このお互いの「時間感覚の差」を「相性」と呼ぶことは可能なのかもしれないね。
スレーブナンバー (2020.12.28 17:08)
それにしてもこれだけ「マスターナンバー」という概念に振り回されているヒトを見ると、これはもはや「スレーブナンバー」って感じだよなぁ。
フォロー解除 (2020.12.28 16:39)
とりあえず今年は、自身の個人年数に関係なく、精神が「0(虚無)」に支配されると、ツイッターのフォローをほぼ全解除してしまう、ということが分かっただけ収穫だったな。
ただの「自己責任論」 (2020.12.28 15:16)
いわゆる「引き寄せの法則」ってやつは、結局のところ「自己責任論」にたどり着くから、僕はあまり好きではないんだよね。
「多様性」の見え方 (2020.12.27 23:58)
奇数(動的・混沌・チカラ)的な感覚の持ち主からすれば、いわゆる「多様性」とは「9(寛容)」なセカイを目指すことになるのかもしれない。
でも偶数(静的・秩序・カタチ)的な感覚の持ち主からすれば、それは単なる奇数(動的・混沌・チカラ)的なセカイの実現に見えてしまうかもしれないのだ。
「旧い」というレッテル (2020.12.26 20:25)
「5(革新)」的な集団における最大の武器は、既存の「4(継続)」的な集団全てに対して「旧(ふる)い」というレッテルを貼ること。
これにより価値を貶められた「4」は、ただ今まで通りのことをしているだけで、ますます「旧く」見えるようになってしまう。
それが更に「5」を新しく見せていく。
結論 (2020.12.25 23:51)
「ナウシカの数ってなんだろう?」などと考えながら観ていたけれど、もう全部の数を持ってるってことでいいや。
疾病予防の「数」 (2020.12.25 16:52)
「6(美)」という数は、美しく調える意から「健康」や「衛生」のイメージも表す。
更には「周囲とのズレ(=美しくないこと)」を避けるために機能する「羞恥心」や「均質性(ホモジナイズ)」、そしてズレを直すための「自粛」や「矯正」のイメージも持つ。
疫病蔓延を防ぐヒントは「6」にある。
インスタ映え (2020.12.24 23:19)
「インスタ映え」と聞くと、自らの楽しい体験をただ「3(表現)」しているように見える。
でも実際には「みんなと同じようにインスタあげなきゃ」とか「ノリやトレンドから外れないようにしなきゃ」などのように、グループ内秩序を「6(調整)」していたりする。
皆が映えるから、私も映えるのだ。
インパクトのあるこじつけ (2020.12.24 15:44)
東京都の今日の感染者数は「888」人か。
インパクトのある「数」からは、インパクトのある「意味」がこじつけられがち。
不安を煽る「こじつけ」も、希望を繋ぐ「こじつけ」も、どちらも真に受けすぎないようにね。
雑な数秘術 (2020.12.23 22:38)
クリスマスイブ(12/24)は「9」になるから「いのちが混じり合う日」か。
そしてクリスマス(12/25)は「1」になるから「いのちが始まる日」か。
こんな雑な数秘術で、年は暮れていく。
看護師たちの悲鳴 (2020.12.23 19:58)
自らが懸命に行う「6(奉仕・自粛)」と、インスタを含む世間の「3(享楽・放言)」とのコントラスト。
この「温度差」に、ヒトの心はそうそう耐えられるものではないね。
火の時代、風の時代 (2020.12.22 21:50)
西暦1000年代は「1(動の火)」なので「火の時代」、西暦2000年代は「2(静の風)」なので「風の時代」などとこじつけてみる。
蒸気機関・電気・原子力などのエネルギー、そして世界戦争という「火」を味わい尽くした後に、言語を超えるコミュニケーション革命の「風」が静かに吹くわけか。
沖縄のヒト (2020.12.22 16:25)
「9」のイメージに悩むヒトに対して「沖縄のヒトのゆったりとした生き方、それが「9」ということだよ」などと伝えておいた。
こぼれ落ちたもの (2020.12.22 16:16)
あらゆることを「1」から「8」、そして「0」のどれかに関連付けていって、どうしても関連付けできない「こぼれ落ちた」もの、それがたぶん「9」になるんじゃないかな。
現代数秘術との違い (2020.12.22 12:50)
「あなたは「7」のヒトなので、こういう性格です」と伝えるのが、一般的な現代数秘術。
一方、逆数秘術(アンビバレント・ヌメロロジー)では「あなたの中の「7」と「2」が、心の中で互いに影響を受けながら(与えながら)どのように立ち振る舞い、どのような状態になっていくか」を探っていく。
自らの肉体の破壊 (2020.12.22 1:13)
「4(安定志向)」のヒトが、突発的に「5(破壊行動)」を発揮するケース。
身近なモノをあえて壊してみることで、それがどれだけ大切なモノなのかを、鈍麻した自らの感覚に「痛み」をもって刻み込むイメージ。
そんな身近なモノの最たる例が、他でもない「自らの肉体」だったりする。
奇妙な (2020.12.22 0:41)
奇数(動的・混沌・チカラ)を表す「odd」には「変な」「奇妙な」という意味もある。
奇数における「変」や「奇妙」を逆数秘術でとらえるならば、あくまでも「偶数(静的・秩序・カタチ)」から見ての「変」であり「奇妙」であるということ。
意味とは「コントラスト(対比)」で与えられる。
フランスの不自由、日本の自由 (2020.12.21 22:19)
奇数(動的・混沌・チカラ)優位のフランス社会における、付け焼き刃的かつオーバーな偶数(静的・秩序・カタチ)システムの導入による不自由。
元より偶数(静的・秩序・カタチ)システムに慣れている日本社会において、むしろ今のフランスよりも「自由」を感じる様。
要は「コントラスト」の問題。
「数」を知らない人々 (2020.12.21 0:01)
アルゼンチンのアビポネ族(19世紀初頭に消滅)、ベネズエラ〜ブラジルのヤノアマ族、南オーストラリアのルミララ族などは全く「数」を知らず、一つのものや一対のもの、最高でも三つからなる集合しか把握できないという。
「数」という概念を必要としないことが、今ではどれだけ貴重なことか。
夢にも現(うつつ)にも (2020.12.20 17:26)
「いつまでも夢なんか追ってないで、早く現(うつつ)に戻りなさい!」と諭す偶数(静的・秩序・カタチ)なヒト。
「そんな現(うつつ)に埋もれてないで、夢に向かったらどうだい?」と唆す奇数(動的・混沌・チカラ)なヒト。
そんな夢にも現(うつつ)にも囚われない「9(無為自然)」な生き方。
「母性」で好きになる (2020.12.20 15:38)
倫理や秩序の逸脱も気にせず、自由奔放に人生を遊び尽くすのが、いわゆる「3」の強過ぎるヒト。
そんな相手だからこそ、つい甲斐甲斐しく面倒を見てしまうのが、いわゆる「6」の強過ぎるヒト。
自らの「6(母性)」が存分に発揮できる相手だからこそ、なぜか好きになってしまうのだ。
母性 (2020.12.20 14:54)
「整ってほしい」と願う親心。
「整えたい」と手を出す親心。
「6(調整)」という数の中に「母性」が輝いている。
クズ (2020.12.20 14:25)
偶数(静的・秩序・カタチ)的な社会の中で、奇数(動的・混沌・チカラ)を貫くヒト。
これだけならカッコいいんだけど、そんな偶数システムに存分に甘えてばかりいるくせに、そんな自らのことを「オレ奇数貫いててカッコいい!」などと自負するヒト。
こういうヒトが「クズ」と認定されるわけか。
山体崩壊 (2020.12.19 23:17)
「5(動の土)」を「山体崩壊」のイメージで捉えてみてもよい。
これは「4(静の土)」に対する抵抗運動であり、「4(安定)」への強い信仰(過信でもある)を激しく揺さぶるカオスでもある。
「まさかこの山全体が崩れ落ちるとは…」という言葉を吐かせることができれば、まさに「5」の面目躍如だ。
静の風 (2020.12.19 22:11)
「2(静の風)」は別に「凪」というわけではなく、空気の振動から生まれる「声」、つまりは「コミュニケーション」のイメージだね。
五つ組 (2020.12.19 21:53他)
逆数秘術(アンビバレント・ヌメロロジー)における五つ組。
「1(動の火)」⇔「8(静の火)」
「3(動の水)」⇔「6(静の水)」
「5(動の土)」⇔「4(静の土)」
「7(動の風)」⇔「2(静の風)」
「9(全)」⇔「0(無)」
「五行説」というよりも「4+1行説」って感じかも。
つか、以前にインドの「五大」に比定してたじゃん。
火・水・土・風は同じで、「9」⇔「0」は「空(くう)」になるというやつ。
しっくりくるな、これ。
今年の「第九」 (2020.12.19 17:10)
異なるもの同士が混じり合うことで生まれる「融和」を表す「9」。
コロナ禍で苦しむ今年の「第九」は、いつもと違った「音」に感じるな。
環境からの脱出 (2020.12.16 15:03)
「4(安定)」として生きたいのに、うまく「4」ができない…
このように悩むヒトは、自らの「4」の弱さを嘆くよりも、まずは自らを取り巻く環境の「5(変化)」が強過ぎるのではないか、という可能性について考えてみた方がいいかも。
そんな環境を脱出した方が、きっといろんな意味で手っ取り早い。
「ズレ(差異)」の問題 (2020.12.16 14:08)
偶数(静的・秩序・カタチ)が強い組織の中では、奇数(動的・混沌・チカラ)が強いヒトは「せっかち」と言われてしまう。
奇数が強い集団の中では、偶数が強いヒトは「鈍くさい」と言われてしまう。
これを当人だけの問題として捉えず、当人と環境との「ズレ(差異)」の問題として捉えていく。
悲しみの源流 (2020.12.15 22:51)
「1」のヒトには「8(辛抱)」にまつわる悲しみがある。
「4」のヒトには「5(変化)」にまつわる悲しみがある。
「9」のヒトには「0(消失)」にまつわる悲しみがある。
自らの「逆数」を「悲しみの源流」として読んでみると、また違った発見があるかも。
「!」 (2020.12.15 15:54)
「7」が「?(クエスチョン)」ならば、対する「2」は「!(エクスクラメーション)」。
「私は○○である」「私とあなたとの関係は△△である」などという、一見して揺るがざる、そして信じ抜くに足る「答え」に出会えたことへの驚きと喜びが、まさに「2」という「!」で象徴されている。
ミルグラム実験 (2020.12.15 14:55)
「閉鎖的な状況において、ヒトはどこまで権威者の指示に従うのか」を検証した「ミルグラム実験」。
これは「アイヒマンテスト」とも呼ばれ、ヒトがいかに自らの「7(懐疑)」を封印し、対する「2(従順)」を強化するのかがよく分かる実験だ。
このアイヒマンが「2」のヒトというのがなんとも。
自分の数 (2020.12.14 22:52)
自分の数(僕の場合は「4」)について書くのって、実は案外難しい。
あまりにもそれが「わかりきったこと」であるが故に、改めて他者に説明することが難しくなるという。
象徴言語としての「数」が染み付いた結果、それを通常言語に翻訳することが課題となる始末。
だって「4」は「4」だもんなぁ。
もしも「子供」がいたなら (2020.12.14 17:15)
僕にもし子供がいたなら、子供を観て(2)、守って(4)、諭して(6)、御する(8)という偶数(静的・秩序・カタチ)への評価が、対する奇数(動的・混沌・チカラ)よりも高くなったのかもしれない。
「数」の評価は、それを扱うヒトの体験によって定まっていく。
食事 (2020.12.13 19:46)
自分の中の「3(ジャンク志向)」と「6(ヘルシー志向)」の真ん中らへんで食を楽しめるといいね。
飽きる (2020.12.13 13:41)
「何かに飽きるということは、自らのビビッドな好奇心を新たに発揮するチャンスなんだよ!」
まさに「3(感情のカオス)」ならではのメッセージだね。
ゲシュタルト崩壊 (2020.12.12 23:59)
漢字などの文字を見続けることで、その文字の構成要素がバラバラとなり、一まとまりのものとして認識できなくなる「ゲシュタルト崩壊」。
まるで「2(言語というコスモス)」が、突然に「7(非言語というカオス)」へと反転する様だ。
「7」が強いヒトは文字以外でも日々これを体験しているのかも。
まずは書き殴る (2020.12.12 19:45)
自らが書こうと思ったことをまずは「1(衝動)」的に書き殴り、それをわかりやすく編集するという「8(制御)」は、後から時間をかけて行っていく。
初めに「8(計画)」を用意し、そのカタチに注ぎ込むように「1(実行)」を発揮する方がよいケースもあるだろうが、今の僕には前者の方が進めやすい。
覚悟 (2020.12.12 16:51)
「4(守る)」と「5(抗う)」は不可分の存在。
もし何かを真剣に「4(守る)」したければ、同じくらい真剣に「5(抗う)」する覚悟が必要となる。
こちらのコスモス(秩序)を守るためなら、相手のそれをカオス(混沌)で荒らす覚悟ともいえる。
複数の「根拠」 (2020.12.11 14:15)
ユングの類型論における、直観(soul)、感情(mind)、感覚(body)、思考(brain)、その全ての機能を判断の根拠として用いる「9」のヒト。
でも同時に二種以上の根拠を用いることで、(それを自覚できないまま)判断やそれに基づく言動に混乱が見られることがある。
パートナー (2020.12.10 19:20)
毎日の「4(ルーティン・日課)」があるからこそ、たまの「5(アドホック・特別)」が輝く。
たまに「5」を味わうからこそ、いつもの「4」に安心する。
「4」と「5」は、互いの良さを認識する上で、欠かすことのできない「パートナー」なんだ。
一度やめてみる (2020.12.10 18:30)
今まで続けてきた「4(ルーティン)」を一度やめてみることは、その「4」が本当に自分に合ったものなのか、そして本当に必要なことなのかを確かめる行為につながる。
つまり「5(改革・変化)」とは、今まで続けてきた「4」の意味や意義を確かめるための大切な行為となり得るわけだ。
セカイを変えるもの (2020.12.10 1:08)
礼儀、良識、責任、義務…これら様々なコスモス(秩序)で作られた「6(デザイン)」なセカイ。
そんなセカイで生きにくさを感じているヒトは、その存在自体が「3(アート)」そのもの。
そのカオスが、きっとセカイを変えていく。
気持ち悪い「アート」 (2020.12.9 23:48)
多くのヒトが美しいと思う作品は、それが「美のコスモス(秩序)」であるがゆえに、「3(アート)」よりも「6(デザイン)」に近づく。
多くのヒトが違和感を覚え、何とも言えない気持ちになり、果ては気持ち悪さまで感じたなら、それこそがきっとカオスとしての「3(アート)」なのだろう。
頑固 (2020.12.9 22:27)
奇数(動的・混沌・チカラ)っぽさをなかなか変えないヒトは、偶数(静的・秩序・カタチ)なヒトからはきっと「頑固」に見られるだろうし、逆もまた然り。
つまり「頑固」かどうかを決めるのは「コントラスト(対比)」であり、いわゆる「頑固な数」というものを決めることはできないということだ。
大抵のヒトは (2020.12.8 14:39)
いくら僕が「3」のことを「倫理の逸脱者」とか「倫理にカオスをもたらす者」などと書いたとしても、だからといって「3」のヒトがそういう性質の持ち主であると表しているわけではないからね。
通常なら対となる「6」マインドを優位に保ち、倫理のコスモスを遵守することに努めているはずなのだから。
「楽しい」から無くならない (2020.12.8 14:21)
「6」が「倫理という名のコスモス」を磨き上げ、その美しさを保つことを自他に課す数だとすれば、対する「3」はそんなコスモスを窮屈に感じ、それを逸脱しようとする「カオス」そのものと言える。
いつまでも「不倫(脱倫と呼んでもいい)」が無くならないのは、その逸脱が本質的に「楽しい」からだ。
真面目なクズ (2020.12.8 14:14)
あまりにも「3(倫理の逸脱者)」なヒトのペルソナが、すばらしく「6(倫理の遵守者)」に見えるというケース。
これもある意味「バランス」か。
シジル魔術 (2020.12.8 13:46)
自らの願望を文章に起こし、その中から重複する文字を消し、残った文字を組み合わせて図案化する「シジル魔術」の一例。
これはまさに「2(言語というコスモス)」を解(ほぐ)すことで生まれる「7(非言語というカオス)」のイメージ。
こうすることでその願いは、深層意識の奥底にまで潜っていく。
誤解 (2020.12.8 12:20)
ヒトが「言葉」を誤解するのは、誤解するヒトが悪いわけでも、誤解させるヒトが悪いわけでもない。
それを構成する「言語」そのものが、あまりにも不完全(定義や解釈の自由性を持つ)なものだからだ。
でも不完全なものだからこそ、ヒトはセカイを「新しく」していくことができる。
セカイの解(ほぐ)し方 (2020.12.8 12:10)
「7」とは「言語」による相互誤解を解消でき得るチカラであると同時に、相互理解を妨げ得るチカラでもあるわけだ。
「7」が持つ「?」という名のツールをどのように使いこなし、「言語」で編み上げられたセカイをどのように解(ほぐ)していくか。
この解し方により、セカイは大きく変わっていく。
解(ほつ)れ (2020.12.8 12:02)
「言語」とは決して解(ほど)くことのできない完璧な「2(線)」ではなく、近づいてじっくり見てみるとわずかながら「解(ほつ)れ」が存在する。
そんな「解れ」を思わず解いてしまうのが、ヒトが自然に持つ「7」マインドであり、これがあるからこそ同じ言葉でも、ヒトにより意味が変わり得るのだ。
言語 (2020.12.8 11:55)
ヒトは「言語」によって物事を定義し、意味を与え、分類をし、理解もし、そして伝達していく。
つまり「言語」とはモノとモノ、ヒトとヒトを「=」でつなぐ「2(線を引く)」のイメージとなる。
そんな「言語」による「=」を確かめ、疑い、考えることが「7(線をほぐす)」のイメージとなる。
不完全 (2020.12.8 1:14)
思考の材料としての「言葉」の大切さを理解すると同時に、意思疎通の道具としての「言葉」の不完全さを痛感しているのが「7」なヒトなのかもしれない。
数秘脳 (2020.12.7 23:15)
単騎で独断専行し、自らの能力をフル活用しながら敵を斃していく「1(ソルジャー)」。
厳格な規律と冷徹な指揮をもって、組織全体を動かしながら敵を制圧する「8(コマンダー)」。
…など『幼女戦記』という戦争アニメを見ながらつぶやく数秘脳。
一面 (2020.12.7 22:38)
「このヒトは本当の意味での「2(信じる)」が欲しいからこそ、ここまで徹底して「7(疑う)」するのかも…」
あまりにも「7」が強過ぎるヒトであっても、このような視点で相手を捉えてみることで、きっとその評価が変わってくるのかもね。
「一面」だけでヒトを評価しないって本当に大事だな。
「暴走」の目的化 (2020.12.7 19:52)
「このまま私は「1(エゴの暴走)」し続けることで、ようやくにして「8(エゴの制御)」のやり方を見つけられるかもしれないし、もしかしたら他の誰かが私をうまく「8」してくれるかもしれない」
そんな風に「1」をやり続けるヒトもいたりするね。
あえて抑え付ける (2020.12.7 18:11)
自らの中において、大いに暴れる「1(野性)」を見たいからこそ、あえて「8(理性)」で徹底的に抑え付けるケースもあるんだろうな。
「1(野性)」の生存確認のために「8(理性)」を用いるパターンだ。
善し (2020.12.6 14:51)
「4(安定)」を「善し」とするヒトからすれば、きっと「5」は「不安定」に見えることだろう。
「5(自由)」を「善し」とするヒトからすれば、きっと「4」は「不自由」に見えることだろう。
そのヒトの「価値観」が、その「数」の印象を決めていく。
違い (2020.12.6 14:40)
「5(自由)」と「4(不自由)」の違いって何だろう?
「4(安定)」と「5(不安定)」の違いって何だろう?
コントラスト (2020.12.6 14:27)
「4(維持)」が「4」であればあるほど、対となる「5(変化)」はより「5」となっていく。
物事は「コントラスト(対比)」によって認識され、そして評価されていく。
つまり「5(変化)」の「5」らしさを決めるのは、対となる「4(維持)」がどれだけ「4」らしいか、ということだ。
変える人 (2020.12.6 14:03)
「変人とは変な人じゃない、変える人だ」
モバイルハウスで全国を旅しながら暮らすヒトの言葉。
「5(変化)」という数は、きっとこの言葉の通りなのだろう。
行うは難し (2020.12.6 00:32)
まずは自分の中の「1(衝動)」「3(奔放)」「5(破壊)」「7(懐疑)」という、荒ぶる奇数(動的・混沌・チカラ)たちを強く意識する。
そしてこれらを「8(制御)」「6(責務)」「4(安定)」「2(信任)」という偶数(静的・秩序・カタチ)たちに注ぎ鎮める。
書くは易し、行うは難し。
ハードモード (2020.12.4 16:03)
自らが「マスターナンバー」であることを強く自覚するヒトは、他のヒトよりも「ハードモード」な人生を歩んでいそう。
そんな「ハードモード」な人生を送るヒトこそが「マスターナンバー」の「特殊性」を強化しているとも言える。
しんどいこと (2020.12.3 16:47)
動かし難い「2(答え)」だらけの世の中で、しかもそんな「2(答え)」に自らの存在意義を託す人々が多い中で、ひたすらに「7(問い)」を追い求めるというのは、とてつもなくしんどいことではある。
寛容 (2020.12.1 23:13)
「1(衝動)」な自分も「8(抑制)」な自分も共に赦していく。
「3(奔放)」な自分も「6(配慮)」な自分も共に赦していく。
「5(変革)」な自分も「4(維持)」な自分も共に赦していく。
「7(検証)」な自分も「2(信用)」な自分も共に赦していく。
それが「9(寛容)」という生き方。
体験 (2020.12.1 16:05)
その占いがもしかしたら、あなたの貴重な「体験」を奪ってしまっているかもしれないよ。