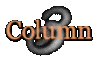
数秘術関連等ツイート(2018年2月分)
社会への順応 (2018.2.28 21:29)
「1(権威無視)」全開で突っ走っていたヒトが、いつの間にか「8(権威重視)」に変転する例。
「7(徹底検証)」全開で突っ走っていたヒトが、いつの間にか「2(絶対信用)」に変転する例。
奇数(動的・混沌・チカラ・コドモ)から偶数(静的・秩序・カタチ・オトナ)への、一つの「順応」の形。
ニュートラルルート (2018.2.28 13:53)
「真・女神転生」のNEUTRAL(中庸)ルートでお目にかかるメッセージ。
「もう右からの声は聞こえない」
「もう左からの声は聞こえない」
「そのまま前に進め…」
LAW(秩序)の声もCHAOS(混沌)の声も聞こえなくなる境地。
これこそ「9(中庸)」であり、進む先に太上老君(老子の神格化)が待つ。
無音状態 (2018.2.28 13:38)
「9(無為自然)」マインドへと至ることで、ヒトは自らを支配してきた奇数(野性)と偶数(理性)から解き放たれる。
それは両者が自己の中で主張をしなくなるということであり、その無音状態において「自己」の定義はあやふやなものとなる。
その隙を狙って、逆数「0(虚無)」が忍び寄ってくる。
コントロール放棄 (2018.2.28 13:22)
「万事をコントロールしたい」という「8」マインドの高まりは、諸事が思い通りにいかなくなった際に一気に反転し、「1」マインドという衝動性として自他の秩序を荒々しく乱していく。
そんな自らに疲れ、そして嫌気がさしたなら、「9(無為自然)」マインドへと至りコントロールを放棄する道もある。
二分する (2018.2.27 12:00)
「逆数秘術」とは奇数と偶数の単純な二元論ではない。
奇数性と偶数性とが混ざり合った止揚としての「9」、両性の無い「0」も用いてセカイをこじつけていく。
しかしこの「9」と「0」ですら二元論的に配置することが可能であり、つまり概念が存在する以上「二分する」ことからは避けられないのだ。
問わず答えず (2018.2.27 11:43)
奇数マインド(動的・混沌・チカラ・コドモ)の生き様とは、セカイを「問い続ける」こと。
偶数(静的・秩序・カタチ・オトナ)マインドの生き様とは、セカイに「答えを出す」こと。
偶奇混交である「9」マインドの生き様とは、何も問わず何も答えず、ただありのままにセカイで「生きていく」こと。
ペッパーくん (2018.2.26 10:37)
ロボットのペッパーくんがヒトを占うことは、もしかしたらもうできるのかもしれない。
でもペッパーくんが別個体のペッパーくんを占う(しかも自律的に)ことは、果たしてできるのだろうか。
ロボット同士に占いをさせることにより、占いという行為の本質が見えてきそうな気がするね。
カタチの押し付け (2018.2.26 10:30)
僕にとって「宗教」の定義とは「幸福や不幸のカタチを定義し、それを押し付けてくるもの」すべて。
幸福や不幸の定義なんぞは、自らがその頭でしっかりと問い続けるから、どうぞご心配なくという感じ。
人類が何万年かけて脳みそのシワを増やしてきたと思ってるんだ。
支配させない (2018.2.26 9:48)
自らの精神を「幸福」にも「不幸」にも支配させない。
この境地を目指すべく「占い」を学ぶのはありなんだけど、学べば学ぶほどむしろ幸不幸に支配されちゃうヒトっているよね。
そんなヒトは「占い」から離れた方がいいと思うな。
ピンとこない数 (2018.2.25 20:29)
「1」から「9」、そして「0」という十個の数のイメージを相談者に見せ、その中から最も当人にとって当てはまらない(ピンとこない)ものを選ばせる。
その数を拠り所にして、当人の分析を図る。
全ての数の要素を持って生まれてくるヒトが、成長のどの段階でその数の要素を失ったのかを探っていく。
人でなし (2018.2.25 17:47)
常識や倫理に反しないよう、他人や社会に迷惑をかけないよう、いろんなことを辛抱しながら頑張って生きるヒト。
つまり「人であり」をし過ぎるヒトは、もう少し「人でなし」になってもいいんじゃないかな。
あえて「人でなし」エッセンスを取り入れることで、自らの心身の破綻を未然に防ぐんだ。
あるがまま (2018.2.25 14:23)
自他の間の「(繋ぐ・分ける)線」を曖昧にぼかしていくのが「9」という数。
「見る」けれども「観ない」。
「聞く」けれども「聴かない」。
つまり目や耳から何かが入ってくることを拒みはしないが、積極的に取り込むこともしない。
ただ「あるがまま」でいる。
それが「9(無為自然)」の境地。
荒れ狂う思考の理由 (2018.2.25 13:37)
自らの思考がカオスに荒れ狂う様を表すのが正に「7」であり、そんな「7」を活性化させる一因となるのが過剰な逆数「2」という「線」である。
よく「観る」から、思考が荒れ狂う。
よく「聴く」から、思考が荒れ狂う。
よく「繋がる」から、思考が荒れ狂う。
よく「隔てる」から、思考が荒れ狂う。
逆数秘術の後藤 (2018.2.25 13:23)
以前は「数秘術師」や「逆数秘術師」とメールなどで名乗っていたけれど、最近は「逆数秘術の後藤」と名乗るようになったね。
つまり「逆数秘術」を扱う「僕」というイメージではなく、あたかも「僕」自身が「逆数秘術」であるという一体化したイメージ。
まぁそれくらいの年月は費やしてきたからね。
アートの瑞々しさ (2018.2.25 12:54)
社会に生きるヒトが何かを「3(アート・表現)」として外へ出そうとすると、自動的に「6(デザイン・調整)」機能が働き、自らの表現の危険性を考慮し始める。
誰かを傷つけはしないか。
良識を掻き乱すのではないか。
この行為に意味はあるのか。
この「6」が過剰に働くと、「3」は瑞々しさを失う。
外へのアート (2018.2.25 12:29)
「3」は「外へのアート」。
「7」は「内へのアート」。
自らの精神にて行われる「7」的アートをやたらと続けていると、精神はゲシュタルト崩壊を起こしかねない。
だからこそ「3」を駆使して、アートを「外」へと露出させていく。
まるで自らの精神を「剥き出し」にするかのように。
前・言語 (2018.2.24 20:48)
「7(非言語思考)」を「2(言語思考)」に翻訳することはできる(ただし翻訳漏れが発生する)。
しかし「2(言語思考)」を「7(非言語思考)」に翻訳することはできない。
「2」は意思疎通ができる「共通言語」足り得るが、「7」はあくまでも個々人の精神でしか使用できない「前・言語」だからだ。
逃げ切る (2018.2.24 9:59)
人生、どうせ逃げるのならば、いっそ逃げ切っちゃおうぜ。
将軍 (2018.2.24 8:50)
仕事でも健康でも、誰かがベストを尽くせるよう、影でシステムを緻密に構築して支えるのが「8」マインドの持ち味。
これは言わば「見えないリーダーシップ」であり、その築き上げたシステムや組織自体が「カリスマ性」を帯び始める。
単騎で駆ける「1」が「戦士」ならば、「8」は正に「将軍」だ。
「相性」じゃない (2018.2.23 17:53)
「相性」が合わないんじゃなくて、ただ相手の表現が合わないだけ。
「相性」が合わないんじゃなくて、ただ相手の習慣が合わないだけ。
「相性」が合わないんじゃなくて、ただ相手の思想が合わないだけ。
自らの不快を「相性」という言葉でざっくりとまとめるのをやめて、もう少し分析してみようよ。
「0」も優しさ (2018.2.22 21:38)
数秘において「どの数が一番優しいか?」などというテーマを見ると、少し残念に思う。
たとえば僕は「1」〜「9」、そして「0」という十種の数を用いるけれど、優しさだって十パターンに分けられるんだ。
もし誰かが愛でお腹いっぱいになったなら、「0(無関心)」ですら一つの優しさになるのだから。
ゴールは無くとも (2018.2.22 16:33)
僕は日々「逆数秘術」について考え、思い付いたことをすぐさまツイートするという行為自体が目的化しているから、それ以外に特に目的を設けることが無いんだよね。
スタートラインもぼやけ、ゴールラインすら不明な道をただ延々と走り続けている感じ。
ゴールを設けなくても、充足はできるんだよ。
こじらせた「壁」 (2018.2.22 15:30)
「4(保守)」をこじらせた僕は「自身や近い人が迷惑を被らなければ、世界がどうなろうと構わない」という絶対防御の「壁」を構築し、心身を守っている。
そんな「壁」の外で展開される「5(革新)」的なイベントに対してはワクワクしつつも、危ぶむあまり参加はせず、ただ横目で眺めるにとどまる。
真理は一つ? (2018.2.22 9:42)
世の中には様々な宗教が存在するけれど、これらに共通するのは「真理は一つ」という捉え方であり、これは正に「超・宗教」というイメージ。
でもこの「真理は一つ」という絶対的教義こそが、世界に蔓延る諸問題の根源である気がするんだ。
そもそも「真理」は「一つ」でなければいけないのかい?
パズルゲーマー (2018.2.22 9:15)
「8(意志のコスモス)」とは、目の前に次々現れるピースを崩さぬよう隙間なく埋めていくパズルゲーマー。
しかしピースである「1(意志のカオス)」の総量が「8」のキャパシティを超えたなら、突如としてフリーズしてしまう。
自らの「1」という荒ぶる意志を減らせたなら、名ゲーマーの仲間入りだ。
感情を「調理」する (2018.2.22 8:36)
「3(感情のカオス)」マインドが自らの喜怒哀楽をそのまま(時にはオーバーに)表現するのに対し、「6(感情のコスモス)」マインドは自らの喜怒哀楽を「調理」して洗練させるイメージ。
控えめに盛り付けられた一つ一つの感情からは雑味が消え、喜怒哀楽のエッセンスがじわりと心に染み渡ってくる。
エネルゲイア (2018.2.21 21:39)
アリストテレスが分けて捉えた「エネルゲイア (活動)」と「キーネーシス(運動)」。
前者はダンスのように行為自体が意味を持つものであり、奇数(動的・混沌・チカラ・コドモ)的。
後者は始点と終点を持ち、移動や達成がその目的となるものであり、偶数(静的・秩序・カタチ・オトナ)的。
「生き辛さ」の開陳 (2018.2.21 19:39)
「マスターナンバー」の利点があるとすれば、それはマスターナンバーであることを指摘された当人は、自らの「生き辛さ」を開陳しやすくなるということかな。
問題となるのは、せっかく開陳された「生き辛さ」を単純に「マスターナンバー」のせいにして終わらせてしまうこと。
これは実に勿体ない。
楽園 (2018.2.21 16:54)
マスターナンバーの「33」は単数変換すれば「6」であり、そして「6」マインドの強い人は集団や社会常識からの逸脱に対する「羞恥」を抱きやすい。
そんな思いに苦しむ「6」にとって、自らが「33」という特別扱いの数を与えられることにより、その数がまるで「逸脱者にとっての楽園」として機能する。
海に浮かぶ船 (2018.2.21 15:58)
「自分の心を安定させる」という表現は、まるで安定自体がスタンダードな印象を与える。
でも実際のヒトの心は、正に海に浮かぶ船のようなものであり、完全に安定すること自体が幻のようなもの。
大嵐の状態に比べれば、凪の時には安定しているように見えるけれど、実際には常に揺れ動き続けている。
脱構築 (2018.2.21 11:14)
現代社会において幾重にも構築された偶数(静的・秩序・カタチ・オトナ)的合理主義。
その中において封じ込められがちな奇数(動的・混沌・チカラ・コドモ)を用いて、絶対化された合理主義的価値観を解体し、偶数との相対化によって奇数を復権させていく。
それが広義の「脱構築」ということか。
自動ブレーキ (2018.2.21 10:05)
現代社会で生きるということは、既に偶数(静的・秩序・カタチ・オトナ)をフル活用しているということ。
そんな中で奇数(動的・混沌・チカラ・コドモ)を出すことを怖れる必要はない。
危険を察知した自らの中の偶数が、勝手にブレーキを掛けてくれるから。
だから存分に奇数を発揮すればいい。
フリーダム (2018.2.21 9:43)
自分以外の存在を「8(コントロール)」することをやめ、更に自分自身をコントロールすることすらも弱めていく。
コントロールできた実績を後付けで「自信」へと置き換えることをやめ、自らの存在自体が「自信」の源であることを思い出していく。
それが「1(フリーダム)」への回帰の近道となる。
桁数 (2018.2.21 9:20)
僕がなぜ「ルートナンバー(1〜9、0)」にこだわるかというと、桁数自体に「価値」を与えることを防ぐため。
一桁よりも二桁、二桁よりも三桁などと、いわゆる「多い」ということに価値を置き始めるのが怖いと感じる。
多い・少ないの差異を消すことにより、価値の高低を生み出す隙を無くしていく。
広めよ、助けよ (2018.2.20 22:20)
「6(助ける)」したければ「3(広める)」したまえ。
「3(広める)」したければ「6(助ける)」したまえ。
その思想・手法で本当に人が助けられると信じるのなら、躊躇せずに広めていけばいい。
その思想・手法を本当に広めていきたいと望むのなら、まず目の前の人を助ければいい。
不立文字 (2018.2.20 21:59)
「文字」を用いて意味を固定化する「2(関連・定義)」機能に対し、「7(検証・疑義)」機能を用いて個人がそれぞれに解釈し直す行為。
それを危ぶんだ(禅宗開祖とされる)達磨が「悟りを開くためには、あえて文字(経文等)を立てない」と戒めたのが「不立文字(ふりゅうもんじ)」というわけか。
へその緒 (2018.2.20 17:48)
この世に生を受けた時、リアルなへその緒が断ち切られると同時に「バーチャルなへその緒」が親と子を結び付ける。
子供が独り立ちをするということは、この「バーチャルなへその緒」を断ち切ることなんじゃないかな。
でもこのへその緒は頑丈だから、研ぎ澄ませた心のハサミでないと切れやしない。
過労美 (2018.2.20 14:03)
「過労死」の原因は「過労美」なんだと思うな。
命知らず (2018.2.20 13:34)
群れから外れた小魚が捕食されるように、ヒトが群れから外れる行為も元来は命がけ。
そんな集団という偶数性に対して美や倫理的価値を与える「6」マインドからすれば、そこから外れる奇数の「3」マインドは命知らずの「恥」扱いとなる。
でも「3」からすれば、集団に留まる「6」こそ命知らずなのだ。
「低刺激」な環境へ (2018.2.20 8:57)
「私って性格悪いよなぁ」などと悩む人は、思い切って「環境(ネットも含めた人間関係全般)」を変えてみるといいかもね。
「環境」による刺激に対する反応パターンこそが、いわゆる「性格」と呼ばれるものなわけだから。
低刺激な「環境」に移れば、穏やかさを取り戻せるんじゃないかな。たぶんね。
国民栄誉賞 (2018.2.19 21:26)
生きてるだけで国民栄誉賞。
○○座時代 (2018.2.19 0:18)
いわゆる「○○座時代」という長い括りだけど、あまりにも便利に使われている感があるね。
この概念を遠い過去に遡れば、数万年単位での人類の停滞期を説明するのが難しくなる。
人類の過去を測るには短過ぎるし、未来を測るには長過ぎる、半端な長さの「ものさし」というイメージ。
「神」の二相 (2018.2.18 15:43)
始原の数としての「1」とは「(唯一)神」でもあるが、これは奇数つまり「チカラとしての神」であり、見えず触れぬ絶対的存在。
そんな神に「カタチとしての神」という偶数性を与えるのが逆数の「8」であり、言語で作られた「理性のアーカイブス」によって可視化・可触化・相対化・概念化されていく。
順番 (2018.2.18 15:13)
数秘の流派によっては、数の「順番」を重視するケースがあるが、僕はその辺りはあまりこだわっていない。
「1」から始まって「9」へと向かえば「9」が完成となるだろうが、「9」から反対に「1」へと向かえば「1」が完成となる。
進むのは「順」でも「逆」でも構わないし、一足飛びでも構わないんだ。
理性の摩天楼 (2018.2.18 11:40)
「1(個人)」が「1」として屹立できるのは、まさに逆数「8(集団)」というバックボーンがあってこそ。
そんな「8」にはヒトの集まり、ヒエラルキー、システム、プロジェクト、スケジュール、更には法体系や学問体系なども含まれる。
「1」が「野性の裸神」ならば、「8」は「理性の摩天楼」だ。
「全」に溶け切る (2018.2.18 11:32)
「8」とは集団、組織、社会、そしてシステムを表す数だが、まだ「9(全)」には至っていない。
「8」であるが故に、逆数「1(個)」という棘が常に集団への同化を妨げるべく突き刺さる。
「9」へと至るということは、つまりは「全」に溶け切るべく、逆数「0(虚無)」で「無我」を作るということだ。
飽きたから (2018.2.17 22:33)
そういえばリハビリついでにやっていた「無料ダイス占い」だけど、飽きたため昨日終了させたところ。
まぁまた気が向いたらやるかもしれないけど、今はあまり占いモードでは無くなったってのも大きいな。
また哲学方面(哲学とは言っていない)へと戻るかな。
釣竿 (2018.2.17 10:44)
「7(思考のカオス)」という「泥沼」から「2(思考のコスモス)」という「釣竿」を駆使して、カタチある思考を釣り上げていく。
ここでいう「釣竿」とは「言語」であり、あらゆる思考を釣り上げるべくボキャブラリー、つまり「釣竿」のレパートリーを増やしていく。
きっと大物が釣れることだろう。
1+1 (2018.2.16 21:10)
【数学】1+1=2
【数秘術】「1」+「1」=「1」バタッ(どちらかの「1」が倒れる音)
幸せ (2018.2.16 13:44)
「3(自己愛)」マインド「幸せになる!」
「6(他者愛)」マインド「幸せにする!」
「9(博愛)」マインド「幸せとか良くわかんな〜い!」
「予防」の逆効果 (2018.2.15 19:50)
「2」で表される「分かつ線」は90°回すと「繋がる線」となる。
たとえば「引き寄せの法則」を用いようとして、逆に絶対に引き寄せたくないものを強くイメージすることで、かえってその引き寄せたくないものが引き寄せられたりもする。
ある意味「予防」がかえって仇となるケースもあるということだ。
「2」という「選別」 (2018.2.15 19:28一部改変)
「2」には確かに「受容」の意もあるが、それは闇雲に繋がるわけではなく、きちんと「選別」を経ている。
なので当然ながらその「選別」から漏れたものは「拒絶」の対象となってしまう。
そして対象を「選別」しようとする時点で、既に明確な「線引き」が行われてしまっているわけだ。
「自信」の根拠 (2018.2.15 8:50)
「8」マインドにとって「自信」とは根拠が必要なものであり、自らの計画やスケジュールを一つ一つ達成することにより、その実績が「自信」へと変換されていく。
そのため、自らの意志で計画を休止したり、スケジュールをわざと空けていく行為に抵抗感を覚えてしまう。
「自信」の根拠が減るからだ。
「絶交」という関係 (2018.2.15 8:41)
「2」とは「線を引く」数であり、「関係」を表す数。
つまり交流という「繋ぐ線」も、絶交という「分ける線」も、共に「関係」ということになる。
通常では絶交を「関係」と呼ぶのは難しいだろうが、絶交相手を強く意識している以上、それは「関係」の継続であるということになってしまうわけだ。
広い「中庸」 (2018.2.15 8:29)
逆数秘術では奇数と偶数の混交である「9」を統合かつ「中庸」のシンボルとし、まずはその境地を目指す。
「中庸」に至ろうとする際は自らだけでそれを完遂させるのではなく、他者との関係性における「中庸」や大自然の中における「中庸」なども意識していく。
全てとバランスを取るということだ。
一粒万倍日 (2018.2.14 13:38)
僕は「一粒万倍日」と聞くと、どうしてもドラえもんの「バイバイン」を思い出しちゃうんだよね。
宇宙が終わる吉日。
形而上学 (2018.2.14 8:14)
逆数秘術的には奇数(動的・混沌・チカラ・コドモ)の「7」は「形而上学」、つまり現象の背後にある《本質》を探求するイメージであり、世界・存在・霊魂などがその対象となる。
そして偶数(静的・秩序・カタチ・オトナ)の「8」は「形而下学(唯物論)」、偶奇混交の「9」は「自然」のイメージ。
迎合 (2018.2.13 21:52)
ダイスでもカードでも、自らについて占った際にやたらと「今の自らの気持ち」を代弁するかのようなイメージばかりが出てしまう時は、むしろ自身を占うことから少し離れた方がいいんじゃないかな。
ダイスやカードがやたらと占者に「迎合」し始めるのは、あまり良いこととは思えないからね。
義理チョコ (2018.2.13 19:23)
義理チョコを数秘的に言い換えるなら「6」チョコかな。
日々お世話になっている人々にあげる「ホスピタリティ」なチョコ。
それに対する「3」チョコは「チョコは大好きな人にしかあげないに決まってんじゃんバーカ!」という感じに「エロス(純愛)」でこれ見よがしにラッピングされているイメージ。
偶数まみれの子供 (2018.2.13 10:09)
偶数(静的・秩序・カタチ・オトナ)まみれの子供をイメージしてみる。
「2」:「お母さんを信じてあげなきゃ」
「4」:「お母さんの言い付けを守らなきゃ」
「6」:「お母さんに迷惑かけないようにしなきゃ」
「8」:「お母さんのためにも我慢しなきゃ」
健気を通り越して、ただ心苦しいだけ。
アルバム (2018.2.12 23:14)
「8」的に生きることとは、たとえるならページ数の限られたアルバムの中に、最良のセルフブロマイドをどれだけ収められるかを慎重に吟味するイメージ。
一方「9」的に生きることとは、アルバムのページ数も写真数も無限にあるかのように感じ、だったら別にいつでもいいやとのんびり構えるイメージ。
なるようになるデー (2018.2.12 22:52)
今年のバレンタインデーは「9」の日になるのか。
まぁ「なるようになる」だろうし、世の中「成功」と「失敗」にくっきりと分けられるものばかりじゃないからね。
それが「9」という数さ。
レイヤー状の魂 (2018.2.12 22:27)
「1」がシンプルかつ唯一無二の「魂」だとするならば、対する「8」は幾人もの「魂」がまるで地層の如く何層にも積み重なった「レイヤー状の魂」と捉えることができる。
そんな身に覚えのない魂の重さに耐えかねた「8」が、その魂の群れの中から唯一無二の「1」を求めようとするのはもっともなことだ。
失せ物探し (2018.2.12 22:06)
もしヌメロダイスにて失せ物探しをやったなら。
「1」占うより勘に頼れ
「2」誰かが見つけてくれる
「3」別のを買おうぜ
「4」箱などに入ってる
「5」ありえん場所にある
「6」掃除したら出てくる
「7」行き先を思い出せ
「8」押し潰されてる
「9」まぁ放っておこうぜ
「0」探すだけ無駄
罪滅ぼし (2018.2.11 11:56)
「自分だけが遊び楽しむことに罪悪感を覚える」というのは「6」マインドの現れ。
自らが存分に「3(遊楽)」に興じるための「罪滅ぼし」として、まずは「6(奉仕)」を徹底するイメージ。
まず偶数(静的・秩序・カタチ・オトナ)を優先し、後に奇数(動的・混沌・チカラ・コドモ)を許可していく。
かませ犬 (2018.2.10 21:37)
Q:「不幸」とは何ですか?
A:「幸福」な人の幸福度を高めるために用意された「かませ犬」
Q:「幸福」とは何ですか?
A:「不幸」な人の不幸度を高めるために用意された「かませ犬」
「期待」という牢獄 (2018.2.10 21:28)
期待されていた選手が期待を裏切る結果を出した際、それを見て何となくホッとする人は一定数いるんだろうなぁ。
まるで「期待」という牢獄から解放されたかのようにね。
不自由を定義する (2018.2.10 20:48)
自らが真に「5(自由)」であるためには、対となる「4(不自由)」をきちんと定義する必要がある。
自らにとってどのようなものが「4(不自由)」となるのかを正しく定めないと、無秩序かつ反発的に「5(自由)」を求めるレジスタンスを続けることになる。
それはもはや「自由という名の不自由」だ。
「毒」から守る術 (2018.2.10 15:49)
「4」と「5」は共に「感覚(body)」の数。
もし「毒々しい」何かが周囲に満ちていたとして、その人が「4(静の感覚)」優位であれば、自らの感覚を極限まで鈍らせることで自身を守る。
逆に「5(動の感覚)」優位であれば、自らの感覚を極限まで鋭くさせることで、その環境から迅速なる離脱を図る。
勘違いしてナンボ (2018.2.10 14:45)
てなわけで吉祥寺駅のスタバにてメール鑑定文を作成し終えたところ。
カフェで仕事をしていると、何となく「忙しい感」「仕事できる感」「スマート感」などによりステキな「勘違い」ができていいね。
まぁ人生「勘違いしてナンボ」だとは思うけど。
思考の鎮静化 (2018.2.9 11:01一部改変)
荒ぶる思考を鎮めるための「感じろ(=思考の割合を減らす)」ならいいんだけど、思考を完全に排除するというのはよろしくないよなぁ。
「思考」は悪? (2018.2.9 8:46)
そもそも自らにおける「幸せ」の再定義を可能とするのは「思考」という機能があってこそなのだから、たまに見かける「思考」を蔑ろにするようなスピリチュアルにはあまり賛同できないんだよね。
荒ぶる「思考」を鎮めるのならばいいんだけど、「思考」自体を悪と断じる思想は果たして如何なものか。
「描く」というチカラ (2018.2.8 22:00)
「3(アート)」という名のワークには「コスモス(秩序)による縛りを解き放ち、自らにカオスを取り戻す」効能がある。
たとえば「絵」を描くならば、模写・技法・技術・技巧・材料・評価などのカタチから自らを解放し、子供の落書きのようにただ楽しく「描く」というチカラを存分にふるえばいい。
「アート」というワーク (2018.2.8 21:40)
自らの波打つ感情をありのままに、いや、それよりも更に激しく、自身の内側から外へと産み出していく。
その出したチカラを他人にわかりやすいカタチに纏めなくていいし、その行為に意味・意義・価値などは必要ない。
ただ心の赴くままに吐き出していく。
これが「3(アート)」という名のワーク。
「アート」の役割 (2018.2.8 20:57)
過剰な「6」に苦しむ、要は社会や他者の役に立つという「使命」に縛られ過ぎてしまい、自らをとことん追い込んでしまう人。
そんな人には「3」的なアート活動を通じて「たとえ何の役にも立たなくても《アート》はそれだけで存在価値や意義がある」と気付かせることにより、「9」的な「中和」を図る。
「成長」からの脱出 (2018.2.8 13:47)
「3」には「成長」や「拡大」のイメージもあるけれど、そんな「3」というカオスかつダイナミックな数は以下のようなことを教えてくれる。
「《成長とは苦しみを伴うものだ》などという堅苦しく不自由な思い込みから一刻も早く脱出しよう!自由に楽しみ続けたってヒトはきちんと成長できるんだから!」
乱暴な「一般化」 (2018.2.7 22:00)
たとえば、とある男性に騙された女性がいたとして、その女性の頭は当然ながら「7(疑念)」という思考のカオスで満たされる。
するとその状態に耐えかねた頭は「男はみんな騙してくるものよ!」などと極めて乱暴に一般化し、その法則を「2(信用)」しきることで思考のコスモス(秩序)を取り戻す。
ジレンマと統合 (2018.2.7 21:27)
自らの「4(保守)」と「5(変化)」のジレンマに苦しむケース。
つまり「変わりたい!でも変わりたくない!」という類の揺れ動き。
別にこれは「4」の人や「5」の人に限った話ではなく、誰の心にも訪れるもの。
「変わっても変わらなくても私は私」という「9」への統合により、ジレンマは離れる。
「伝統」に逆らう (2018.2.7 11:44)
占いにおいて脈々と受け継がれてきた「象徴体系の伝統」を尊ぶべしというのはわからなくもない。
でも伝統とは「革新」の連続によって磨かれてきたものであり、つまりは伝統をあえて破壊する行為ですら、伝統を伝統足らしめる行為の一つとなる。
だから別に伝統に逆らう人がいたっていいと思うんだ。
本来の「3」はどこ? (2018.2.6 14:08)
子供の頃に親から「決して他人を悲しませたり不安にしてはいけない」などというような「6」を至上とする教育を受け、それを頑なに守る人。
この人がいくら表面的には「3」的に明るく奔放に振舞っていたとしても、それは「3」の仮面をつけた「6」かもしれない。
その人本来の「3」はどこにあるのか。
本心か、戦略か (2018.2.6 13:48)
たとえば明るくペラペラと喋る人に対して「この人は「3」の人(または「3」を多く持つ人)だから」と説明するのが既存の現代数秘術。
でも「逆数秘術」の場合は、その「明るくペラペラと喋る」理由を環境とそれに対応する心の動きから探っていく。
その振る舞いが本心か戦略かで大きく変わるからだ。
容認 (2018.2.6 13:18一部改変)
個人の奇数(動的・混沌・チカラ・コドモ)性の発露を偶数(静的・秩序・カタチ・オトナ)的な社会の側が容認できるかどうかというのは、かなり大事なポイントかもね。
「神秘」から離れる (2018.2.6 12:31)
昔から僕は「自説を補強するために、徒らに《神秘》や《神聖》をこねくり回す」行為に対し、ある種の警戒感を抱いている。
だから「神秘」や「神聖」の礼賛からも畏怖からも、僕は距離を置くようにしている。
僕は数秘術から「神秘」などを取り除いた「逆数秘術」でこじつけ遊びをしているだけ。
獣の数字 (2018.2.6 11:59)
いわゆる「獣の数字」と呼ばれる「666(異説では616)」は「六百六十六」であり、ただ「6」が三つ並んでいるわけではないんだよね。
だから時々見かけるウェブの「www」を「666」にこじつける(ラテン文字の「w」はヘブライ文字の「ו(ヴァヴ・数価6)」に対応)ことには、少し違和感を抱いているよ。
生年月日が不明でも (2018.2.6 10:38)
一般的に「命術」における鑑定には生年月日(更には生時)が必須となる。
ただ「逆数秘術」は少し変わっていて、たとえ生年月日が不明であっても、対象人物の第一印象を「数」に置き換えて、それを元に逆数や補数などを当てはめての鑑定が可能。
もちろん氏名をゲマトリアしたものでも構わない。
なんとなく (2018.2.5 20:30)
「1(自我)」から最も遠いところにあるのが「9(無我)」のイメージ。
「1」のアクションが「衝動的」のイメージだとするならば、「9」のそれは「なんとなく」のイメージ。
何かしらの明確な目標・理由・意志があるわけではなく、ぼんやりかつ曖昧な意識で事を為す数。
正に「人為の諦め」だ。
構造を暴く「7」 (2018.2.5 15:59)
逆数秘術において奇数(動的・混沌・チカラ・コドモ)最大の「7」とは、正に「オトナによって作られた社会構造というカタチを一から問い質す」イメージ。
「7」には哲学者のイメージもあるが、言い換えるなら「コドモ性をこじらせたオトナ」という感じ。
「なんで?どうして?」を武器に構造を暴く。
弁明つき反発 (2018.2.5 15:40)
既存の価値観に対する「3」的な「不快なものへの感情的反発」が持つ子供っぽさに耐えかね、ヒトはそれに「6」的な矯正・教導・保護のイメージを与えて大人ぶる。
つまり「本当はこんなこと言いたくないが、その言動により苦しむ人もいるのだから見過ごすわけにはいかない!」という弁明つき反発だ。
「6」への批判 (2018.2.5 15:33)
母の子に対する「6(献身愛)」的な歌が一部で批判を浴びているらしい。
「献身」を「犠牲」と捉えてしまう風潮は行き過ぎた逆数「3(利己愛)」の現れとも言えるが、最近は特に「6」的概念が批判の矢面に立たされることが増えた印象がある。
それも「3」的な「不快なものへの感情的反発」が著しい。
二つの「叛逆」 (2018.2.4 12:09)
逆数秘術的に偶数(静的・秩序・カタチ・オトナ)は構造側の数であり、対する奇数(動的・混沌・チカラ・コドモ)は構造への「叛逆」を表す。
しかし奇数は構造の「外」へと向かう叛逆、偶数は構造の「内」に属したまま行う叛逆と言い換えることもできる。
前者は家出、後者は引きこもりのイメージ。
結婚願望の正体 (2018.2.4 12:00)
あなたの「結婚したい!」の正体は「結婚しなければならない」という強迫観念かもしれないね。
つまり純粋な自らの意志ではなく、社会構造(親・親族・友人・目上の人など)の側からの有形無形の圧力によってコントロールされているだけかも。
結婚なんて本当に「望む」人だけがすればいいんだ。
使わぬ「相性」 (2018.2.4 11:55)
僕は逆数秘術において「相性」という概念を用いていない。
なぜならヒトは多面性を持っており、シチュエーションによって奇数性や偶数性を出し入れしているため、一概に(単純に)関係性の評価を下せないから。
それにそもそも「相性」が良ければ結ばれるというものでもないし。
「浄化」の徒労 (2018.2.4 11:23)
汚れたプールからコップ一杯の水をすくい取って綺麗にし、再びプールへと戻していく。
占いやセラピーやヒーリングによっていくら「個」が浄化されたとしても、戻っていく「社会」の側が汚れたままでは正直埒(らち)があかない。
「社会」の浄化が見込めないならば、いっそ「外」へ出てもいいさ。
無神論と不可知論 (2018.2.4 10:38)
いわゆる「無神論」とは「神」の実在を「7」機能を駆使して疑い抜いたあげく、今度は「2」に反転して「無神」であることを信じ抜く、言わば「宗教」なんだろうな。
もし「2」に反転せず「7」のままでいたならば、おそらくは「不可知論(物事の本質はヒトには認識不可能)」を支持するだろうから。
「自我」の認識 (2018.2.3 18:07一部改変)
いわゆる「自我の観察者としての自我」を表し得るのが「2」だったりする。
つまり「2」があるから、ヒトは初めて「自我」を認識できるとも言えるわけだ。
親切 (2018.2.3 17:43)
「6」とは他者を慮り、慈しみ、慎み深く奉仕する数。
とはいえ相手も「6」的に慎み深ければ、こちらの親切を遠慮され続けてしまう。
そんな相手の「6」的な慎みの壁を、逆数「3」というオーバーなまでの「ぜひぜひ!」で軽々と乗り越えていく。
そんな「6」と「3」の合わせ技で親切が達成される。
疲れる「ビジネス」 (2018.2.3 12:23)
僕も人のことは言えないんだけど、facebookを見ていたら色んな人の講座案内がドバーッと流れてきて、なんだか疲れちゃったな。
もうね、みんな「ビジネス」やり過ぎ感がすごい。
「逆数秘術」については幾らでも話したいんだけど、あんまり「ビジネス」はやりたくないんだよね。
自分との「約束」 (2018.2.3 11:45)
「2」という線は「約束(契約)」を表し得る。
これは通常、自身と他者の二者による約束(契約)となるが、自らと「他者的」な自らとの間に交わす約束(契約)にもなる。
自らが自分自身との間に取り決めた約束(契約)をきちんと履行することで、変化の荒波にも負けないコスモス(秩序)となる。
「言語」は命綱 (2018.2.2 8:03)
動的・カオスな思考を表す「7」は内観や内省をも表す。
しかしそこに「7」しか無ければ、待つのは非言語的イメージのざわめきのみ。
「7」を活かすには、逆数「2」という静的・コスモスの思考、つまり「特定の言語的イメージとの固い結びつき」が大切。
思想、文章、知識、これらが「命綱」となる。
頑固 (2018.2.1 23:14)
そもそも「頑固」とは、実に「相対的」なもの。
奇数(動的・混沌・チカラ・コドモ)的な状況下においては偶数(静的・秩序・カタチ・オトナ)的な振る舞いが「頑固」と見なされるし、逆もまた然り。
だから数秘術において一概にどの数が「頑固」とは言えず、それを決めるのは自他の「差異」となる。
相手の気持ち (2018.2.1 13:54)
占いにて慎重に「相手の気持ち」を確かめ、相手にこちらへの好意が多少でもあるならば、ようやくにして一歩を踏み出そうとする試み。
でもそんな迂遠なことをしていると、やがて「当たって砕けろ」精神全開の第三者に相手をサッと奪われちゃうかもよ。
「巧遅は拙速に如かず」ってね。
仕立て上げる (2018.2.1 13:08)
(多分少し前の僕のツイート絡みの質問だと思うけど)「運命の人に仕立て上げる」とは、相手を変えることでもあるけれど、それよりは自身の中で相手の存在や性質をゆっくりと馴染ませる「自己変容」の方にウエイトを置いているよ。
つまり「自らの心に住まう相手」を変えていくイメージに近いかな。