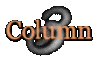
数秘術関連等ツイート(2016年3月分)
病的依存パターン (2016.3.31 23:45)
重度の依存、つまり病的なまでに「2(関係性)」に拘る人が陥るパターンは二つ。
一つは逆数「7」を駆使し、自らの精神世界で相手との関係性を妄想する非現実的アプローチ。
もう一つは補数「8」を駆使し、相手を精神的肉体的に縛るような言葉を用いてコントロールする現実的アプローチ。
ナイチンゲール (2016.3.31 13:31他)
「1」の女性が自らの「1」をフルに発揮して生きることで達成し得る一つの理想像は「1」のナイチンゲールだろう。
もちろん逆数「8(制御)」をツールとして駆使しなければあれだけのことはこなせないけれど、自らの「1」という強大な《ベクトル》あってこそ使うツールの威力も増すというもの。
組織を統率し、皆の意識を一つの目標に向かわせていく際に必要となるのが「8(コントロール力)」。
しかしただ「8」を駆使するだけの手練手管にのみ拘っていては、小さな目標しか達成できない。
リーダーの中にある「1(ベクトル)」の強さや熱さが「8」の及ぶ範囲を広げ、効果を高める。
開き直った奉仕 (2016.3.30 19:06)
「他者を助けるために私は生きる」という使命感で頑張るのではなく「他者を助けているのは私が私自身を助けるために他者を利用しているだけに過ぎない」と開き直った方がいろいろとスムーズになることもあるね。
重苦しい権威 (2016.3.30 18:57)
今日の打合せの時「後藤さんは自らの占い師としての権威性を自ら低めている感じですね」的な感じのことを言われたけど、これはもうその通りだしそれこそが僕の自然体だね。
外向きの自分を作って後で自己矛盾に苦しむくらいなら、初めから素の自分でいた方がラクだし、そもそも権威は重苦しいだけ。
権威に逆らう数 (2016.3.30 18:24)
奇数とは権威に逆らう数とも言える。
権威の存在を一切意識しない「1」マインド。
権威をからかい舐めてかかる「3」マインド。
権威に真っ向から抗っていく「5」マインド。
権威の細部まで徹底的に疑う「7」マインド。
偶奇両有の「9」は権威をのらりくらりと玉虫色にやり過ごす。
好きなのは何? (2016.3.30 14:30)
そのヒトが好きなのか。
その男性(女性)が好きなのか。
その男性性(女性性)が好きなのか。
立ち止まって考えてみるのもありかも。
「奇跡」の拡散 (2016.3.30 14:17)
体験としての個人的《奇跡》ではなく、誰もが味わえる大衆的《奇跡》こそが大規模宗教の下地となる。
そう考えるとネットで拡散した《奇跡》が一部の知性による検証をかき消して、一気に世界宗教の下地となる可能性も出てくる。
既存の宗教はその《奇跡》に反発せず、むしろ利用することだろう。
男性性と女性性 (2016.3.30 11:47他)
その文化における男性に属する要素が《男性性》に集約され、女性に属する要素が《女性性》に集約される。
文化が変われば《男性性》と《女性性》の中身は当然変わり得るし、普遍的であるとされる文化が変わらない保証もない。
性の役割が流動化している時代、両者という幻に囚われなくてもいい。
文化的要素としての《男性性》と《女性性》という対概念を《人間性》という一つの概念に統合していく過程の真っ只中に我々は今生きている。
もちろん生物的な性質の違いはまだまだ残るだろうが、それすらも少しずつではあるが往復可能な状態になっていくだろう。
どちらにもなれるという自由。
波乱万丈の理由付け (2016.3.30 10:28)
そろそろ「マスターナンバーだから人生波乱万丈なんだ」という表現(ないし思い込み)は何とかならないものだろうか。
ルートナンバー(1〜9)を一体何だと思っているのか。
陰と陽 (2016.3.30 10:23)
僕は逆数秘術において、奇数⇔偶数の対称性に動的⇔静的、混沌⇔秩序、チカラ⇔カタチと当てはめているが、《陰》と《陽》には当てはめていない。
そもそも陰と陽は一つの数の中に混交して存在し、他の概念のように切り離して捉えられないから。
そういう意味では偶奇両有の「9」的概念かも。
「運命」と数 (2016.3.29 22:45)
《運命》を無視する「1」、準備する「8」。
《運命》を堪能する「3」、注意する「6」。
《運命》に抵抗する「5」、忍従する「4」。
《運命》を検証する「7」、信用する「2」。
《運命》に動性・混沌で接する奇数、静性・秩序で接する偶数、そして溶け込んで忘れ去る「9」。
団体という歪み (2016.3.28 23:53)
とある存在を熱烈に盲信して(歪んだ「2」)、少数の同志が排他的な居場所を作り(歪んだ「4」)、独自の作法や様式美で世界を塗り替え始め(歪んだ「6」)、やがては巨大なヒエラルキーシステムとして君臨し始める(歪んだ「8」)。
習い事の団体や宗教団体などに忍び寄る歪んだ偶数性の罠だ。
情報の可視不可視 (2016.3.28 22:56)
「2」は見える情報、「7」は見えぬ情報。
「7」という非言語思考を積み重ねて「2」という言語化(定義化・関連付け)を行うのが「哲学」という行為。
「2」という言語テキスト(聖書・経文等)を学び尽くして「7」という非言語思考の極みに達しようとするのが「宗教」という行為。
「7」のアトム (2016.3.28 17:40一部追記)
鉄腕アトムの誕生日が2003年4月7日という情報が流れてきたので、基本数を出してみたら「7」だった。
ロボットである自らに苦悩、葛藤するアトムらしいといえばらしいし、作品全体に流れるテーマ性が正に「7」という感じもする。
そういえば「7つの力」なんてものもあったし、作者の手塚治虫も「7」の人だったね。
「不如意」を無くす (2016.3.27 22:47)
占いというツールは「不如意(思いのままにならない)」から「不」を取り除くためのものだと思うけど、更に一歩進んで「不如意」から「不如意」を取り除くものとして使うといいかも。
つまり「不如意」を「不如意」と思わなくなるようなアプローチであり、「なるようになるさ」の境地への道だね。
「生」と「死」の芸術 (2016.3.27 12:53)
自らの《生》をアートしていくのが「3」的な生き方であり、《死》なんぞ一切気にすることなくただひたすらに《生》を遊び尽くすイメージ。
自らの《死》をデザインしていくのが「6」的な生き方であり、より良い《死》を送るために逆算的により良く《生》を調えていくイメージ。
「手放し」の段階 (2016.3.27 11:44)
自らの去就を「7」的にうんうん悩まず、えいやっ!とダイスを転がして「2」的に決めるのが「手放し」の第一段階。
ダイスすら転がさず、どちらに進んだとしても「9」的にオーライと捉えるのが「手放し」の第二段階。
なお、全てに「0」的な虚無感を抱く「手放し」の第三段階はお勧めしない。
無意識に一番近い数 (2016.3.26 13:56)
「1」から「8」の人(な人)は自らの数や逆数・補数などは意識しやすいが、それ以外の数については無意識下に仕舞われやすい。
しかし「9」の人(な人)は全ての数が含まれている無意識と意識との間のベールが穴だらけなため、自由に通り抜けしやすい。
「9」とは無意識に一番近い数なんだ。
礼儀へのタブー (2016.3.26 12:09)
「6」という「礼儀」にとって、両隣の数(隣接数)である「5」と「7」はある種の「タブー」となる。
先人達によって脈々と受け継がれてきた「礼儀」の刷新や破壊を目論む「5」的な行為。
今まで当たり前のように行ってきた「礼儀」が本当に必要なものなのかを検証していく「7」的な行為。
非言語的イベント (2016.3.26 12:02)
本というのは著者の非言語的思考のカオスという「7」が、言語的思考のコスモスという「2」へと翻訳されたものだけど、著者の「7」を完全翻訳しているわけではない。
著者の「7」に直接触れるためには、感覚や直接的体験などの非言語的イベントの共有が必要となる。
「口伝」もその一つだ。
人間理解の種 (2016.3.25 23:30)
言葉と事象とを一対一で関連付ける、それは則ち思考のコスモス「2」であり、その約束事により人間は安心してコミュニケーションできる。
しかし、そんな約束事の陰に隠されてしまいがちな自らの中の思考のカオス「7」、つまり関連付け困難な非言語思考の中にこそ、人間理解の種が眠っている。
母体の延長 (2016.3.25 21:08)
子供という存在は本来、母体から生まれ出た時点で一つの《個》であるはずなんだけど、中には「母体の延長」として扱われる子供もいる。
子育てにおいて母と子の間に「2(線を引く)」を構築するのは大事だけど、繋ぐ線よりも実は子供を《個》として確立させる《分ける線》の方が大事なのかも。
個人とシステム (2016.3.25 16:25)
「1」という《個人志向》と「8」という《システム志向》。
でも「1」だからこそ「8」という大なるシステムへの所属願望が芽生えたりもするし、「8」だからこそ「1」という所属を脱した自由な身分への憧れが芽生えたりもする。
自らの志向の方向性がどちらなのかをじっくりと見極めよう。
「自己」の行方不明 (2016.3.25 8:03)
「9」という数は「境界線」がおぼろげになったりハッキリしたりを繰り返すことを表し得るが、自らの意識の境界線が明滅を繰り返し、マクロとミクロを自在に行き来できる「9」的な人もたまにいる。
でもこれは訓練を施さないと途端に「1(自己)」の行方不明へとつながってしまう恐れがある。
思考の共有 (2016.3.25 0:16)
自らの中の「7」という《動的思考》とは「言語」に囚われない思考であり、だからこその自由がある。
しかしその自由を行使すればするほど「2」という《静的思考》、つまり思考の言語化とそれに伴う他者との思考の共有が困難となる。
だからこそ共有のための一定の《選択ルール》が必要となる。
よそ見のツケ (2016.3.24 22:23)
人類による人類にとっての《絶望》は、その恐れの段階から前もって皆が注視し続けていれば、やって来ることはないだろう。
しかし、もしもよそ見をしていたり、注視せずにボーッとしていたならば、その《絶望》はあっという間に目前まで迫って来て、油断した我々に致命傷を負わせることだろう。
有益無益関係なく (2016.3.24 16:55)
とりあえず今現在、あなたが行っている「3」的な《表現行為》が人々や社会の中でどのように役立っていくのか、という「6」的な《有益性》の意味付けは周りの人々がそれこそ勝手に行ってくれることだろう。
だからまずは有益か無益かなんて関係なく、思う存分「3」を発揮しちゃえばいいんだ。
良質かつ豊富に (2016.3.24 16:03)
読書や鑑賞という良質かつ豊富な「2(インプット)」は、良質かつ豊富な「7(思索活動)」につながり、それはやがて良質かつ豊富な「3(アウトプット)」へと結実していく。
逆に言えば、良質かつ豊富な「3」や「7」に結び付かない「2」にやたらとこだわり続けるのは時間の無駄かもしれない。
満ちて、消える (2016.3.24 15:53)
自らが「9(満ちる)」の境地に達したなら、併せて「0(消える)」もやってくる。
自らの《生》が「9(満ちる)」であると感じられるようになれば、あらゆる不安や恐怖、更には過剰な希望や情熱は「0(消える)」により無くなっていく。
この境地に達するため、全ての「数」を味わい尽くす。
創られて、磨かれる (2016.3.24 15:20)
とある一つの目的を達成するために、それをより洗練させていくのが「6」というデザイン。
とある一つの目的からあえて外れてみたり、お遊びの部分も創り出してみるのが「3」というアート。
「3」によって《未来》は創られ、「6」によって《未来》はより美しく便利なものへと磨かれていく。
自己愛を守る手段 (2016.3.24 14:59)
「3」的な《自己愛》が自らを守る手段として用いるのが、隣接数である「2」と「4」である。
「2」に進めば自らを全肯定してくれる存在への甘えとしての《依存》につながっていく。
「4」に進めば自らを守る壁や場を構築して周囲からの指摘をシャットアウトする《保身》につながっていく。
ぶっちゃけない愛 (2016.3.24 14:49)
自らの不祥事をぶっちゃける「3(自己愛)」的な行為で「6(他者愛)」は補完できない。
「6」とは周囲を不快にさせないよう慎み深く生きることを表す数であり、もし自らの快楽の為すがままに生きる「3」的な行為をしてしまったのなら、それを一生涯隠し続けるのが「6」的な《礼儀》と言える。
「いいね」の手間 (2016.3.24 14:29)
SNSにおける「いいね」とは、手間暇かけて配線を繋ぐことにより光る電飾LEDのようなもの。
配線を数多く繋ぐ手間と、消費電力というエネルギーを惜しまなければ、その分「いいね」という光の数は増えていく。
あとはこの《作業》を面倒と思うか、やり甲斐に感じるかという違いだけだ。
偶数性の優先順位 (2016.3.24 14:08)
一般的にヒトは若年期に自らの偶数性を「2(恋人や配偶者との関係性)」>「4(自身や居場所の安定)」>「6(社会への自能力の還元)」>「8(社会組織の所属員としての矜持)」の順で優先していく。
しかし中年期以降は「8」>「6」>「4」>「2」という優先順位に変わっていきやすい。
人となり (2016.3.24 13:38)
公人を業績で判断しようにも、その業績自体が高い専門性を帯びたもの、または自らの生活と関わりない分野であれば、一般市民としては判断することが難しくなる。
そのような一般市民にとっては公人の《人となり》こそが最も判断しやすい材料となる。
でもこの《人となり》は平気でウソをつく。
嫉妬エネルギー (2016.3.23 21:56)
「8」という強力なコントロール性は、万事を自身というシステムの中に組み込むことで心の充足を得る分、得られなかった時の不完全燃焼感は容易に「嫉妬」へと化ける。
でもその自らの中の「嫉妬」に真正面から向き合い、その正体を確かめることで、むしろ「嫉妬」は強力な行動エネルギーに変わる。
ヒーロー性 (2016.3.23 19:16)
自らの中の「1(ヒーロー性)」が乏しいからこそ「ヒーロー」という存在を待望するのか。
はたまた自らの中の「1」が現実世界に反映した姿としての「ヒーロー」という存在を待望するのか。
当人の中に「1」があろうが無かろうが、「ヒーロー」という存在は万人の中の「1」を思い出させる。
奇数的開き直り (2016.3.23 16:07)
自らが他者に対して行う偶数的(静的・秩序・カタチ)優しさが相手から評価も感謝もされなかった場合、そのせっかくの偶数性は性質を反転しつつ自らへと逆流し、奇数的(動的・混沌・チカラ)開き直りへと変貌していく。
偶数的優しさが強ければ強いほど、奇数的開き直りも度を超えたものとなる。
「7」の時代 (2016.3.23 15:27)
自サイトに今月分の数秘術ツイートをまとめているけれど、今年に入ってから実に「7」と「2」の思考・ブレインコンビのツイートが多い。
まぁ現在の個人年数「7」のせいにしてもいいのだけれど、これは後世の人が見たらきっと《「7」の時代》みたく名付けてくれることだろう。
ピカソか。
システム化 (2016.3.23 13:41)
「7」という自らの内側にてこねくり回して出来上がる非言語的なアイデアは、そのままでは他者に理解してもらいにくいし、教えることもままならない。
この非言語的なアイデアを丁寧に言語化し、更にシステム化することにより、理解も教育もしやすくするべく、「7」は次の「8」へと向かっていく。
猜疑心を鎮める (2016.3.23 13:22)
子供でも大人でも、相手の「7(猜疑心)」を鎮めるためには、逆数である「2」をきちんと当てがう必要がある。
つまり相手の目をまっすぐ見て、相手の話を丁寧に受け止め、相手の手をしっかりと握り、相手の心とちゃんと向き合うことにより、相手とのラポールを形成していくということだ。
子供という公共財 (2016.3.22 18:17)
そろそろ子供という存在自体を強い親権で守られる《私財》ではなく、必要とあらば即座に親権に制限を加えるべき《公共財》として積極的に保護していかなければいけないのかも。
大実験の危機 (2016.3.22 18:00)
人類を様々に規定してきた《国境》という構造の境目を朧げなものにしていくEUという歴史上の大実験。
でも昨今のシリア難民問題やフランス・ベルギーでのテロ事件によって、せっかく朧げになった《国境》という構造線が再び明確化されていくのではないかという恐れ。
これは大実験の危機だ。
「個」か「衆」か (2016.3.22 17:05)
《個》の悩みを一つ一つ吸い上げて解決しようとする試み。
《個》に直接的に向き合わず、自らのメッセージを《衆》相手に無差別にばら撒き、その《衆》の中にいるそれぞれの《個》が各自めいめいにそれを持ち帰り、自己解決ツールとして勝手に使わせる試み。
僕は後者のやり方が好きだな。
中途半端な「神」 (2016.3.22 16:55)
日本という強い偶数性(静的・秩序・カタチ)こそが《善》とみなされる社会。
こういう偶数性が強ければ強いほど、極めて純粋にまで高められた奇数性(動的・混沌・カタチ)はむしろその存在が《神》として許されるのではなかろうか。
でも中途半端な奇数性ならば、途端に爪弾きにされてしまう。
結婚指輪 (2016.3.22 14:42)
相手との永遠の愛を誓う《結婚指輪》というツールは正に「2」的なものとも言えるし、偶数という《カタチ》そのものとも言える。
そんな結婚指輪を剥き出しのままあげるのもいいが、箱に納めたままそっと差し出し、おもむろに箱を開けてみた方が《約束というカタチの美》はより際立つかもしれない。
批評してこそ (2016.3.22 14:36)
「7」な人が他者との関係性を重んじるという「2」の機能を働かせることは、円満な関係を保つ上ではとても大事なことだけど、それをやり過ぎてしまうとせっかくの「7」が詰まらなくなってしまう。
臆することなくビシバシ批評してこその「7」だし、そんな「7」だからこそ支持するファンもいる。
手垢で汚そう (2016.3.22 13:20)
万の書物を通り過ぎるくらいなら、一の書物を手垢で汚し尽くした方がよほどその人の《チカラ》になるんじゃないかな。
「アクション」を愛せよ (2016.3.22 13:13)
結局のところ《お金》というものは、それ自体が好きな人のところにはなかなか来ず、《お金儲け》という行為自体が好きな人のところにばかり集まりやすい。
自らの《アクション》を愛した末にこそ、それに対する相応の《報い》がもたらされる。
人間らしい言葉 (2016.3.22 13:03)
結局のところ《哲学》とは人間にしかできない行為なわけだから、同じ哲学本を読むのなら、より《人間らしい言葉》で書かれたものを僕は選ぶだろうね。
慣習からズレよう (2016.3.22 12:35)
食堂に入る時間を早めることで、並ばずにゆったりと食べることができる。
早朝から都心へ赴かざるを得ないような仕事を避けることで、満員電車による苦しみからは解放される。
我々が普段当たり前のものと規定してしまっている「慣習」から如何にズレることができるかが幸せのヒントになるかも。
イライラへの対策 (2016.3.22 11:47)
電車遅延の際、その原因等について初めのうちにまぁまぁ詳しく説明してくれれば、その情報を《物語》として脳内でこねくり回すことで自らをもてなすことができるから、そこまでイライラせずに済むかも。
反省と結論 (2016.3.22 11:10)
自らの過去、つまり自身の行為やその結果について時間を遡って考えることが「7」という反省へと繋がっていく。
そしてこの「7」が中途半端なまま、自らの行為やその結果について「これは○○のせいだ」などと早計に関連付ける、つまり「2」という結論を行えば、安心はするが学習にはならない。
ヘラクレス (2016.3.22 11:03)
「ヘラクレスの生き方こそ生きるということであり、意気地のない生き方は、ぐずぐず時間をかけて死ぬことにほかならない」
〜『幸福論』アラン著・村井章子訳より〜
なんという「1」性てんこ盛りの言葉だろうか。
失敗をレンチンしない (2016.3.22 10:42)
「失敗は私たちより短命なのだから、後生大事に暖め返すことはない」
〜『幸福論』アラン著・村井章子訳より〜
誘蛾灯の蛾の如く (2016.3.22 10:37)
「ではいったいなぜ宿命を信じ込むのだろうか。主な理由は二つある。第一は、恐怖のせいで、待ち構えている不運に自ら飛び込んでしまうことだ(中略)これは一種の幻惑と言えるだろう。おかげで、占い師は一財産築いてきたのだ」
〜『幸福論』アラン著・村井章子訳より〜
七日行者 (2016.3.22 10:03)
数秘術的にみて「三日坊主」は「3」だからこその飽きっぽさと捉えるならば、七日を超えて続けることでその深みにハマって抜けられなくなる様を「7」の持つイメージから「七日行者」と名付けたい。
偉大になる「神」 (2016.3.22 0:40)
科学とはてっきり創造主であるところの《神》を小さくするものだとばかり考えてきた。
でも宇宙や極小世界のことが詳しく分かり始めるにつれ、むしろ科学という行いそのものが創造主としての《神》をより偉大なものとして祭り上げていくのではなかろうかと考え始めている。
残酷な子供 (2016.3.21 23:07)
テレビで「子供の持つモメ事を解決する力」をやたらと美化して取り上げているけれど、それが本当ならばイジメは起こらないはずだよなぁ。
子供は大人よりもはるかに残酷やで。
ギフテッド (2016.3.21 22:05)
社会への適応困難ぶりから、その特性をマイナスに捉えた上での「障害」という語ではなく、むしろ他の人が持ち得ない能力や才能を与えられたというプラスに捉えた上での「ギフテッド」という語。
後は親も含む周りの人々がその「ギフト」に気付けるかどうかだ。
予兆 (2016.3.21 18:59)
自らの「2」の機能、つまりどんなささいな予兆も逃さずに受信する「アンテナ能力」を高めれば高めるほど、自動的に逆数「7」の機能も高めてしまう。
それはつまりキャッチした予兆情報の一つ一つを過分にチェックするだけに飽き足らず、どんな予兆が来るのかを無駄に怖れる疑心暗鬼モードだ。
セカイの美 (2016.3.21 18:40)
「3」的に創り出すチカラの美と、「6」的に造り出すカタチの美。
この両者がお互いを尊重し、そして刺激し合うのが「9」という雑多なるセカイの美。
意欲を削がない (2016.3.21 17:55)
「3」的に次々と新しい《命》を生み出すアーティストに対し「こういうものを作りなさい」などと指導するのは、実は行き過ぎた「6」であり、それにより「3」の才能はむしろ萎むかもしれない。
「こういうものもあるよ」などとそっと伝える方が「3」の意欲を削がない良い「6」的サポートかも。
コミュニケーション (2016.3.21 14:44)
「2」とは自らと他者との間に線を引く「コミュニケーション」を表す。
でも線を引くというのは繋がるだけではなく、分け隔てるためにも行われる。
繋がるコミュニケーションも、分け隔てるディスコミュニケーションも、同じ「2(コミュニケーション)」というツールであることに変わりはない。
感情の「声」 (2016.3.21 13:39)
「3」が強まると喜怒哀楽という感情の声はメガホンでがなり立てたように大きくなる。
周囲には喧しいが、自らの感情の異変に気付きやすくなる。
「6」が強まると喜怒哀楽という感情の声は口元を塞いで囁いたかのように小さくなる。
周囲には優しいが、自らの感情の異変に気付きにくくなる。
感情のボリューム (2016.3.21 13:13)
「3」も「6」も共に《感情》を表す数だけど、「3」は喜怒哀楽という感情のボリュームを上げる機能であり、「6」は感情のボリュームを落とす機能を表す。
そのため「3」の機能が強まると喜びも悲しみもより一層ボリューミーなものとなり、「6」の機能が強まるとそれらはよりスリムになる。
心の沈殿物 (2016.3.21 11:38)
自らの内側に泥の如く溜まっていく心の澱(おり)。
「7」マインドが強くなると、この沈殿物をヘタにかき混ぜてしまい、視界が一気に悪くなってしまう。
原因となる泥を取り除こうとすればするほどに、濁りは増してしまう。
かき混ぜないで放っておけば再び沈殿し、元のクリアな視界は蘇る。
儀式 (2016.3.20 15:38)
「儀式」とは偶数という《カタチ》であり、時の流れを区切ることにより「ターニングポイント」として機能する。
そしてそのポイントは、人生を歩むにつれて勢いを弱め始める奇数という《チカラ》が、その勢いを再び取り戻すために用いられる「踏切板」でもある。
偶数で奇数を回復させるのだ。
勉強 (2016.3.20 13:50)
僕はもう何年も「勉強」というものをしていない。
辛うじて読書はしているものの、その中身を覚えようとはしていない。
今の自分に必要なものなら自動的に記憶として残るだろうし、そうでなければさらりと忘れるだろう、くらいのスタンス。
「学び」というものにすら囚われない「9」的学び。
反抗的な態度 (2016.3.20 10:55)
いろいろな人や意見に対して反抗的に突っかかる行為は、過剰に「5」の機能が働いている状態と言える。
そしてこれは自らの「4」に固執する人ほど使いたがる機能とも言える。
自分が得意でいられるようなささやかな自己領域を守るべく、その領域に馴染まないもの全てを異物とみなし攻撃する。
二つの「平和」 (2016.3.20 9:44)
周りの人々や社会そのものに大いに関心を持ち、そしてそれらに「平和」をもたらすべく積極的に奉仕活動を行う「6」的なあり方。
そしてこれと同じくらい大切なのは、周囲や社会への関心を一時的に休んで、自らの中に静かな「平和」を作り味わう「4」的なあり方。
「4」と「6」は同じ量で。
オーバーシミュレート (2016.3.19 22:36)
「7」という機能は己が演算能力の限界まで可能性の枝葉をたどる「オーバーシミュレート」と名付けてもよいと思う。
それに疲れ切ると自動的に「2」という機能が働き、とある一本の道に己が可能性の全てを「マーキング」で固定化する。
ある意味「2」という機能は戦略的な思考停止とも言える。
健気な子供 (2016.3.19 19:10)
「1(自尊心)」を「8(我慢)」で抑える子供。
「3(好奇心)」を「6(行儀)」で隠す子供。
「5(冒険心)」を「4(規則)」で止める子供。
「7(猜疑心)」を「2(信頼)」でごまかす子供。
大人からは健気に見えるけれど、彼らの奇数性はどこで発揮できるのかが心配になるね。
三つの優しさ (2016.3.19 15:30)
希望を増やそうとする「3」的な優しさは「ポジティブ」向きの意識ゆえ。
絶望を減らそうとする「6」的な優しさは「ネガティブ」向きの意識ゆえ。
そして希望も絶望も波の如く訪れることを柔らかく受け入れさせる「9」的な優しさはポジネガ混交である「ナチュラル」向きの意識ゆえ。
「5」という中心 (2016.3.19 15:13)
「1」から「9」を3×3の升目に並べると「5」が真ん中にくる。
「1」と「9」、「2」と「8」、「3」と「7」、「4」と「6」、つまり補数コンビの丁度真ん中に浮かぶ「5」。
それらの数に縛られず、閉じ込められず、むしろ動きながら彼らに刺激を与え続ける「5」は正にヒトの性だ。
偶数で休む (2016.3.19 11:32)
自らが「7」という思考の泥沼で溺れ始めたなら、逆数である「2」を活用して命綱となるような人物や思想を見つけていく。
自らが「5」という激動の只中に飲み込まれたなら、逆数である「4」を思い出して生活の中に不動や静謐の時間を取り戻していく。
奇数に疲れたなら、偶数でじっくり休む。
その責任必要? (2016.3.19 0:28)
未来も目標も特に持たずにのほほんと生きている僕は別に無責任というわけじゃない。
ただ責任をアウトソーシングしているだけだよ。
その責任、ホントに必要?
水曜どうでしょう (2016.3.18 23:49)
たまたまニコ生で「水曜どうでしょうclassic」を観ている。
「9」の大泉洋が「9」なことをやるだけの「9」な番組。
「9」を味わうにはもってこいのコンテンツだよね。
「あっ!なんだ!こんなんでもいいんだ!」的なゆる〜い感じを全肯定できれば、もう正真正銘の「9」だね。
中途半端な太さ (2016.3.18 20:28)
「2」の人が他者との絆を築くために用いる「ロープ」の太さは割と中途半端だったりする。
一人の人と繋がるにはあまりにも太過ぎるため、いざという時に切るのが難しくなる。
かといって「ロープ」を解き、何本もの細切れにして大勢の人と繋がろうとすると、太さが足りずにすぐ切れてしまう。
ラッキーの見極め (2016.3.18 13:30)
果たしてその「ラッキー」が本当の「ラッキー」になるかどうか、慎重に見極めないとなぁ。
情緒不安定 (2016.3.17 21:57)
日本人の情緒不安定さを思うと、きっと「文春スゲー!」から「文春ヒデー!」に変わるのはあっという間なんだろうな。
人為の否定 (2016.3.17 21:01)
ヌメロダイスで「0」が出た時は大体「考えるだけムダムダ!」という感じの言わば「人為の否定」の意味合いだったりするね。
「1」を起こそう (2016.3.17 8:14)
自らを様々なブロックで抑え込み、過度にブレーキを掛け続け、自信なくただひたすらに自制に励む「8」の権化のような人。
しかしそんな人ほど、その内側には様々なブロックを貫き壊し、強引にアクセルを踏み続け、自信に溢れひたすらに衝動のまま猛進する「1」が眠っている。
さぁ、起こそう。
早いも遅いもないさ (2016.3.17 8:01)
「1(行動衝動)」の矢を放つのに遅すぎるということはないし、「9(無為自然)」の境地に達するのに早すぎるということはないよ。
取りこぼされたもの (2016.3.16 23:23)
「7」という非言語的思考をこねくり回した末に、その概念を(本人的に)ピッタリの言葉に当てはめることができれば、それは「2」という言語的思考として秩序の棚にしまわれる。
しかし、その言語化の過程において「取りこぼされたもの」の方にこそ、探し求める本質は眠っているのかもしれない。
消去法的信用 (2016.3.16 21:35)
自らと対象との間を《ロープ》で固く結び付けるかのような「2(信じる)」という行為。
でももしこれがしんどく感じたのなら、とりあえず両者の間に存在する「7(疑い)」を一つずつ丁寧に取り除いていくことにより「2(信じる)」の代わりとしても良いと思う。
消去法的な《信用》だ。
雰囲気 (2016.3.16 20:06)
「雰囲気」とはとても「9」的なもの、つまりは曖昧模糊としたつかみどころのない、けれどもその場全体を緩く包み込むような得体の知れないもの。
それ自体に明確な意志はなく、あるのは何となくぼんやりと見える「メッセージ性」のみ。
そんな「9」は逆数「0(虚無)」と何ら違いは無い。
雰囲気によるテロ (2016.3.16 19:44)
昨今、個人化しているテロを見ていると、彼らをテロに掻き立てるのはイデオロギーではなく割とぼんやりとした「雰囲気」なのではないかと考えてしまう。
イデオロギーはあくまでも後付けで用いられる動機付けというところか。
そしてその「雰囲気」はネット端末の画面からもくもくと湧き上がる。
祈り (2016.3.16 18:23)
「祈り」ってすごく「2」的なイメージの行為だけど、言い換えるならば「双方向性への信頼」って感じかも。
ハズレは占いの母 (2016.3.16 12:47)
既存の占いが当てはまらない人が、新たな占いを創り出していく。
つまり「ハズレは占いの母」なんだ。
よりオーバーに (2016.3.16 12:37)
自らの内側にしまい込まれた過去や記憶を思い出そうとするのはヒトが持つ「7」的な機能だが、それを行う際には補数の「3」も自動的に機能しやすくなる。
つまり過去や記憶の実情よりも《オーバー》なイメージとなって映し出され、そしてより《オーバー》なストーリーとして人々に触れ回っていく。
「礼儀」というカタチ (2016.3.16 12:24)
「6」という数は「礼儀」を表し得る。
感情・マインドに属し、かつ偶数(静的・秩序・カタチ)でもある「6」は自らの感情を波立たせず、そして周囲の感情を波立たせないよう細心の注意を払う。
このような自他の感情を穏やかに調える仕草が洗練された結果、「礼儀」というカタチが成立する。
角から生える脚 (2016.3.16 12:00)
牡羊座かつ「1」の人はもはや角から直接脚が生えているんじゃなかろうか。
不信心 (2016.3.16 11:05)
「絶対に神託を聞くまいとすることにこそ、不信心は最大の力を発揮する」
(『幸福論』アラン著、村井章子訳)
占いを信じないのであれば、それを徹底することだ。僕のように。
しきたり (2016.3.16 10:55)
自らの《しきたり》を守ろうとするのが自己正義としての「4」だし、他者に《しきたり》を守らせようとするのが社会正義としての「6」だね。
おやつ (2016.3.16 10:31)
おやつと数
「1」ハイチュウ・スナック菓子
「2」パピコ・チョコフォンデュ
「3」バブルガム・カップケーキ
「4」堅焼き煎餅・クッキー
「5」パチパチ飴・激辛物
「6」マカロン・和菓子
「7」ねるねるねるね・アイス
「8」ミルフィーユ・濃厚物
「9」綿菓子・生チョコ
空気の中の空気 (2016.3.15 22:04)
我々が「真理」と呼ばれるものを探し求めるのは、空気の中から空気を、海水の中から海水を探し求めるようなものだ。
「ロープ」を切ろう (2016.3.15 8:36)
「7」という泥の中でもがくように悩み苦しむ時、自らの「7」という思考のカオスを責めても意味がない。
肝心なのは自らと思考の対象物とを固く紐付けてしまっていること、つまり「2」という思考のコスモスの方を何とかしなければならない。
観察・受容・思考のロープを物理的に切り離そう。
「愛」になる (2016.3.15 8:27)
意識の中から「愛」という言葉が完全に消え去った時に、その存在自体が「9」という「愛そのもの」となる。
愛するんじゃなくて、愛になるんだ。
現実世界とのリンク (2016.3.15 8:23)
「7」の人の中には現実世界との「リンク」がうまくできず、どうしてもほわわんとしてしまう人もいる。
それは逆数「2」の不足、つまりリンク能力の不足と説明することもできるが、逆に「2」の過剰、つまり一旦リンクしたら外せなくなることへの怖れから無意識的にリンクを避けているともいえる。
らしくなくてもOK (2016.3.14 22:06)
たとえば「4」の子供が「4」らしさを全く見せず、逆数である「5」全開で暴れ、壊し、飛び回ったのなら、それはむしろ喜んだ方がいい。
「5」というツールを駆使することで、「4」というルールや常識などの「壁」の存在をその身を以て確かめているのだから。
「数」らしくなくても大丈夫。
心のバランス取り (2016.3.14 17:13)
外ではバリバリの「6」として、正に模範的に生きている人が、自宅では逆数「3」を全開にしてダラダラと自分を甘やかすケース。
これは逆数というツールを駆使して、自らの心のバランスを取っているのだと考えればいい。
「3」的な自分を否定してしまえば、「6」の濃度が増して中毒を起こす。
反対側への偏り (2016.3.14 12:50)
過激な奇数性(動的・混沌・チカラ)に対するアンチテーゼとしての偶数性(静的・秩序・カタチ)。
過剰な偶数性に対するアンチテーゼとしての奇数性。
これらはあらゆる事象で見かけるが、両者の共存共栄を意図したものでは無い分、より致命的な《反対側への偏り》へと至る可能性が高まる。
二元論的世界 (2016.3.13 14:44)
偶奇両有の「9」とは正にカオスモスな「多様性」そのものだが、奇数(カオス)にも偶数(コスモス)にも偏れない「9」的世界は慣れないと相当に居心地が悪く感じてしまう。
でもそれは、それだけヒトが奇数か偶数かという二元論的世界に馴染み過ぎてしまっているという現実を強く示している。
円形に並べる (2016.3.13 14:37)
「1」とはただの「始まり」であり、「9」とはただの「終わり」であるけれど、「1」から「9」の数を直線的に捉えるとどうしても最初と最後の数だけ特別なものに見えてしまう。
そうならないためにも「1」から「9」を円形に並べることで、「始まり」も「終わり」も特別視することがなくなる。
今更やめられない (2016.3.13 13:21)
僕は毎月、自らのサイトに数秘術ツイート群をアップしているけれど、特にツイートの多い月はこの作業が実に面倒で仕方ないし、そもそもどれだけ読まれているかも定かではない。
とはいえ、こんな作業をもう五年半も続けてしまっている以上、今更やめられない。
《継続》のアイデンティティ化だ。
性格とは「後付け」 (2016.3.13 12:22)
ヒトは自らの《性格》というものを普段からわざわざ《言語化》しているわけではなく、かなりぼんやりとした形でしか捉えていない。
そんな状態で占い本などに書かれた、つまり《言語化》された自らの《性格》と思しき箇所を読むことで、改めてヒトは自らの《性格》を後付けで固定化していく。
レベル上げ (2016.3.13 11:07)
人生もゲームも「レベル上げ」以外の楽しみ方を見つけられるかがカギなんだろうな。
解呪 (2016.3.13 10:28)
人類が「産めよ、増えよ、地に満ちよ」の呪縛から解き放たれるのはいつの日になるんだろうか。
幻痛 (2016.3.12 17:34)
「1」にとって自らとはただの《点》だが、「2」にとって自らとは他者や社会と繋がる《線》自体も含みがち。
そんな《線》が切れれば自らも痛がるし、そんな《線》が絡めば自らも苦しがる。
でも自らから伸びる《線》自体は自らとは全く別のものであり、その痛みはただの「幻痛」に過ぎない。
「8」は「∞」じゃない (2016.3.12 16:20)
二年に一度はつぶやいているが、無限大を表す「∞」はローマ数字で1000を表す「CIƆ(最後の文字は逆さのC)」起源が最も有力な説。
『「∞」は「8」が起源』とか『「8」は「∞」が起源』とかが数秘術本に書かれていることもあるけれど、「8」に強いパワー性をこじつける魂胆が見え見え。
不確定なセカイ (2016.3.12 13:31)
限界を定めることで諸事の安定を図るのが偶数という《カタチ》。
限界を超えることで諸事の変革を図るのが奇数という《チカラ》。
この両者が重なり合うことで偶奇両有という「9」の《セカイ》ができあがっていく。
そんな《セカイ》は「シュレディンガーの猫」の如く不確定性に満ちている。
複雑な模様の織物 (2016.3.12 11:40)
自らの「基本数」に対するコンプレックスから、自らの「逆数」へと走る人がいる。
自らの「逆数」に対する嫌悪感から、自らの「基本数」にこだわり続ける人もいる。
いずれにしても、まずはこの二つの「数」の往復運動により、その人の人生は複雑な模様の織物として織られ始めていく。
二つの自然回帰 (2016.3.12 11:26)
最新の技術やシステム、つまり《未来》というものを認めかつ適応できた上での自然回帰と、《未来》への不適応からそれを認めず、開き直って逃避として自然回帰していくのとでは大きな違いが現れるね。
ジレンマ (2016.3.12 10:35一部改変)
「4」と「5」が合わさって「9」へと至るまでの道程は実に険しいものがある。
しかし両者のシーソーゲームに疲れ切らないと中々「9」の境地には辿り着かないというのも実にジレンマだ。
コンプレックス (2016.3.12 10:32)
自らの「4」に対するコンプレックスが、自らを逆数「5」へと強力に向かわせる。
「こんな狭い世界は嫌だ!」
「普通なんてつまらない!」
「平穏なんて飽き飽きだ!」
そして「5」を十二分に経験した後、自らの「4」の価値に気付き戻ってくることで、自身のコンプレックスは漸く赦される。
「4」の年の見直し (2016.3.12 10:06)
「4」の年は逆数「5」的なイベント(様々な心身の変化)が起こることにより自らの「4」、つまり従来の習慣・住居・身体についての見直しを迫られることも多い。
答えは既にある (2016.3.12 0:50)
「7」という数の持つ大切なテーマは「答えは自らの内側に既に眠っている」ということ。
ただし「7」は一桁最大のカオスなので、答えを引っ張り上げるのは容易ではない。
そこで必要となるのが、逆数である「2」の機能。
自らの内側の一点で像を結び、それを強く信じ抜いてあげればいい。
「4」という蝶番 (2016.3.12 0:36)
「1」「4」「7」は「自のライン」を構成するが、真ん中の偶数(静的・秩序・カタチ)が両脇の奇数(動的・混沌・チカラ)のバランスを保ち安定させる「蝶番」の役目を果たす。
自らの「4(場への帰属)」がしっかりしていれば、「1(外世界への侵攻)」も「7(内世界への逃避)」も軽く済む。
マナーの中の世界 (2016.3.11 23:58)
帰りのバスの中で僕の隣に座ったダウン症の男性が何度か放屁をしていた。
21番(→3)染色体が3本あることと多幸感という特徴から、僕はダウン症の人を「3」の権化と捉えている。
普段我々がいかに「6」というマナーの中で窮屈に過ごしているか、ということを「3」に教えられた気がする。
意識過剰 (2016.3.11 18:53)
自意識過剰な「3」。
美意識過剰な「6」。
無意識過剰な「9」。
ボランティアしない (2016.3.11 12:50)
震災に対して真正面から向かい合うことで、自らの《平穏》が変質してしまうのではないかという奥底の怖れ。
そして震災を本当の意味で《自分ごと》として受け容れられていない心理。
自らの《狭い壁の中》で自己を保つのにいっぱいいっぱいな「4」の僕は震災ボランティアを一切やっていない。
中立の精神 (2016.3.11 12:40)
「2」「5」「8」は「他」のラインを構成するが、真ん中の「5」だけが奇数(動的・混沌・チカラ)となる。
「2」という信頼と従順、「8」という支配と操縦、この両者による偶数(静的・秩序・カタチ)的なしがらみから逃れ、他者との適度な距離感を動きながら保つのが「5」という中立の精神。
「怒り」の原因と目的 (2016.3.11 12:13)
原因論で考えるならば「怒り」とは自己の中に発生するコントロール不能な「1」的衝動によるものということになる。
しかしアドラー的な目的論で考えるならば「怒り」とは相手を支配するために用いられる「8」的コントロールツールということになる。
「怒り」とは「1」であり「8」である。
五度目の3/11 (2016.3.11 8:37)
今年の3/11は数秘術で見ると「5(変化)」の日。
あれから5年、変わったものは何だろう。
そして変わらなかったもの、あえて変えなかったものは何だろう。
説明するだけ (2016.3.10 23:16)
その人が「4」だから「頑固」と決めつけるんじゃ、ただのレッテル貼りになっちゃう。
あくまでもその人の「頑固」を「4」というイメージで説明していくだけ。
ここんとこ間違えないでね。
「破壊」を恐れない (2016.3.10 23:00)
たとえば自らの中にある「5」を振り絞って、「4」という閉鎖的かつ旧守的な場所から出て行くという行為。
これは元の「4」から脱け出して新しい場所を見つけることだけではなく、元の「4」に新しく生まれ変わるきっかけを与えることでもある。
だからこそ「5(破壊)」を怖れてはならない。
忠誠 (2016.3.10 12:38)
たとえどんなに支配や制御を拒む「1」であっても、そんな「1」を心地良くスムーズに御してくれる「8」に出会えたのなら、「1」は喜んで忠誠を誓うだろうね。
面倒臭さかも (2016.3.10 12:33)
自らの持つマイナスな「4」マインド、つまり「面倒臭いから動きたくないだけ」という気持ちを素直に認めることを避け、「これは慎重さなんだ」とか「僕は義理堅い人間なんだ」などというプラスな「4」マインドへと変えていく心的作業。
その慎重さや義理堅さは、実はただの面倒臭さかもしれない。
四次元ポケット (2016.3.10 8:23他)
全ての数を内包する「9」はドラえもんの「四次元ポケット」みたいなもの。
でもドラえもんがテンパると「四次元ポケット」から意中の道具を出せず、デタラメな道具を出してしまう。
肝心な時に使うべき「数」を出せず、違う「数」が出ることにより余計な苦労を背負いこむのが「9」の性。
ドラえもんの「四次元ポケット」に喩えた「9」だけど、全てに絶望した際には逆数「0」という強大なニヒリズムが顔を出し、目の前の全てのものを消そうとすることもある。
それはまるで大嫌いなネズミに遭遇してとち狂ったあげく「地球破壊爆弾」を出して地球もろとも消し去ろうとするようなもの。
「四次元ポケット」の如く全ての数を持つ「9」が意中の「数」を出すためには、自らの「これがやりたいんだ!」という欲求のチカラをはっきりとさせる必要がある。
そんな「1」という補数こそが「9」に強大な推進力をもたらす。
勢いよく進み始めてから「8」というハンドリングをすればいい。
レーダー (2016.3.9 11:41)
それぞれが駆使する「レーダー」。
「1」と「8」は直観(ソウル)。
「2」と「7」は思考(ブレイン)。
「3」と「6」は感情(マインド)。
「4」と「5」は感覚(ボディ)。
「9」は全てがレーダーであると同時に、レーダーを一切気にせず無為自然に生きるということでもある。
オカルトポケット (2016.3.9 11:11)
なんか「オカルト」という言葉って検証不能な事柄を乱暴にしまい込む「ポケット」みたいな概念にも感じるな。
静・動・波の美 (2016.3.9 9:40)
数秘術において「6」は「美」を表す数とされるが、逆数である「3」も十分に「美」を表し得る数となる。
偶数の「6」が秩序・カタチを重んじる「静の美」とするならば、奇数の「3」は混沌・チカラを重んじる「動の美」となる。
そんな動と静とが往復することで「9」という「波の美」となる。
テーマを越える (2016.3.8 22:02)
生年月日や氏名から与えられる特定の「数」とは、即ちカタチとしての「数」であり、これがあることで自らのテーマの固定化が容易となる。
でもそんなカタチにだけ囚われず、自らの意思で自由に選び取ったチカラとしての「数」を自在に駆使することで、固定化されたテーマすらも乗り越えていける。
出産というイベント (2016.3.8 16:15)
既に取捨自由な「文化的イベント」となりつつある先進諸国における「出産」という行為について、旧来的かつ取捨不自由な「生物的イベント」としての価値観を当てはめようとしてくる人々の存在。
これはある意味、伝統観や宗教観、それらに基づく道徳観などを凶器として用いる「いじめ」と大差無い。
やる気と暇 (2016.3.8 15:18)
「やる気」がある時に限って「暇」がなく、「暇」がある時に限って「やる気」がない。
「暇」とは「やる気」というガス状のものが薄らいだ時にようやく現れ始めるものなんじゃなかろうか。
落とし所 (2016.3.8 14:43)
落とし所という着地点、すなわち「4」的な目的地を用意も想定もしないで行う「5(刷新・改革運動)」はやがて崩壊の憂き目に遭う。
偶数という《カタチ》も用意せぬままに奇数という《チカラ》を発動しても、その《チカラ》はその真の性質を発揮する前に徒らに雲散霧消してしまうからだ。
一致不一致 (2016.3.8 14:35)
奇数かと思えば偶数を行い、偶数かと思えば奇数に向かう。
言葉と行動とがぴったり一致することもあれば、両者がてんでバラバラになることもある。
そういう言行一致と言行不一致とが一人の中に混在するのが「9」というパーソナリティであり、それこそが多種多様な社会で「生きる」ということ。
原因を探さない (2016.3.8 12:47)
「9」という「あきらめ」は別にネガティヴな諦念というわけではなく、「原因を探し求めることをしない」というむしろポジティブ寄りの姿勢なんだ。
因果を固定化せず、曖昧で宙ぶらりんな状態にあえて放ったらかすことにより、あらゆるものから自己を解放しようとする試みこそが「9」という行い。
孤り(ひとり) (2016.3.8 11:53)
「1」とはただの「個」であり、そしてただ「孤り(ひとり)」であることを表す数。
しかしこの「孤り」を「孤高」としてプラスに捉えるのか、はたまた「孤独」としてマイナスに捉えるのかは、正に心の持ち方次第だ。
そしてそれは他者との繋がりや社会の中の自分をどう捉えるかで大きく変わる。
人生のレシピ (2016.3.8 11:20)
「1」という圧倒的な自我のチカラを封じ込めるためには、「8」という究極的な抑我のカタチを用意しなければならない。
「1」が勝ればチカラによる暴威で自らはバラバラとなり、「8」が勝ればカタチによる暴圧で自らは押し潰される。
このチカラとカタチのバランス取りが人生のレシピとなる。
「6」のささやき (2016.3.8 10:41)
「人と関わるといろいろ疲れるし、自分のスペースで寛いでいるのが一番だよなぁ」などと開き直って引きこもる「4」マインドな僕に、補数の「6」がささやいてくる。
「でもさぁ、自分のできることを人に施して、それに対して正当な報酬を得られる喜びの方がはるかに勝るんじゃないかなぁ」とね。
「数秘術を学ぶ」とは (2016.3.7 16:31)
初めに「数秘術」から「術」が外れて「数秘」となる。
次に「数秘」から「秘」が取れて「数」となる。
そして「数」から「数」が去って「」となる。
最後には「」すら消えて無に帰する。
これが「数秘術」を学ぶという過程の全て。
舫(もやい)綱 (2016.3.7 16:11)
自らが自らの知性を信じること、つまり両者を繋ぎ止める「2」という舫(もやい)綱が無ければ、「7(検証)」という機能はたちまちにして自らを難破させる嵐となり得る。
「おまけ」に戻ろう (2016.3.7 14:39)
集客ないし顧客定着のため、一度ベーシックな役務の中に取り込んでしまった「サービス」を後から分離するのは難しい。
だからこそ「サービス」とはあくまでも「おまけ」に過ぎないというところまで立ち戻らなければいけない気がする。
際限ない競争が生むのは「サービスの癌化」かもしれない。
サービスの基本化 (2016.3.7 13:47)
元々は気配りとか相手の便宜を図るための《追加要素》であったところの「サービス」が、日本という特殊な土壌で揉まれるうちにいつのまにか《基本要素》に変化してしまったことが様々な悲劇を生んでいる原因かもしれない。
見えない・見える (2016.3.7 13:40)
チカラであるところの奇数とは「見えないもの」である。
カタチであるところの偶数とは「見えるもの」である。
そんな奇数と偶数とが混在した「9」とは「見えないもの」と「見えるもの」との混合、つまり「ある」となる。
そして奇数も偶数も無在の「0」はどちらも無いため「ない」となる。
日本人の「大丈夫」 (2016.3.7 13:05)
偶数マインドの強い人(我々が普段イメージする《日本人》と言い換えてもいい)が用いる「大丈夫」という言葉の嵩増し感。
2〜30%程度の「大丈夫」感であっても一度「大丈夫」と伝えてしまえば、その「大丈夫」はほぼ100%の「大丈夫」感として伝わってしまうという実に面倒な言葉。
「理不尽」について (2016.3.6 19:53他)
突発的かつ個人的な奇数性(動的・混沌・チカラ)のちょっかいにより、積み重ねられた偶数性(静的・秩序・カタチ)の中に「理不尽」の種が宿る。
そんな奇数性が消え去ったあとも偶数性の中の「理不尽」は無くならず、むしろシステムや人員などの手によってその「理不尽」は再生産されていく。
システムや集団にとってはただのイレギュラーでしかない「理不尽」であっても、内部でそれが消えずに再生産され続けることにより、むしろ「理不尽」はレギュラー化されていく。
やがては「理不尽」そのものがシステムや集団を維持するための楔(くさび)として、より積極的に扱われ始める。
暴力的に集める関心 (2016.3.6 18:21)
その人自身のリサーチ能力が乏しかったり、そもそもリサーチする気が無かったりする場合、自身の奇数性を《暴力的》に発揮して相手や周囲の関心を手っ取り早く集めたりする。
「1(カリスマ)」とか「3(ユーモア)」とか「5(プロテスト〈反抗〉)」とか「7(レビュー〈批評〉)」とかを用いる。
理不尽保存の法則 (2016.3.6 14:19)
若い頃より受け続けてきた社会の理不尽を、老いたのちにそれを社会へと還元していく行為に対して「理不尽保存の法則」と名付けたい。
ただ「4」であれ (2016.3.6 12:58)
競争に翻弄されず、成長に固執しない。
ただ「4」でいる。
ただ「4」である。
落ち着いて、寛いで、固めて、守って、繰り返して、囲って、収めて、蓄えて、ゆっくり歩んで、様式に従って、地道に続けて、足元を見て、自らの《感覚》を信じて、自分を保って、安心できる《場》を作っていこう。
脱トートロジー (2016.3.5 22:55)
僕が数秘術や占いを考える上で大切にしているのは「《不思議》を《不思議》で解説しない」ということ。
「3」を育もう (2016.3.5 12:42)
「6」はホスピタリティの数であり、そして慈しみや育みの数でもある。
でも何を対象に「6」を発揮すればよいのかわからない時は、逆数の「3」がヒントとなる。
つまり自分自身や他者の自己愛や自己顕示欲、承認欲求や表現欲などを適度に満たし、輝かせ、より良質なものへと成長させることだ。
ダウングレード (2016.3.5 12:34)
その「マスターナンバー」、きちんと使いこなせているかい?
いまいち扱い方がよく分からなかったりするんじゃないかな。
だったらいっそのこと、その持て余している「マスターナンバー」を「ルートナンバー(一桁の数)」へとダウングレードしたっていいんだよ。
生きやすい方で生きよう。
生きるための理由 (2016.3.5 12:00)
生きるための理由を「他」に求め、それと強固につながる(または断固として拒む)ことにより「生」を実感するのが「2」マインド。
生きるための理由を「自」だけで完結させ、自らが生きるという行為それ自体が「生」そのものであり、そこには根拠も理由も存在する余地すら無いのが「1」マインド。
生まれ出る奇数 (2016.3.4 23:19)
奇数(動的・混沌・チカラ)は「生まれ出る」ことを表し得るけれど、それぞれに違いがある。
「1」は無から突如として発生する感じ。
「3」は出産のように母体から自然に出てくる感じ。
「5」は母体を顧みず破壊的・爆発的に飛び出す感じ。
「7」は外ではなく内側へとにじみ出る感じ。
生きる・生かされる (2016.3.4 17:51)
執念的な「1」の「生きる」と、諦念的な「9」の「生かされている」。
この両者を行ったり来たりしながらみんな生きていく。
点と球の繰り返し (2016.3.4 16:47)
「自己」だけがギュッと詰まった「1」という小さな「点」が様々な「数」を経験して、最終的に「9」という大きな「球」へと成長していく物語。
その「9」という大きな「球」は次なる広い世界に移動した途端、「1」という小さな「点」となり新たなる旅を始める。
これの繰り返しが人生。
優しくなれるさ (2016.3.4 11:26)
ヒトの「優しさ」とは特有の性質ではなく、あくまでも社会で生きる上で用いる「ツール」であり、それを駆使した結果としての「態度」だと思う。
だから「自分は優しくないのかな…」などと悩む必要はない。
「優しさ」というツールを使うべき時が来たならば、ごく自然にそれを使うだろうから。
旅路か旅先か (2016.3.4 11:07)
「行動のための目標」が奇数マインドであり、その行動を為すためには目標を変えることを厭わない。
「目標のための行動」が偶数マインドであり、その目標を成すためには行動を変えることを厭わない。
旅路という途中経過を楽しむ奇数と、旅先に着くという目標達成感を味わう偶数の違い。
デコボコを均す (2016.3.4 0:26)
現実のスガタを理想のカタチに近づけることは、両者の差異というデコボコを「均していく」ということ。
理想や社会に合致させるべく、個人というデコボコをそれらのカタチにうまく合うよう均していく。
この「均していく」という行為が正に「6」で表される「教育」という象意につながっていく。
優しさは「ツール」 (2016.3.3 22:56)
数秘術本において「2」は「受容力があって優しい」などという説明が多い。
しかし「2」は別に初めから優しいわけではなく、世界を鋭く観察して自らの存在を安定化させるための「リンク」先を見つけようとしているだけ。
優しさや受容力はそのための「ツール」であり、本質というわけではない。
「1」とは生きること (2016.3.3 21:38)
「8(コントロール)」を駆使して自らの中でうごめく「1(衝動・欲求)」を制御する際、ついチカラを入れ過ぎて「1」を容赦無く圧し潰してしまうと、今度はピクリとも動けなくなってしまう。
「1」の暴走はもちろん防ぐべきものだけど、「1」が無いと「生きる」が「ただ生きてる」だけになる。
居場所 (2016.3.3 21:24)
その内側で自由に遊ぶことができる「3」と、その外側へいつでも好きな時に飛び出していける「5」を共に満たすことができれば、両者の真ん中に本当の意味でくつろげる「4(居場所)」が出現する。
「日本死ね」について (2016.3.3 18:17)
「日本死ね」という言葉のすごいところは、従来なら母国である「日本の死」はそれに属する「私の死」とイコールであったのが、ようやくにしてイコールでは無くなり始めているところ。
死にそうな国から離れて他国で生きたとしても、それは「私」という個人が当然のように行使できる「生の権利」だ。
帰属への恐怖 (2016.3.3 8:37)
「1」には「帰属する」ことに対する根源的恐怖や強い忌避感が眠っている。
「1」という絶対的な「個」において全ての存在は自らに「帰属させる」ものであり、決して自らが他の何かに「帰属する」ということではない。
「帰属する」ことにより、自らの「個」が損なわれることへの強い恐怖だ。
帰属意識の呪い (2016.3.3 8:29)
「8」の人は集団や社会という「システム」に対する帰属意識が強く、それらの中における自らの居場所や存在価値、あるいは影響力というものに強い拘りを持つ傾向がある。
これは例え「1」の人であっても、自らの「1」を素直に出すことを怖がり逆数「8」で圧殺したならばやはり上記のようになる。
個とシステム2 (2016.3.3 8:20)
「1」にとって「システム」とは、全てにおいて自らという「個」のために使われるべきもの。
「8」にとって「個」とは、全てにおいて自らが属する「システム」のために使われるべきもの。
「1」が育ってこそヒトは個としての尊厳を取り戻し、「8」が育ってこそヒトは個を超えた力を発揮する。
個とシステム1 (2016.3.3 8:11)
「1」はあくまでも自らという「個」が全ての基準であり、そこから自らが属するに値する「システム」を創り出す。
「8」はあくまでも自らが属する「システム」が全ての基準であり、そこから自らと思しき「個」を取り出す。
スペース (2016.3.2 22:57)
相手そのものを観察してしまう「2」と、自らと相手との間のスペースを観察する「5」との違い。
「2」は安定性確保のためにスペースを埋め、「5」は柔軟性確保のためにスペースを空ける。
防衛のための攻撃 (2016.3.2 22:43)
周囲のあらゆるものに対してツッコミまくる「5」的な反発。
他者からの指摘に何倍もの言葉を返す「5」的な反駁。
自らの小さなスペースを汲々と守る「4」の中には、他者や周囲を過度に警戒し、ある種の「仮想敵国」として扱い、更には逆数「5」を用いて「防衛のための攻撃」を行う人もいる。
健康のための「3」 (2016.3.2 18:59)
自己保全のために「現状の健康を維持する」のが「4」マインド、自己美化のために「より一層の健康美を目指す」のが「6」マインド。
そんな健康のためには以下の「3」がとても大事。
内部の毒素を出すデトックス。
身体の不調をごまかさない。
わざとらしいほどに大きく動く。
よく笑う。
繋がる・確かめる (2016.3.2 16:09)
「1」的な存在(神や偉大な存在)と凡弱な自らとを「2」という線でつなぐことで安心安寧を得るのが「帰依」であり、この線を掴み従うという行為そのものが「宗教」なんだね。
そんな線に繋がれた両端、更には線の存在そのものについて自らの知をもって確かめていくのが「7」という「哲学」だ。
怒りあっての赦し (2016.3.2 15:29)
「マインド・感情」に属する「3」の怒りとは異なり、「ソウル・直観」に属する「1」のそれは正に自らと一体化したものとなり「怒りの権化」という存在そのものとなる。
そんな「1」という「怒り」がきちんと存在するからこそ、補数である「9」の「赦し」が「赦し」としての価値を得る。
奇数という自由 (2016.3.2 14:38)
奇数(動的・混沌・チカラ)という「自由」。
世界における己が実在も自由も絶対かつ当然な「1」の自由。
眼前に広がる世界の中で動ける喜びを味わう「3」の自由。
世界の外へと翔び立つことで新たな風を浴びる「5」の自由。
自らの内に世界を見出し、その中を旅して巡る「7」の自由。
代償は成人後に (2016.3.2 12:37)
その家庭が極めて歪な偶数性(抑圧・秩序志向)で満ちていたならば、そこで育つ子供がそれに逆らうかのように奇数性(反発・混沌志向)を自らの中で育むのはごく自然なこと。
でもその歪な偶数性に馴染むべく、自らの偶数性を強化して自身の奇数性を圧殺したなら、成人後に代償を払うことになる。
悩めなくなる (2016.3.2 12:18)
「死んだらもう悩まなくなる」ではない。
「死んだらもう悩めなくなる」だ。
自らの正しさを疑う (2016.3.2 12:13)
健全な「7」マインドだからこそできる大切なことは「自らの正しさを疑える」ということ。
教育や経験等を重ねることで強くなる固定観念、つまり事象と事象の間に張られた「2(関連付け)」と、それにより生まれる自らにとっての「正しさ」の定義。
これすらも疑える柔軟性が健全な「7」の証。
フロイトを翻訳 (2016.3.1 8:49)
フロイトの定義を数秘術的に翻訳するならば、自我(エゴ)は偶奇両有の「9」であり、エス(イド)は奇数性(本能性)、そして超自我(スーパー・エゴ)は偶数性(規範性)って感じかな。
家族という単位 (2016.3.1 8:26)
「家族」という集団単位。
外部に対しては極めて排他的であり、内部においては極めて過干渉・過保護であるところがまさに「6」的な存在。
他を排することで集団の純度を高め、自らが属するメンバーに対しては過剰なまでに手を掛けるというその行為自体を「美しい家族愛」として規定していく。
唯一者 (2016.3.1 8:16)
自己自身、つまり自我を思想の根底に置き、自我を「唯一者」としたマックス・シュティルナー。
彼の「私の事柄を、無の上に、私はすえた」という言葉。
「1(自己)」は有限であるが故に生きていく瞬間瞬間で自らを定立し、新たに自我を創造し、そして自らが創り上げた自己をも克ち超えていく。