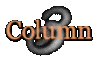
数秘術関連等ツイート(2015年9月分)
偶数でチェックしよう (2015.9.30 23:38)
そのアクション(1)は誰を意識(2)してのものなのか。
その表現や創作(3)はどの場所(4)で行うべきなのか。
その改革(5)にきちんとした理念(6)はあるのか。
その思考(7)にシステマティックなプロセス(8)はあるのか。
奇数の正当性を偶数でチェックしよう。
「壁」の意味を知る (2015.9.30 15:32)
自らの自由を阻んでいた「壁」が、実際には自らの自由を守る「壁」だったということに気づくまでが「4」のテーマだったりする。
創るスピリチュアル (2015.9.30 15:25)
「スピリチュアル」なものがあるから「スピリチュアル」を求めるんじゃなくて、「スピリチュアル」なものが欲しいから「スピリチュアル」を自ら創り上げるヒトというのは一定数いると思う。
問題なのは前者と後者を同一視してしまうこと。
空のハンドル (2015.9.30 14:34)
自他を含めあらゆるものをコントロールしようと欲する「8」マインド。
これはそれぞれが持つ「ハンドル」を全て独占しようとする行為。
しかしこれらの「ハンドル」は本当にそれぞれに直結しているのだろうか。
実は何にも繋がっていない「空のハンドル」を持っているだけかもしれないよ。
それ「断捨離」? (2015.9.30 14:11)
その「断捨離」にちゃんと「自我」は含まれているかい?
アール・ブリュット (2015.9.29 20:19一部抜粋)
「アール・ブリュット」とは「加工されていない、生(き)のままの芸術」という意味のフランス語とのこと。
正にありのままの創造性を意味する「3」な言葉だね。
「きっかけ」を無くそう (2015.9.29 18:20)
ヒトの中の「ケモノ(暴力性)」をいくら法や倫理などの「鎖」で雁字搦めに抑え込んでも「ケモノ」が完全にいなくなるわけではない。
肝心なのは「ケモノ」が出てくる「きっかけ」を無くしていくこと。
満員電車の混雑が「きっかけ」で暴力が発生したならば、その混雑の方を何とかすべきなんだ。
ヒトは「暴力的」 (2015.9.29 18:10)
虐待や暴力のニュースに接した人々は「こんなことは一部の人間がやることであり、常識では考えられない!」などと反応する。
でもヒトは本質的に「暴力的」であり、それを法や倫理など多々の「鎖」によって暴れ出さないように抑え込んでいるだけ。
「きっかけ」次第でヒトに「ケモノ」は蘇る。
「我」は「他」 (2015.9.29 17:59)
我々は自らという「我」と環境という「他」を対比で捉えがちだけど、「我」は「他」を構成する一要因であり、そして「他」も「我」を構成する一要因であり、本来なら同じもの。
この「我」と「他」を分けることで、色々と分かったふりをする。
面倒臭い「吉凶」 (2015.9.29 13:39)
「吉」を招き「凶」を避けようとするのはヒトの性(さが)であり、それはつまり万物を「吉凶」の二つに分離すること。
でも「禍福は糾(あざな)える縄の如し」という言葉を考えるならば、上記の行為は正に糾える縄(撚り合せた縄)をいちいち解いていくようなもの。
なんて面倒臭い行為だろう。
かわいそうな日 (2015.9.29 13:27)
「吉日」ばかり愛でるなよ。
「フツーの日」がかわいそうだろ。
わた師 (2015.9.29 12:33)
「数秘術師」である前に、まずは「わた師」でありたい。
「現象」は「現象」 (2015.9.28 16:52)
そろそろヒトは「現象」に「意味」を与えることから足を洗ってもいいんじゃなかろうか。
たとえば「この地震は私にとって悪魔でしかない」とか「この地震によって私は愛の大切さを知った」とか。
「地震」はどこまでいっても「地震」でしかなく、「怨敵」でも無ければ「教師」でもないんだ。
高過ぎる目標 (2015.9.28 16:14)
高過ぎる目標を与えることは、一つの「暴力」になるね。
その目標と現実との乖離が、当人に強い「自己否定感」を植え付けるという意味で。
消費される「美」 (2015.9.28 16:04)
とある人物を一方的に「美のシンボル」として祭り上げ、更にはそのシンボルに対して「美のシンボルは常に『スタンドアロン』であらねばならない」などという呪いをかける。
他の「美のシンボル」と繋がったならば、「美のシンボルペア」として一層祭り上げていく。
こうして「美」は消費される。
「分類」をやめる (2015.9.28 15:22)
ヒトを「分類」していったとしてもヒトのことを理解できるわけではない。
結局それはただの「分かったふり」でしかない。
だからこそ僕はそろそろヒトを「分類」することから足を洗いたいと思う。
「数」をそんなことのためにのみ使うのは、あまりにももったいなさ過ぎるからだ。
「時間」こそ苦 (2015.9.28 15:05)
「1」という「一者」に無く、「2」という「二者」に存在するのは「時間」という概念。
「二者」の間に起こる運動により初めて「時間」という概念が生まれる。
つまり「時間」とは「一者」であることを捨てることであり、そこから「分離」の苦しみが生まれる。
「時間」こそが苦なんだ。
「暴力」について (2015.9.28 14:40)
「行為はイデオロギーではない。もしイデオロギーから生まれる行為であれば、それは暴力に到る」(『クリシュナムルティの日記』p101)
この「暴力」は暴力を制御すること自体も別の形の「暴力」と捉えている点が面白い。
「1(衝動)」も「8(自制)」も行き過ぎればどちらも「暴力」だ。
超シンプルな風水 (2015.9.28 14:20)
様々な本を読んで風水にこだわるよりも「部屋に新鮮な風を入れる」というシンプルさを僕は好む。
愛されるに値する国 (2015.9.28 13:18)
やたらと「愛国心」という言葉を使いたがる人がいる。
でもその愛される対象としての「国」とは自然発生的な概念ではなく、その構成員たる我々が我々の意思で作り上げていくもの、という意識が欠けている人もいたりする。
我々に必要なのは「愛されるに値する国を作り上げる」意識だと思う。
「善性」なき「家族」 (2015.9.28 13:05)
構成員それぞれの「個」がきちんと尊重されている場合のみ、「家族」という概念に強い「善性」が与えられる。
もしそれぞれの「個」が「家族」の名の元に踏みにじられるならば、その「家族」から「善性」は奪われていく。
尊ばれるべきは前者の「家族」であり、後者の「家族」ではない。
「善」と「善性」 (2015.9.28 12:45)
「善」は独りでかつ自発的に行うことで、その「善性」を発揮していく。
しかしその「善」を集団かつ強制的に行わせようとすると、その「善」からは「善性」が失われていく。
「善」を無理強いさせず群れさせず、単体の「善」が柔らかく周りに伝播していくことでその「善」の「善性」は光り輝く。
人道的 (2015.9.28 12:36)
「人道的」であることはとても大事なことだけど、この「人道的」という概念には社会において恐ろしいほどの強制力がある。
でも「人道的」であることを無理矢理に強制されることは、果たして「人道的」なことなのだろうか。
追い求めれば求めるほどに「人道的」は「人道的」では無くなっていく。
十字架の愛 (2015.9.28 11:42)
為そうとする「愛」が「3(エロス・純愛)」ならば難しくはない。自己完結型の「愛」だからだ。
しかし他者が絡む「6(フィリア・友愛)」になると、様々な縛りが現れる。
ましてや「9(アガペー・無償の愛)」にもなると、常人が為すのはとても困難となる。それは「十字架の愛」だからだ。
スーパーなムーン (2015.9.28 1:28)
「スーパームーン」という言葉を見て思うのは、月に月蝕以外の「特別感」を与えたいと思う気持ちにより生まれた言葉なのかな、ということ。
つまり「スーパームーン」という現象に対して「スーパームーン」と名付けたわけではなく、「スーパーなムーン」を月蝕以外に作り上げたということ。
この人こそ… (2015.9.28 0:20)
「4」のクリシュナムルティ(1895年5月12日生)をマスターナンバーにしたがる気持ちはよくわかる。
でも「各桁バラして加算」しても「年・月・日それぞれの数字根を加算」しても「年・月・日をそのまま加算後単数変換」してもマスターナンバーは出てこない。
少しズルすれば出るけどね。
ヒロイックな占い師 (2015.9.27 22:20)
占い師によるアドバイスは占術や技術などではなく「この俺の生き様を目に焼き付けろ!それが俺からのアドバイスだ!」的なヒロイックさ(すごく「1」的な)で攻めてもいいと思う。
「制御」は「被制御」 (2015.9.27 14:41一部改変)
何かを制御(8)しようとすれば、それは必ず制御されるもの(2)を生み出す。
つまり「制御しなければ」という意識が制御者(8)と被制御者(2)という「分離」を生む。
この分離を無くし「制御とは被制御でもある」ということに気付けば、両者が合わさって10→「1(強い運動性)」が生まれる。
正反対の「知」 (2015.9.27 14:24)
対象をつぶさに観察し、それに名前をつけ、他の対象と関連付けをし、更に体系化してアーカイブにまとめていくのが「2」という「知の秩序化」。
そしてそのアーカイブを一つ一つ検証し、その正しさを問い続けていくのが「7」という「知の混沌化」。
共に「知」ではあるが中身は正反対の性質だ。
何者だい? (2015.9.27 14:12)
「自分とはいったい何者なのか?」ということを問い続けさせられ、自ら定義した「何者か」になるための努力を余儀なくされる社会とはどれだけ不自由な空間なんだろう。
「自らが何者なのか」などということをいちいち問わずとも「あなた」はそこにいつでもいるし、決して「あなた」を辞められない。
やがては消えていく (2015.9.27 14:06)
四つの機能の全てを溶かして「自然」との一体感を味わうのが「9」であることだが、この一体感すらもやがては消えていくものであり、それは「0」になるということ。
もし「9」であり続けることに拘ったり、それに聖性を与えてしまったならば、折角混ざり合ったものが「分離」していってしまう。
「9」で得る一体感 (2015.9.27 13:46)
大地にどっしりと座り、ただじっとその場にいるという行為。
それを続けていくと、思考が無くなり、感情も薄れ、感覚も鈍り、やがては直観の動きも消えていく。
全ての機能が曖昧の中に溶け始めた時、そこで初めて自らを包む「自然」との一体感を味わえる。
これが「9」になるということ。
罪滅ぼし (2015.9.26 17:40一部改変)
大口を開けて笑い楽しむ「3」的なものを堪能した後、それをただの「3」で終わらせずに逆数「6(いかに役に立った)」や補数「7(いかに深かったか)」を付加させる人がいる。
それはただ「3」を消費しただけの自分に対してある種の「軽さ」や「幼さ」を感じてしまったが故の「罪滅ぼし」だ。
ゆとりのある行為 (2015.9.26 16:49)
目の前の「生」を生き抜くことに使うリソースを減らすことで、ヒトは初めて「考える」ことができるようになる。
100%リソースを使っている状態で悩んだり迷ったりすることは「考える」こととは程遠く、極めて受動的な「呪い」となる。
「考える」とはゆとりのある能動的行為なんだ。
「平均台」から降りよう (2015.9.26 16:19)
その人自身が定義した何かしらの「成功」へとひたすらに向かい、その道筋から落ちないようにまっすぐ歩んでいくという一種の「苦行」。
その平均台のような道から降りてみることで、生き生きとした動きを取り戻した自らに気づけるかもしれないよ。
落ちて始まる人生もある。
引き寄せない (2015.9.26 16:12)
まずは「引き寄せない」ことから始めてみてはどうだろうか。
「2」は「はかる」 (2015.9.26 15:29)
「はかる」という言葉は正に「2」的な言葉。
時間の長さを「計る」。
物体の長さを「測る」。
物体の重さを「量る」。
計画の道程を「図る」。
他者の意見を「諮る」。
他者の誤動を「謀る」。
これらは全て自他の間に引かれる「2(ライン)」に通じていく。
自発的な「勉強」 (2015.9.26 15:12)
自らの「創造性」が自らの持つ「ツール」の能力を大きく超えたものとなった時、ヒトは初めて自ら「勉強」する。
僕の「排泄物」 (2015.9.26 15:07)
僕のツイートはとどのつまり大便とか小便の類いに他ならない。
僕個人の生理的欲求に基づき、ツイッターという海に垂れ流しているだけ。
でもそんな排泄物であっても、いくらかの滋養は残っているのではないかと思いたい。
僕という消化器官を通して漉し出された何かしらの変容物だ。
「善悪」じゃなく「広狭」 (2015.9.26 14:59)
異なる二つの主張を「善」と「悪」に分けようとするから話がややこしくなる。
そうではなくて、単に「狭いところを見つめている」者と「広いところを見渡している」者との違いというように分けてみたら良いのではないだろうか。
その両者の中には、単純な善悪の概念は入り込めなくなる。
「ツール」の役目 (2015.9.26 14:47)
「ツール」というものは何かを作り上げる際に用いるものであり、もし目指す何かが出来上がれば、もうその「ツール」を持つ必要はなくなる。
僕にとっての「数秘術」とは、正にそういう「ツール」なんだ。
曲解から始まる「信仰」 (2015.9.26 14:41)
自らが強く感じていることと、ほとんど同じことを他者から聞いたとすれば、当然ながらその他者を信じようとするだろう。
問題なのはそれがたまたま二人の考えが合致したというただの事実を「絶対的な正しさ故」であると大いに曲解してしまうという点だ。
この曲解から始まる「信仰」もある。
共に「4」である縁 (2015.9.26 14:35)
組織の指導者であることを強いられた結果、指導者を辞めて「真理は組織化し得ない」などと組織という概念自体を否定したクリシュナムルティ。
占い師であることを母から強いられた結果、占い嫌いな占い師(いずれ辞める予定)となった僕。
共に「4」であるという縁をこじつけておくとしよう。
「比較」なんかしない (2015.9.26 14:10)
わざわざ他の何かと「照らし合わせる」ことにより、自らが信じる「正義」や「神聖」を確かめたり強化したりする人は多い。
けれどもそんな「比較」の中に「正義」や「神聖」などは存在しない。
いちいち他の何かと比べずとも、それ単体で光り輝くのが「正義」や「神聖」と呼ばれる概念なんだ。
この一冊 (2015.9.26 14:02)
「この一冊に出会えたのなら、自らが所有している凡百の本など未練なく捨ててもいい」…そう思えるような本に出会えることは、とてつもない喜びだ。
僕が持っている何十冊の数秘術本をブックオフに下取りさせたくなるくらいの喜びが今ここにある。
持っているのは『クリシュナムルティの日記』。
「美」の果て (2015.9.26 13:51)
ヒトが美しいものを「美しい」と感じて褒め称える機能にこそ、恐ろしいまでの「残酷さ」が潜んでいる。
なぜならその機能によってヒトは「美しくないもの」を無視したり、嘲笑したり、放逐したり、矯正したり、挙げ句の果てには駆除したりもするからだ。
その一連の究極が「ジェノサイド」。
ナイフの二つの機能 (2015.9.26 13:38)
「ナイフ」の機能を「数」で喩えてみる。
その鋭鋒で対象に刺し込んでいく「7」。
その鋭刃で対象を真っ二つに斬る「2」。
「7」が過ぎればその身は抜けなくなり、「2」が過ぎればその身は欠け落ちていく。
両輪の「知」を廻す (2015.9.26 13:19)
「2」で「知の秩序」を調え、「7」で「知の混沌」を楽しむ。
この両輪が勢い良く廻ることで「9(森羅万象)」の姿が朧げに浮かび上がってくるように感じる。
この「9」は秩序と混沌を抱き込んだ存在であり、両者の「知」が混じり合うことで我々は「無知の知」を思い知らされることになる。
「カテゴライズ」の先へ (2015.9.26 13:09)
いくつかの事柄を整理するために「分ける」、そして他者から見てわかるように「名付ける」、これが「2」という「カテゴライズ」。
でもこれは「7」という「思考」や「洞察」のために行う「知の整理」であり、もし「2」で止まってしまえばただの思い込みによる「盲信」と大差が無くなってしまう。
「幅」の是非 (2015.9.25 18:23)
「宇宙における天体運動は極めてスケールの大きなものだから、多少の幅は容認すべきだ」という考え方に以前から違和感を抱いていたりする。
そのことが解釈の幅を広げていることは理解しているけれど。
偶像崇拝というコピペ (2015.9.25 12:36)
ムハンマドが最初の啓示を受けたマッカ(メッカ)のヒラー山登山口には、登山する観光客に対しての「この山は本来は神聖視されるべきものではない」という注意書きがサウジアラビア政府によって掲げられているらしい。
「偶像崇拝」という「神聖さをコピペする」ことの是非について考えさせられる。
「反応」の毒 (2015.9.25 9:12)
「2」というロープで人々や社会と繋がるということは「2」の「反応」という行為・被行為で自らを縛り上げるということ。
その「反応」から離れるためには「7」という混沌の沼に自らを逃がすしかない。
これは当然ながら「孤独」を生むが、「反応」という毒に侵されるよりかはマシかもしれない。
平和圧 (2015.9.24 21:45一部改変)
偶数性の強い人にとっては「自らの定めた多々のタブーに触れないこと」こそが平和。
奇数的な好奇心の持ち主を冷ややかな目で見る「平和圧」だ。
「タブー」を設ける「6」 (2015.9.24 21:39)
静的・秩序・カタチを表す偶数、とりわけ「6」という数は「タブー」を多く設ける数として捉えても良いと思う。
多々の「タブー」で囲い込んだ内側に「倫理の美」を作り出していく。
そんな「6」の生んだ「タブー」に遊びながら挑むのが「3」であり、その必要性を掘り下げ検証するのが「7」。
弱まっていく「7」 (2015.9.24 21:23)
「信頼」→「信奉」→「信仰」というように「2」が強くなればなるほど、「7」という「検証性」は弱まっていく。
このことが果たして良いことなのかどうかについては何とも言えない。
「視線」が作る「美」 (2015.9.24 20:58)
他者からの「視線」にさらされることで自らの「外」に磨きをかける「6」。
自らの「視線」を自身で強く意識することで自らの「内」に磨きをかける「7」。
「6」という「外の美」で社会に美しき秩序が生まれ、「7」という「内の美」で精神に美しき混沌が戯れる。
「6」の中の哀しみ (2015.9.23 14:39)
僕は「3(感情の混沌)」を楽観や喜びの数、「6(感情の秩序)」を悲観や哀しみの数として扱っている。
混沌のままに感情を激しく波立たせている時よりも、その感情が少しずつ穏やかになっていく、または静めてなだらかにしていこうとする秩序化過程の中にこそ本当の「哀しみ」が現れる。
開けるか、閉じるか (2015.9.23 14:10)
「目を開けるための哲学」と「目を閉じるための哲学」。
目を開けることで「余計な闇」を払う哲学。
目を閉じることで「余分な光」を遮る哲学。
目を開けることで、閉じていた時よりもはっきり見える「闇」がある。
目を閉じることで、開いていた時よりもはっきり見える「光」がある。
ストーリーは淡々と (2015.9.23 13:54)
この世界というストーリーには「プロローグ」も「エピローグ」も「ヤマ」も「オチ」もありゃしないよ。
ただただ淡々と流れていくだけ。
ラブソング (2015.9.23 13:29)
たった今、外で一匹のセミが鳴き始めた。
でも彼の渾身の恋歌を聴いてくれるセミは果たしてまだいるのだろうか。
効いている感 (2015.9.23 12:58)
多くの人々がつい求めてしまうのは「効いている」ことよりも「効いている感」なんじゃなかろうか。
そう、育毛スプレーのシュワシュワ感みたいに。
「思考停止」という思考 (2015.9.23 11:21)
「2」という「思考の停止」とは無思考状態というわけではなくて、「思考を止めるための思考」であると言える。
「2」という「ライン」で自他を繋ぐのも、自他を分けるのも、それ以上徒らに思考しないようにするための思考行為。
でもそんな「2」から「7(思考の運動)」が芽生えていく。
「信仰」を哲学すること (2015.9.23 10:11)
「信仰」というものは極めて「2」的なものであり、これはつまり「思考停止という秩序」であるとも言える。
しかし人々の中には信仰を哲学せんと「7」的な「思考運動という混沌」を模索する人も時折現れる。
でもこの「7」は素直な「2」でいられなくなった己への失望の現れかもしれないのだ。
「9」は特別じゃない (2015.9.23 9:59)
僕は奇数(1・3・5・7)と偶数(2・4・6・8)両方のイメージを併せ持った数として「9」を捉えているけれど、だからといって別に「9」のことをマスターナンバーのように特別扱いはしない。
「9」という数はただそういう属性であるだけであり、そこに特別性などありはしない。
「自由」で「不安定」 (2015.9.23 9:43)
奇数とは「自由」かつ「不安定」そのもの。
「1」は自由かつ不安定な直観。
「3」は自由かつ不安定な感情。
「5」は自由かつ不安定な感覚。
「7」は自由かつ不安定な思考。
この奇数性を「自由」と捉えるのは奇数マインドの強い人であり、「不安定」と捉えるのは偶数マインドの強い人。
放屁 (2015.9.22 23:23)
「お腹に溜めているのは良くないから出しちゃおう!」といって勢いよく放屁するのが「3」だとすれば、「人前で放屁とか恥ずかし過ぎてありえない!」とたしなめるのが「6」だね。
そして「屁?そういえばそんなのも出したっけ」などと放屁という行為自体も意識しなくなるのが「9」って感じ。
「食べていく」の軽重 (2015.9.22 23:12)
何かで「食べていく」という表現の中には「それで頑張って生活していく」という重さと「まぁ食えれば何だっていいさ」という軽さが同居しているね。
もし自らの中で仕事が重くなってしまったのなら、一度ふわりと軽くしてみようか。
そう、「食べていければいい」のだから。
「惑う」暇の無い社会 (2015.9.22 22:19)
「四十にして惑わず」などと言われるけれど、現代社会だとむしろ「惑うことすら許されない」感が強い気がする。
様々な「リアル」を急き立てられ、自己啓発本に自己啓発を強いられ、「大人」であることを頑張らせられる社会。
とてもじゃないが「惑っている」暇なんか与えてもらえない。
お客様を信じるな (2015.9.22 20:03)
昔、ヤ○ーのコールセンター(テクニカル部門)で働いていた時に「お客様の言葉ではなく、モデムを信じろ」などと教えられたけれど、これは占いでもそうかもね。
「お客様の言葉ではなく、ホロスコープやタロットを信じろ」的な。
一周忌 (2015.9.22 17:05)
そういえばもうすぐ「3」の友人の一周忌だが、自らが「3」的なことをする際には常にそいつが横にいるような感じがするから、特に寂しさなどは感じない。
墓に行かずとも、位牌に手を合わさずとも、自らが「そいつらしさ」と共にあれば、いつだって対話はできる。
あいつは「3」になったんだ。
無くなっていく「時間」 (2015.9.22 16:52)
ここ数年、僕の中では「時間」というものが無くなりつつある。
「過去」については多少懐かしんだりすることはあるが、「現在」についてはかなりぼんやりとなるようになったし、「未来」にいたっては全くもって作ろうとする気が無くなっている。
「時間」が生み出す苦悩から解放されつつある。
無幸の幸 (2015.9.22 16:23)
ヒトは「幸」を手に入れることに躍起になるけれど、この「幸」の裏には「苦」がもれなくくっ付いてくる。
だから「苦」から離れたければ、「幸」への執着をまず止める必要がある。
それが「幸」なのか「苦」なのかよくわからなくなる「無幸の幸」であり、「9」によって得られる「0」なんだ。
死にゆく人 (2015.9.22 16:10)
死にゆく人は決して「死」を手に取ることはできない。
「死」を手に取るのはいつだって、死にゆく人の周りにいる人々。
そしてその「死」に哀しさや悔しさなどの感情的概念をデコレーションしていき、なんとかして「死」を自らの中で消化しようと励んでいく。
死にゆく人にはない不自由さだ。
消えていく「死」 (2015.9.22 16:01)
「死」というものをただの「0(無)」と見て避けるのか、はたまた遍く宇宙に満ちている「9(全)」と見て優しく受け容れるのか。
むしろ「9」的なものとして受け容れることで、「死」は「0」的に消えていくのではなかろうか。
余りにも当たり前過ぎる存在を意識しなくなるのと同じように。
「9(全愛)」に気づく (2015.9.22 15:40)
「愛は、時間のなかにも分析のなかにもない。後悔したり、互いに責め合うような泥試合のなかにもない。金銭や地位への欲望がなくなり、自分をずるく偽らないようになったとき、愛はそこに在る(『クリシュナムルティの日記』より)」
自ら「0」になれば、そこが「9(全愛)」であることに気づく。
「血」のせいじゃない (2015.9.22 12:31)
自殺者の子が自殺したり、大量殺人鬼の弟が大量殺人を犯したりする悲劇。
我々はこのようなことを「血(遺伝子)」のせいにしがち。
でもこれらは別に「血(遺伝子)」のせいなどではなく、彼らが自ら生み出してしまった「血(遺伝子)の呪縛」という概念に囚われてしまった結果生まれた悲劇。
こんなこともあるさ (2015.9.22 11:18)
たとえどんなことが我が身に降りかかったとしても「まぁこんなこともあるよね」などといなしてしまえるようになるのが理想。
いるいる (2015.9.21 12:44)
自分の奇数性(動的・混沌・チカラ)には寛容であっても、他人の奇数性には不寛容なヒトって一定数いるね。
三つの「調和」 (2015.9.21 1:44他)
「神」または「モナド(単子)」であり、古代には通常の「数」扱いされなかった「1」を除けば、最初の奇数は「3」となり、最初の偶数「2」と掛け合わさることで「6」という「調和(ハルモニア)」が生まれる。
でも「6」自体が偶数であるため、ある意味では「静的・秩序的調和」とも言える。
偶数の「6」が「静的・コスモス的調和」であるならば、対する奇数の「3」は「動的・カオス的調和」であり、そしてその両者が混ざり合った「9」は「動静混交・カオスモス的調和」となり、それはつまり「森羅万象」そのものとなる。
奇数と偶数の同時性 (2015.9.20 22:47)
奇数性と偶数性は一つの事柄において同時に存在し得る。
たとえばオカルトを疑ってばかり(7)の人が持つ、オカルトへの強い関心(2)。
たとえば恋人と常に繋がっていたい(2)気持ちの裏にある、相手の浮気に対する警戒心(7)。
奇数が偶数を、偶数が奇数を互いに刺激し合っていく。
「過必要」の害 (2015.9.20 18:14)
もちろん社会において「偶数性(静的・秩序・カタチ)」は必要なものだが、問題なのはそれを過剰に必要であると思い込んでしまうこと。つまりは「過必要」の害。
自他の安心安定を強く求め過ぎてしまえば、「偶数性」は依存(2)・頑迷(4)・拘泥(6)・執着(8)などに化けていくことになる。
辞められない理由 (2015.9.20 16:54)
幼少の頃より受け続けてきた「偶数性教育」により、よく従い(2)、よく守り(4)、よく働き(6)、よく忍ぶ(8)ことがいかに善であるかを叩き込まれた人が、大人になってから「ブラック企業」をなかなか辞められなくなるのも無理はない。
主張や逃亡、疑念などの「奇数性」は悪者扱いされる。
「居場所」が欲しいだけ (2015.9.20 14:37)
その人の「5」的な反抗や自由奔放に見える行為は、ただ「4」的な「自分の居場所」が欲しかったことが理由かもしれないよ。
まずは周りから (2015.9.20 14:27)
「所変われば人変わる」というのは別のその人自身が変わるわけではなく、先にその人を取り巻く周囲の人々が変わるということ。
周囲からの視線が変わればその人自身の周囲に対する「反応」も大きく変わっていく。
たとえ鏡が同じ物を映したとしても、その場の明暗によって映り方が変わるように。
バチガイ (2015.9.20 14:17)
あなたが「キチガイ(気違い)」と断じる存在は、実はただの「バチガイ(場違い)」なだけかもしれないよ。
恐れて望む (2015.9.20 14:14)
奇数(動的・混沌・チカラ)は偶数(静的・秩序・カタチ)に絡め取られて囚われることを恐れ、そして望んでいく。
偶数は奇数に自らを侵食され、やがては蹂躙されていくことを恐れ、そして望んでいく。
偶奇両有の「9」は恐れに満ちた世界を逃げ回り、やがて諦め、そして全ての恐れと溶け合う。
「異常」とは「距離」 (2015.9.20 14:02)
顕著な偶数性(静的・秩序)に満ちた移動中の電車内にて、顕著な奇数性(動的・混沌)に溢れた人が奇声をあげてドアを何度も蹴りながら車両内を移動していった。
その対象を「異常」であると定義するのは、その対象の持つ極性とその対象が存在する空間や集団が持つ極性との「距離」に他ならない。
蜘蛛の巣 (2015.9.20 13:34)
八本足の蜘蛛が用意周到に巣を張り巡らせて獲物を待ち受けるのは正に「8」的なイメージになるけれど、巣という住処と罠を作っているが故に巣から離れられなくなるリスクを負っている。
そんな「8」が自ら作った巣から離れられた瞬間に、巣に頼らぬ「1」としての強さとダイナミックな野生が蘇る。
組体操という「病」 (2015.9.19 23:32)
『学校はなぜ「巨大組体操」をやめられないのか』なる記事を読んだが、この「巨大組体操」というリスクの集合体こそ正に「偶数病」の病巣という感じ。
集団内において絆(2)・継続(4)・倫理(6)・自制(8)を声高に訴え、それらを強いるようになったなら、それはもう「偶数病」の罹り始め。
自虐と自尊 (2015.9.19 18:09)
自己否定の強さ、つまり「8(自虐)」が強いということは、その分だけ「1(自尊)」も強いということ。
「1(自尊)」という暴れ馬を「8(自虐)」という手綱で無理矢理抑え込んでいる。
つまり自らの「1(自尊)」の奔走を恐れるが故の過剰なブレーキング。
「美」の味方 (2015.9.19 15:41)
世界に「美」をもたらそうと躍起になる「6」がもし燃え尽きたなら、隣にいる「孤高」の名が付いた「7(孤独)」と「刷新」の名が付いた「5(破壊)」とが共に手招きしてくることだろう。
それらの誘いに乗ることなく、真の「7(孤高)」と「5(刷新)」に勇気をもらい「6(美)」を果たそう。
人々に与えるもの (2015.9.19 15:20)
「3」という「アート」が人々に与えるのは「感動」。
「6」という「デザイン」が人々に与えるのは「恍惚」。
「9」という「ナチュラル」が人々に与えるのは「安心」。
ケンカをさせる金持ち (2015.9.19 14:52)
「金持ちケンカせず」という言葉があるけれど、実際には「金持ちは自らケンカはせずに、他者にケンカをさせる」という表現の方が正しいと思う。
自らケンカしても損害を被るだけだけど、むしろ他者をけしかけてケンカさせ、その他者に便宜を図った方が稼げるわけだから。
だから金持ちになれる。
「根」と「葉」 (2015.9.19 14:46)
「4」はスタティック(静的)な感覚であり、いわば「感覚の根」。
何事にも動じずどっしり構え、その場から様々な養分を吸収し蓄える。
「5」はダイナミック(動的)な感覚であり、いわば「感覚の葉」。
陽光を浴び、風雨に揺れながら大木のバランスを取り、そして不要物を排出していく。
負のプレゼント (2015.9.19 14:15)
相手への慮りがズレた「親切」の最大の問題点は、いかにズレたものであったとしてもその「親切」を断った側にある種の「申し訳無さ」を生じさせることであり、それはある意味で「負のプレゼント」とも言える。
「親切」する側が負うべき責任を「親切」される側にあげてしまう恐ろしいプレゼント。
人生後半部の「数」 (2015.9.19 13:46)
「4」の抱く逆数「5」的な「異端願望」も、やがて冷めれば「4」的な「正統願望」へと揺り戻されていく。
「5」の抱く逆数「4」的な「正統願望」も、やがて厭きれば「5」的な「異端願望」へと舞い飛んでいく。
自らの「数」のテーマを痛いほど思い知らされるのは、むしろ人生の後半部だ。
本当の意味の「信仰」 (2015.9.19 13:30)
「7(疑念)」から逃げ回ることに疲れ切ったが故に走る「2(信仰)」は本当の意味の信仰ではなく、ただその対象を「信じ込もう」としているだけ。
本当の意味での「信仰」とは対象のありのままを観て、そのありのままを受け入れ信じる「2」から「9(我が消えて対象に溶ける)」への移行のこと。
幸せになりたいだけ? (2015.9.19 13:23)
僕の逆数秘術は別にヒトを幸せにするわけじゃなくて、ヒトに「幸せとは何か?」を考えさせるきっかけを与えることが可能かもしれないというだけのツールに過ぎない。
ただ幸せになりたいだけのヒトは他の数秘術師の元を訪れた方がいいと思うよ。
シャッフルマシン (2015.9.19 12:54)
つくづく政治問題とは「友人シャッフルマシン」だな。
誰の味方? (2015.9.19 0:04)
僕は与党の味方でも野党の味方でもなく、「プロテスト(抗議)」の権利や「プロテスタント(抗議者)」の味方だよ。
難解かつシンプル (2015.9.18 23:11)
奇数(1・3・5・7)側から見ても偶数(2・4・6・8)側から見ても、偶奇両有の「9」はとてもわかりにくい存在。
しかしそれは奇数偶数という「極性」の中で生きているからこその複雑さであり、ヒトも自然も宇宙も全ては初めから「9」であると思っている人からすれば「9」こそがシンプル。
鏡に映る「歪み」 (2015.9.18 22:11)
歪んだ「6」を鏡に映した時、そこに映るのは歪んだ「6」ではなくて鏡像としての歪んだ「3」が映る。
「これはあなたのためなのよ!」などと押し付ける一方的な親切や教導はまさしく歪んだ「6」であり、そしてそれはただ自己愛を満たすために行う歪んだ「3」の現れでもある。
「結論」と「思考」 (2015.9.18 21:16)
「2」の思考はいわば「結論のための思考」。
結論というゴールが既に創り上げられており、そこに向かう思考のラインをただひたすらにたどっていく。
「7」の思考はいわば「思考のための思考」。
たとえ結論に至ったとしても、そこからまた思考のラインを引き、どこまでも思考を重ねていく。
「教え」から「教理」へ (2015.9.18 20:47)
はじめは「9(アガペー)」として存在した「教え」から「3(エロス)」が綺麗に取り除かれることで、殊更に「6(フィリア)」であることを求める「教理」が誕生する。
もちろん「6」に生きることは人生を美しくしていくけれど、たまには取り除いた「3」の喜びを思い出してみてほしい。
阿片 (2015.9.18 16:00)
「1(我)」による苦しみから逃れる道として補数の「9(無我・忘我)」があるが、これは喩えるなら「阿片」のようなもの。
適量適質であれば鎮痛効果を存分に発揮するが、多量かつ劣悪のものを使用すればたちまち心身を害する毒となる。
この「9」の適切な使用法を教えてくれるのが「仏教」。
人を殺める言葉 (2015.9.18 15:45)
Q:歴史上最も多くの人を殺めた言葉は何ですか?
A:「愛国心」
メタ数秘術 (2015.9.18 14:15)
これから必要となってくるのは「メタ数秘術」だと思う。
数秘術ワールドの中で数秘術ごっこに興じるうちに、何か大切なものを失くしてしまいそうな気がするんだ。
偽善活動 (2015.9.18 13:13)
見返りを求めることを否定せず、「これは偽善活動さ」などと言ってのける「6」の慈善活動ほど清々しいものはない。
利己心とフィリア (2015.9.18 13:07一部追記)
「フィリア(友愛)」であるところの「6」とは則ちこういうことなんだよね。
でもこのことに気づけた「6」の「フィリア」はとても力強くなる。
…『利己心がわずかでも含まれていない隣人愛というものはあるだろうか』(「超訳ヴィトゲンシュタインの言葉」より)
「願い」が作る数秘術 (2015.9.18 12:15他)
とある名称や単語の頭文字を取り出して作られる略称のことを「頭字語」というけれど、ゲマトリアの際には正式名称と略称のどちらを採用するかで迷うことになる。
たとえば「WHO」だと19→「1」だが、「World
Health Organization」だと122→「5」となる。
しかし「WHO」の役割から考えると数秘術師としては「6」にこじつけたいところ。
ならば「WHO」は母音数が「6」となるし、「World
Health Organization」であれば子音数が「6」となるので、お望みの「6」が現れる。
数秘術師の「願い」が数秘術を作る。
「神」の居場所 (2015.9.16 11:59)
「2」は「神」とつながり、「7」は「神」を自らの中に見出し、「9」は「神」に包まれ自らを溶かしきる。
「2」は「外在化」の数であり、「神」は自らの「外」にいる。
「7」は「内在化」の数であり、「神」は自らの「内」にいる。
「9」には「外」も「内」もなく、全てが「神」となる。
「意味」を伝える手段 (2015.9.16 11:46)
「言葉」に「意味」を与えているんじゃなくて、「意味」に「言葉」を与えているだけだよね。
だから何かしらの「意味」を伝える手段は別に「言葉」に限らず、音楽でも絵画でも造形でも舞踊でも何でもいいんだ。
「あさが来た」 (2015.9.16 11:04)
新しい朝ドラ「あさが来た」の主人公のモデルは「5」の広岡浅子。
大商家に生まれるも因習により読書から遠ざけられ、大坂の豪商に嫁ぐも商いを手代に任せきる風習に疑問を感じ、独自に簿記等を学び始める。
「4」の古き壁の中にて自らの「5」を育てた浅子は実業家・教育者として名を馳せる。
「定義」しているだけ (2015.9.16 0:01)
その占いはもしかしたらあなたがあなた自身のことを理解できたつもりにしているだけで、実はただあなた自身をとあるカタチに「定義」しているだけかもしれないよ。
ヒトという不定形な存在を「カタチ」に押し込めるのは相当に無理のある行為だから。
いろんな「定義」 (2015.9.15 23:01)
占星術や数秘術で自らを天や時に「定義」してもらってもいいし、エニアグラム的なもので自らを自らの意思で「定義」してもいいし、自らを「定義」することから離れるのもいいね。
「恋愛」と「結婚」 (2015.9.15 21:13)
結局のところ「恋愛」はとことん奇数的(動的・混沌・チカラ)なものであり、「結婚」はとことん偶数的(静的・秩序・カタチ)なもの。
でも中には奇数的な「結婚」をすることで偶数的な退屈さから逃れる人もいるし、偶数的な「恋愛」をすることで奇数的な危なっかしさを避ける人もいる。
いろんな「癒し」 (2015.9.15 21:01)
奇数性(動的・混沌・チカラ)が強過ぎる社会であれば偶数性(静的・秩序・カタチ)が「癒し」となるし、逆もまた然り。
でもその両極の往復運動に疲れた人は、偶奇が混ざり合い曖昧模糊となった「9」に「癒し」を求めていく。
そして絶望的に疲れ切った人は「0」へと走り、偶奇を消し去る。
「奇数」の反乱 (2015.9.15 12:49)
政治権力や国家権力という強大な「偶数(秩序)」に対する、一般市民たちの「奇数(混沌)」による自由希求の戦いが革命だったりデモだったりする。
「偶数」の正しさを押し付けられるほどに、ヒトの持つ「奇数」精神は一層燃え上がっていく。
「奇数」による反乱の原因は「偶数」が生み出す。
「7」という「異常」 (2015.9.14 16:28)
「異常」とは字の如く「常とは異なる」状態を表す言葉だけれど、その「常」自体に疑いを持ち続けるのが「7」であり、だからこそ余計に「異常」扱いされてしまう。
しかしこの「7」の検証機能が働かなければ、この世界に満ちあふれる「常」が実は「異常」であるということが皆目わからなくなる。
奇数病の例 (2015.9.14 16:19)
「社会から俺が放逐されるんじゃない!俺が社会を放逐するんだ!!!」などと叫ぶ重症の奇数病患者の例。
「おかす」ということ (2015.9.14 14:28)
奇数性(混沌)による偶数性(秩序)への抵抗を表す言葉として「おかす」がある。
これは「冒す」にも「侵す」にも「犯す」にも変換可能だが、奇数性がどれに向かっていくかは正直紙一重の差であり、立場によってもその意味合いは大きく変わってくる。
リツイートとふぁぼ (2015.9.14 13:14)
「リツイート」って「こんな面白いのがあったから見てみて!」という意味ではすごく「3」的だし、「ふぁぼ」って「これはためになるから大事に取っておかなきゃ」という意味ではすごく「4」的だね。
転色 (2015.9.13 21:46)
早まって転職する前にとりあえず「転色」でもしてみたら。
「自分の色(キャラ設定)」を変えてみるの。
「自分」は「自分」のまま演じ続けなければいけない、なんて脚本ルールは無いからね。
五感による検証 (2015.9.13 17:04)
五感をフル活用して「検証」を試みるのが「7」だよなぁ。
ほのかな香り (2015.9.13 16:32)
香り付き柔軟剤とかもそうだけど、この「香りだらけの社会」の中で上書きされて消えていく「鼻腔に遠慮しながら入ってくるほのかな香り」も多いんだろうな。
どっちを書いても (2015.9.13 14:46)
「4」の人の性格について書いたとしても「5」的に生きてる「4」の人が違和感を持つし、そっちを意識して書くと今度は「4」的に生きてる「4」の人が違和感を持つ。
なので今度は「4」と「5」が交互に現れる旨を書くと「そんな書き方なら当たるに決まってる!」などと言われる不条理。
二つの「伝統」 (2015.9.13 13:03)
「4」という現在進行形の「伝統」は、古くから続いているものが現在においてもなお脈々と受け継がれ、その継続自体が存在意義であるもの。
「7」という過去完了形の「伝統」は、既に失われつつある智慧の集合体であり、発掘者の好奇心を刺激してやまないもの。
責任としての「笑顔」 (2015.9.12 16:15)
「3」的な笑顔を「ありのままの笑顔」とするならば、「6」的な笑顔は「責任としての笑顔」だろう。
相手を心配させまいと作り出す優しさと慈愛に満ちた笑顔。
どんなに不安な状況下でも、「6」スマイルを見せることで皆にも笑顔が伝わっていき、不安を乗り越える大きな力となっていく。
「気づき」の矛盾 (2015.9.12 15:39)
「二項対立の罠を超えて皆が一つになれるように『気づき』を深めていこう!」などというスローガンを掲げる集団が、結局のところ『気づけた人』と『未だ気づけない人』という二項対立を抱え込まざるを得ない矛盾。
「気づいても、気づかなくても、どちらでもいいさ」という「9」的集団なら欲しい。
「ワンネス」への旅 (2015.9.12 15:17)
「9(全)」という「ワンネス」から、「0(無)」という「ワンネス」を経て、「1(単)」という「ワンネス」へと向かっていく旅。
「手相」を超えて (2015.9.12 14:41)
「乙武洋匡さんを納得や共感させる手相占い師」ならば、僕はその占い師をとても好きになると思う。
「4」は「5」の「母」 (2015.9.12 11:23)
たとえそれがどれだけ「5(異端)」であったとしても、その存在が長続きすればやがて「4(伝統)」へと変質していく。
「5」が「5」であり続けるということは、「4」への変質に対する激しい抵抗運動なんだ。
つまり「4」という存在こそが「5」という存在を輝かせる「母」となる。
孔孟と老荘 (2015.9.12 11:18)
孔子や孟子が説いたのは「6」の道であり、老子や荘子が歩んだのは「9」の道。
混沌に満ちあふれた社会に偶数性(秩序)を必死に取り戻そうとする「6」の道。
混沌も秩序もごちゃ混ぜであるのが「自然」という世界そのものであり、その「自然」のままにただただ生きようとする「9」の道。
「喜ばせる」ということ (2015.9.12 11:14)
自らの中の「6」、つまり「わたし以外の誰かを喜ばせる」ために日々頑張っている人は、自らの中の「3」、つまり「わたしがわたし自身を喜ばせる」ことがきちんとできているのかどうかを時々思い返してほしいと思う。
「3」が輝けば、「6」はもっと輝ける。
冒涜者 (2015.9.11 0:00)
奇数人よ、健全な冒涜者たれ。
生きてるだけで丸儲け (2015.9.10 16:50)
「生きてるだけで丸儲け」というのは確かにそうなんだけど、実際ヒトって自らの命の価値を自身の存在以外のモノ(マイホームなど)に委ねてしまうヒトも多いから難しい。
「不倫」で育つ (2015.9.10 14:09)
「不倫」が占い師を育てている。
能力的にも経済的にも。
二つの「信じる」 (2015.9.9 16:52)
自分が「観た」もの(実際に目で見たかどうかにかかわらず)を「2」的にそのまま信じる人。
「観た」ものを鵜呑みにせず、きちんと「7」的な検証を挟んでから信じる人。
この両者の「信じる」は言葉は同じであっても意味合いは全く異なるし、そもそも互いに理解し合うのがとても難しい。
「0」あってこそ完成 (2015.9.9 16:32)
自らを「9(全)」の如く、とにかく様々なもので満たそうと躍起になってはいないだろうか。
でも本当の意味での「9」には「0(無)」という空っぽな部分も含まれているし、「0」が含まれてこそ「9」は完成に至る。
だから「0」を恐れたり、排除しようとしたりする必要はないんだ。
条件反射的に (2015.9.9 13:22)
マイナンバーが配られた時に条件反射的に単数変換をしない人は数秘術師じゃない。
貪欲 (2015.9.8 22:14)
「7」は自分の「内側」に貪欲であり、「3」は自分の「外側」に貪欲なんだ。
その「自由」はない (2015.9.8 20:03)
医者には病気になる「自由」は無いし、ダイエットインストラクターにはぶくぶくと太る「自由」は無いし、占い師には不幸になる「自由」は無いよね。
非生産活動 (2015.9.8 18:05)
この三日間くらい「妖怪ウォッチ」プレイに夢中になっていたら、数秘術ツイートが激減したではないか。すばらしい。
「生産」も楽しいけど「非生産」も楽しいねぇ。
「空っぽ」という可能性 (2015.9.8 14:27)
「空っぽ」とは「空(0)」で「満ちている(9)」というわけだから、とてつもないポテンシャルだよね。
「偏り」も「偶然」のうち (2015.9.7 8:37)
たとえサイコロの目で「1」が10回連続で出たとしても、そういった事態を含めての「偶然」なんだよね。
「偶然」とはランダム的に見えるとは限らない。
でもヒトはこの一種の「偏り」を何か意味のある「必然」と捉えてしまいやすい。
数秘術を嗜んでいる人は特に。
「1」の不完全燃焼 (2015.9.5 23:57)
「1」マインドの強い人がうまく前進できなくなった際に、補数である「9」マインドを演じることで「成功とか失敗とかそんなんどっちでもいいんだよ!」などと自らをごまかしたりする。
これにより一時的には自らを慰めることはできるだろうが、自らの「1」の不完全燃焼による中毒は避けられない。
こじつけ過ぎに注意 (2015.9.5 22:48)
「星」や「数」に自らの人生をこじつけすぎるあまり、何でもないようなことまでも不運や不遇として捉えてしまわないようにね。
どっちにしようかな (2015.9.5 17:59)
「2」:「どっちにしようかな…(どっちかに決めなきゃ)」
「9」:「どっちにしようかな…(別にどっちでもいいや)」
あくまでも「一度きり」 (2015.9.5 14:06)
一度でも「奇跡」を起こしたなら、その後は何度でも同じかそれ以上の「奇跡」を求められてしまう。
一度でも「成功」を収めたなら、その後は何度でも自らに同じかそれ以上の「成功」を課してしまう。
一度きりの結果を永遠のものにしようとしてしまうこと自体が、ヒトの罪や罰だったりするんだ。
工夫ある継続 (2015.9.5 11:18)
よく「継続は力なり」などと「4」的な継続を奨励したりする。
しかし本当の意味で力となるのは手前の「3」という「創造性ある試み」を含めた継続であって、ただの「4」だけだとその場で足踏みしているのと大差無くなってしまう。
つまり正確には「工夫ある継続こそが力」ということ。
「6」と「3」のバトル (2015.9.5 1:58)
「6」:「そんなことをしていてはあなたのためにならないよ!」
「3」:「これが自分のためになるかどうかなんてことは自分で決める!」
「自然物」への偏執 (2015.9.5 1:00)
「自然」というのはいわゆる「大局的なバランス」のことであり、「人工物」を忌避するあまり対極のものとしての「自然物」に偏執していくのは既に「自然」ではないよね。
有名という「罰」 (2015.9.5 0:15)
「有名」になるというのは、「無名」では無くなるという「罰」だったりするね。
「感情」の善し悪し (2015.9.4 23:21)
難民問題を見ていて思うのは、人は「感情」により難民を受け入れたとしても、後年その「感情」により難民を追い出していく恐れがあるということ。
「感情」によって決定したことは、また「感情」によっていとも簡単に覆る。
二つの「力」 (2015.9.4 23:05)
「Force」と「Power」、二つの「力」。
物理的な強さ、押したりする強さを表すのが「Force」であり、「1」的かつ直接的な「力」。
一方、潜在的な能力や権威などを表すのが「Power」であり、「8」的かつ間接的な「力」。
「1」で押すもよし、「8」で操るもよし。
「占い」と「メガネ」 (2015.9.4 20:13)
占いって「メガネ」と同じだね。
どれだけ手の込んだものを提供しようとも、度が合わなければ何の役にも立たないから。
「盲信」という盲進 (2015.9.3 22:41)
グチャグチャでドロドロした「7」というカオスな思考はとても辛い。
ただ、いくらラクになりたいからといって、逆数である「2」というコスモスな思考に盲進して良いものだろうか。
それは確かにカオスの沼からは抜け出させてくれるだろうけど、もっとひどい結果が待っているかもしれないよ。
どちらも「愛」 (2015.9.3 22:30)
相手の自由を尊重し、相手の行為を赦していく鷹揚な「愛」。
相手に執着し、半ば所有物のように扱っていく粘着な「愛」。
どちらも同じ「愛」という言葉で表現されるけど、どちらの「愛」がいいですか?
「哲学」の流れ (2015.9.3 21:57)
「2(思考の秩序・静的思考)」という「=」で固くつながっていた自らと世界を「7(思考の混沌・動的思考)」というナイフで一旦バラバラにする。
そして組合せを変えて再度「=」でつなぎ直すという行為。
この「2」→「7」→別の「2」という一連の流れが「哲学」と呼ばれる行為だね。
「5」という覚悟 (2015.9.3 13:25一部改変)
「4」という安寧空間を「退屈」と断じ、そこを未練なく捨て去ろうとする大いなる覚悟が「5」だ。
「ダメ」だから面白い (2015.9.3 12:09)
「ひみつ道具出して〜!」と甘えるのび太と、「しょうがないなぁ…」などと言いながら結局はのび太を甘やかすドラえもん。
この両者のダメダメなやり取りは、ダメな「3」とダメな「6」とが合わさった「9」的ほんわか感を醸し出す。
そんな「ダメ」の存在が許される世界だから面白いんだ。
「9」のドラえもん (2015.9.3 12:02)
2112年9月3日生まれのドラえもんの基本数が「9」というのは、「ドラえもん」という作品を考える上で大切なポイントなのかもしれないね。
「9」という数のイメージが「円」や「球」につながるのとは別に、世界中で皆に愛される存在という意味で。
そういえばのび太は正に「9」だよなぁ。
ハズレを引かない (2015.9.3 11:54)
「4」マインドの強い人が意識しがちなのは「アタリを引く」ことよりも、いかに「ハズレを引かないか」ということなんだ。
「4」のグルメ (2015.9.3 11:50)
新宿に着き、先にポーチを購入。
ダイスの店が開くまでの間、お昼を食べようと美味しそうな店を探すも、結局たどり着いたのは「プロント」のパスタ。
この「どこにでもあり、いつでも変わらぬ、それなりの美味しさ」というのが好きなんだよね。「4」マインドな僕としては。
「力」の行く先 (2015.9.3 11:12)
「8」マインドの強い人が諸事を都合良く進めるために振るう「力」は、回り回って自らを抑圧する「力」へと変わっていく。
自らが振るった「力」に対する責任を自らが逃げずに被るという表現でもいい。
振るった「力」の強さの分だけ、その「力」が今度は自らを何重にも縛り上げていく。
「1」の人の「9」の年 (2015.9.3 10:59一部改変)
「1」の人にとっての「9」の年は、まるで靄だか嵐だかわからない混交した世界の中に自らを飛び込ませるようなもの。
でもあえてそうすることで次の「1」の年がより可能性に満ちたものとなる。
大いにカオスモスの中で揉まれよう。
言わないか、言うか (2015.9.3 8:54)
「4」:「言わなくても気付いてよ」
「3」:「言わなきゃわかんないよ」
TPO (2015.9.2 23:49)
「6」って正に「TPO」の数だけど、「TPO」をゲマトリアしたら「6」になるんだね。
全てを内包する「赦し」 (2015.9.2 22:24)
全ての数を内包した「9」という赦しの数の中には、当然ながら全てを疑い、確かめ、そして考える「7」という検証の数が含まれている。
この「7」の要素を否定し除外した「赦し」がもてはやされたりもするが、「7」の大切さを認めてしっかりと味わった先でこそ「9」という赦しが体現可能となる。
理解か、説明か (2015.9.2 12:43)
「7」:「もっと自分で考えて理解しろよ」
「3」:「もっとわかりやすく説明しろよ」
ネガティヴ・アルケミスト (2015.9.2 8:32)
とてつもなくマイナスな「7」モードに入った人には、どれだけの言葉を尽くして励ましたとしても、その言葉を分解・再構築することでとてつもなくネガティヴな意味に置き換えてしまう。
まさに「ネガティヴ・アルケミスト」だけど、これは同時に「ポジティブ・アルケミスト」の持つ才能でもある。
甘い罠 (2015.9.2 1:31)
「3」というアーティストの両隣には常に「2(コピー)」と「4(パターン)」という甘い罠が潜んでいるね。
エンブレム (2015.9.1 18:22)
「3」の日(2015.7.24)に大々的に発表された東京オリンピックエンブレムが「9」の日(2015.9.1)に見直し発表か。
39日の命に合掌。
「不運」の時こそ (2015.9.1 12:53)
ヒトは一度「不運」な出来事に遭遇すると、目に見える全ての出来事に「不運」のラベルを貼ってしまう。
本当は他の出来事に関しては「幸運」であるはずなのに、それをも「不運」一色に塗り固めてしまう。
「不運」の時こそ、近くにあるはずの「幸運」を探していくようにしたいね。