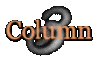
数秘術関連等ツイート(2014年9月分)
暦の「リズム」 (2014.9.30 23:31)
暦が生み出す「リズム」に身を委ね、安心感に包まれながら生きていく偶数人生。
暦が生み出す「リズム」からあえて外れ、冒険を楽しみながら生きていく奇数人生。
暦に入るも人生、出るも人生。
「自由」の中身 (2014.9.29 20:16)
「4」的な環境を自らの意思で壊し飛び出すことは容認するけれど、周囲からそれを強制されると激しく拒絶し「4」の壁の中に閉じこもるのが「5」かもね。
「5」の希求する自由とは「自由意思」の自由であり、環境としての自由とは限らないんだ。
カテゴライズの善悪 (2014.9.29 15:46)
カテゴライズ(分類する)という行為は理解も不理解も同時に生み出し得るね。
本来は理解するために分類するわけだけど、分類したことによって結果として相互不理解を促進かつ容認するケースも多く存在する。
だからカテゴライズという行為は一方的な悪とも善とも言えないよなぁ。
どうしても偏るね (2014.9.28 22:33)
数秘術を扱う際、本当は自らにおける数のイメージをニュートラルに保つことが理想なんだけど、どうしても特定の数のイメージだけプラスかマイナスのどちらか一方に偏るケースがほとんどなんだよね。
偶数的な環境で苦しんだ人が偶数にマイナスのイメージを持ってしまうのは仕方の無いことさ。
自意識過剰 (2014.9.28 22:28)
無関係なヒトの、無関係なツイートが、たまたま自らの心理や状況と合致した場合、それをエアリプとつい捉えてしまうくらいには自意識過剰なんですよ、僕は。
用語なしで (2014.9.28 22:14)
占いの用語を一切使うことなく、皆にわかりやすいアドバイスができる占い師になれるといいね。
家族 (2014.9.28 22:10)
これからみんなが貧しくなっていったのなら再び大家族制度が蘇るんだろうけど、それによって家族の絆が輝きを取り戻す場合もあれば、逆に家族間の憎しみが倍加する場合もあるよなぁ。
家族とは実にすばらしく、そして実に面倒臭い。
「次」のない世界 (2014.9.28 14:13)
何回か失敗している部下が「次こそは必ず!」とリベンジを誓っても、デスラー的上司が「貴様にはもう『次』などない」などと冷たくあしらい処刑ボタンを押すような世界。
いわゆる意識が高い系のヒトが「仕事をするならばこの位の意識を持て!」と言ったりするけれど、もはやディストピアだよね。
自分の「命」 (2014.9.28 14:02)
「俺の命は親のものでも妻のものでも、ましてや会社や社会のものでもない!俺の命は俺のものだ!!!俺の命をどう使おうが俺の自由だ!!!」
自のラインであり「我、保有す」の体現者とも言える「4」的な考え方だし、同じ「4」の僕もこの考え。
ちゃんと自分の命を自分のために使ってるかい?
メジャーリーグ (2014.9.28 12:47)
メジャーリーグの奇数的(混沌)な応援に満ちたボールパークと、日本のプロ野球の偶数的(秩序)な応援に満ちた野球場。
メジャーリーグ中継を観てるとなんとなく対比させてしまうね。
政治の「ブーム」 (2014.9.28 12:17)
政治におけるブームって具体的な政策等で作り出されるものではなく、既存の政治の持つさっくりとした抽象的な性質に対するアンチテーゼが生み出すものだったりするよなぁ。
「4」的な政治に飽きたら「5」的な政治を求めるし、「5」的な政治で混乱したら「4」的な政治を求めるわけだね。
噴火活動 (2014.9.27 19:27)
マグマという動的な混沌たる「1」が次の「2」で地表への道を作り、そして「3」という噴火活動で噴出に至るわけだね。
その次の「4」という安定までにいかほどの日月がかかるんだろうか。
術(アート)の始まり (2014.9.27 0:27)
奇数も偶数も、混沌も秩序も、そして四大元素すらも全てが溶け合っている「9(全)」という世界の溶液から、原初的欲求や衝動などの直観力を駆使して「1(一なる個)」という単結晶を取り出してみよう。
それが数秘術という術(アート)の始まりなんだ。
「逆」から攻めてみよう (2014.9.26 14:49)
たとえば「1」のイメージを理解する際、その数をストレートに理解するだけではなく、他の数のイメージの「逆」のイメージをあてがうことでより立体的に理解することができるかもね。
「8」の自制に対して「1」の衝動、「9」の無我に対して「1」の自我など、「逆」からも数を攻めてみよう。
喜ぶ食べ物 (2014.9.25 16:42)
身体が喜ぶ食べ物を心が喜ぶかどうかは別問題だよなぁ。
受容=排除 (2014.9.25 15:46)
「2」は繋がる線と分ける線の両方を表すけれど、これはつまり「誰かと繋がる」ことを意図すれば則ち「それ以外とは繋がらない」ことを意図しているのと同義となるということなんだよね。
「見たいもの」を定めた途端「見たくないもの」を同時に定めることにもなるわけだ。
受容とは排除なんだ。
「7」こその「3」 (2014.9.25 15:07)
「7」の如く自らの内側にうごめく混沌をただひたすらに掘り進めていくと、やがては掘り進められる限界点に到達する。
その限界点に到達した途端、発作的に補数の「3」が起動し、掘り進めてきた上で発生する諸々の残骸を自らの外側へと大噴出させたりする。
「7」極まれば「3」に転ずるんだ。
「知」の寄り道 (2014.9.25 14:46)
僕のサイト内にあるツイッター集だけど、ページ内検索機能等は特に設けてはいない(ツイログなら検索可能)。
今は目的物を探し当てる際、ウェブ検索で簡単に見つかりやすくなったけど、むしろ延々と探し続ける過程における「寄り道」の方が更にすばらしいものを提供してくれたりもするよなぁ。
有名欲 (2014.9.25 11:30)
もし「数秘術で有名になりたい!」と思ったとしても、その願いって有名にしてくれる存在(=他者)への依存である気がするなぁ。
有名無名関係無く「俺は死ぬまで数秘術をやり続ける!」という継続宣言とか「俺は数秘術になる!」という同化宣言をし、それを何十年かやり通せば嫌でも有名になるよ。
「7」の代表 (2014.9.25 0:50)
求道者としての「7」の代表はイチローで、混沌の闇の権化としての「7」の代表は蛭子能収でいいのではないかと思う。
カオスをのぞき込め (2014.9.25 0:17)
ヒトは「7」という世界のカオスに「2」というコスモスのベールを掛け、思考やそれに連なる生活を安定させている。
そんなオブラートの如きベールを恐る恐るめくり上げ、その内なるカオスをのぞき込む勇気あるヒトは山盛りのリスクと共に世界の真実とまだ見ぬ叡智を手に入れることができるだろう。
セルフブランディング (2014.9.25 0:00)
個人として活動していく以上、いわゆる「セルフブランディング」は必要だろうなぁとは思う。
でも「セルフブランディング」そのものが目的になったらしんどいね。
自分らしく生きて、自分らしく行動し、自分らしく表現していった結果が「セルフブランディング」になるのならそれがいいや。
ヒトの性 (2014.9.24 20:30)
奇数(動性・混沌)に倦んだら偶数(静性・秩序)の鎖に喜んで縛られようとするし、偶数に疲れたら奇数の翼でどこまでも飛んでいこうとするのがヒトの性ってことで。
まだまだ頑張ります (2014.9.24 19:27)
そういえば「明日のダイスメッセージ」をつぶやき始めてからちょうど一年経った。
必要としてくれる人がいる限り今後も続けていきたいと思うけれど、毎日コンスタントにこじつけるのもなかなか大変ではあるよなぁ。
でもこじつけ力の強化には大いに役立っているから、今後も頑張るとします。
無計算という計算 (2014.9.24 13:03)
基本数「7」のローラやスギちゃんが見せるキャラとか芸って、どことなく無計算で放りっぱなしの補数「3」な匂いが漂ってくるしそれで成功してるね。
でも実際は逆数「2」の如く周囲を観察し、場の空気を読み、きちんと計算した結果としてあれらのキャラや芸があるんだなぁという感じで見てる。
広がった世界 (2014.9.24 12:06)
古代の世界はとても「狭かった」ため、占いや暦の及ぼす影響力はほぼ絶対的なものだったし、そこから逃げることもほぼできなかったんだろうな。
でも現代の世界はとても「広くなった」から、占いや暦の及ぼす影響力も相対的に小さくなっていると思う。
それらから逃れる術はいくらでもあるさ。
ただの「おもちゃ」さ (2014.9.24 11:38)
僕の構築した「逆数秘術」は高邁なものでもなんでもなく、言ってみればただの「おもちゃ」。
だからそんな「おもちゃ」の仕組みを学んだり、ただ飾っているだけでは面白くもなんともないよね。
その「おもちゃ」で森羅万象をこじつけて遊ぶことをどんどん楽しめば、何かが「変わる」はずだよ。
起源考・その3 (2014.9.24 11:25)
「9(カオスモス)」から「0(虚無)」へと飛び出した「1(始原というカオス)」は新たなる世界の創造主となる。
その世界は「2(分化というコスモス)」や「3(表出というカオス)」など他の数を経て「9」へと至り、やがて世界は再創造される。
その流れは螺旋と円とを交互に生む。
起源考・その2 (2014.9.24 11:04)
この世界は「0」という虚無から「1」という始原の光が突如として現れたのか。
それとも「9」というカオスモスが初めに存在し、そこから「1」が飛び出して「0」の中に居場所を移すことで「1」が「1」であることを思い出すことができたのか。
「1」の「前」について考えると面白いね。
起源考・その1 (2014.9.24 10:56)
「他」の概念も内外の概念も存在しないのが始原の点である「1」。
「他」や内外の概念が現れ自他の判別が可能となるのが線である「2」。
内外の概念がごちゃ混ぜとなっており判別できないのがカオスモスという全体である「9」。
「9」から「1」の光が生まれ、「2」の線で分けられる。
アウトプットの「3」 (2014.9.24 0:11)
読書という「2(インプット)」を行うと「3(アウトプット)」が実にはかどるね。
ちなみに僕は「1」ではなく「3」にアウトプットの意を与えているけれど、「1」は始原であり内外の概念が存在せず、「2」という内外の境界ができて初めて次の「3(内から外へ出す)」が可能となるんだ。
「数」で遊ぼう! (2014.9.24 0:03)
数秘術を占いとして用いるのではなく、イメージをまとった象徴としての「数」をおもちゃにして、森羅万象相手におままごとごっこで遊び倒して欲しいなぁ。
これメチャメチャ楽しいし、これが楽しめるようになると占いの技量も上がるし、そもそも占いという行為から自然と遠ざかるようになるよ!
それぞれに輝こう (2014.9.23 23:19)
奇数の如くありのままの生を貫き、混沌と遊び戯れる人生。
偶数の如く生をコントロール下に置き、秩序に勤しむ人生。
偶奇両有の「9」の如く混沌と秩序の混在を赦し寛ぐ人生。
どの人生もそれぞれの幸とそれぞれの苦をもたらすけれど、人任せにせず自ら選んだ道であれば自然と輝き始めるさ。
充満 (2014.9.23 22:52)
たとえるなら「8」は「人工的な充満」であり「9」は「自然的な充満」。
静的かつ秩序の「8」がもたらす充満はその空間内にぎっちりと詰まっており、動くことが一切できないイメージ。
動静混合かつカオスモスの「9」がもたらす充満は多少の隙間があり、流動性は失っていないイメージ。
「4」がテーマ (2014.9.23 22:42)
占星術を諦め、長年やってきたタロットもほぼ捨て去り、数秘術ばかりを馬鹿の一つ覚えの如く十年ほどやり続けた結果としての「今」がある。
もちろんこれは死ぬまで続けていく。
「継続は力なり」を正に人生をかけて学んでいくのが僕自身の数である「4」の最大のテーマなのかもしれないね。
いざとなったら (2014.9.23 20:41)
いざとなった時に動ける人はいざとなる前から動いているイメージがあるし、「いざとなったら動くさ!」と言っている人はいざとなっても動けないイメージがあるんだけど何でだろ。
「2」の鑑 (2014.9.23 2:16)
基本数「2」の声優・古谷徹氏。
役作りに大切なのは情報収集であるといい、キャラクターについて手に入る情報はすべて頭にインプットしたり、キャラクター表を見て同じポーズをとってみるといったようなことを自分の体にコピーしていくとのこと。
観察・情報収集・模写の「2」の鑑だね。
「占い」を殺す人 (2014.9.23 0:15)
本気で「占い」を殺せる人こそが、本当の意味で「占い」を生かせるのかもしれないね。
逆数性と「歌」 (2014.9.22 20:14)
「3」はありのままを表現する様を表し、「6」は相手を斟酌して調整する様を表すね。
この逆数性を歌にたとえるならば、「歌う満足(3)、聴かせる親切(6)」って感じかな。
この双方のバランスこそが自他の感動を呼び起こすんだね。
どっちも眉唾物 (2014.9.22 18:38)
誹謗オンリーも礼賛オンリーも僕にとっては眉唾物だわな。
モーニングサービス (2014.9.22 18:17)
中部圏のモーニングサービス(ドリンクを頼むと無料でありえない量の食事がついてくる)って究極の「6(ホスピタリティ)」だよなぁ。
「不幸せ」を探す (2014.9.22 17:02)
自らが「幸せ」を感じたいあまり、他人の「不幸せ」をまるで重箱の隅をつつくように探す行為に名前をつけたいなぁ。
成功と人間性 (2014.9.22 12:15一部改変)
「成功するためにはまず人間性を向上させるべきだ!」などという意見を聞くことがあるけれど、広く世界を見渡してみると人間性としては「?」な人物でも成功している例はいくらでもあるよね。
もちろんわざわざ悪魔になる必要はないけれど、無理をして天使になる必要もないんだ。
ヒトはヒトさ。
粗悪品の「苦労」 (2014.9.22 11:55)
「若い時の苦労は買ってでもしろ!」とはよく言われるけれど、景気がなかなか上向かない昨今だと「苦労」も粗悪品が多く出回るみたいだね。
「買ってみた 苦労によって 殺される」
反組織人と組織人 (2014.9.22 11:51)
奇数人は「反組織人」であり、偶数人は「組織人」って捉えることができるね。
奇数人は社会に適応するべく偶数仮面を身に付けるし、偶数人はストレス解消のためすっぽんぽんな奇数になろうとする。
そして偶奇両有の「9」は反組織人と組織人の往復に疲れ果て、「0」スイッチに手を掛ける。
追い求めない幸せ (2014.9.22 10:01)
「星の影」や「数の幻」を追い求めすぎない方が幸せにつながるのかもしれないね。
当たるも当たらぬも (2014.9.21 22:14)
占いを「サイエンス」と考えちゃうとたぶん誰も幸せにしないだろうから、やっぱり「アート」と考えようよ。
無理して理解を求めたり、根拠を証明しようとしたりせず、それぞれがそれぞれのやり方で楽しめばいいんだ。
当たるもアート、当たらぬもアートさ。
南半球 (2014.9.21 22:01)
大殺界という概念は喩えて言うなら万物が枯れる「冬」のようなものだというけれど、僕ならば「こっちが冬ならばユーは南半球行って夏をエンジョイしちゃいなよ!」てな感じのアドバイスをしちゃうだろうね。
北半球のシステムだけが全てじゃないからさ。
外向きのコントロール (2014.9.21 21:13)
様々なことを限界まで耐えに耐え、忍びに忍んだ「8(コントロール)」的な人は耐え忍ぶべき理由がなくなることで一気に多数の人間や彼らが持つ時間や心までをも横暴的にコントロールする場合があるね。
内向きのコントロールが逆数「1」の暴走によって反転し、外向きのコントロールとなるんだ。
知識か知恵か (2014.9.21 12:17)
知識が乏しい人は「知識よりも知恵の方が大事だろ!」と開き直り、知識が豊かな人は「知識あっての知恵だろ!」と反駁する。
まぁ両方大事ということで。
あくまで「法則性」 (2014.9.21 8:51)
占いで示せるのはせいぜい「法則性」までであって「法則」ではないよね。
占い文化の継承 (2014.9.20 22:27)
占いが当たってた人々が占い文化を紡いでいくという当たり前感。
外側も大切 (2014.9.20 1:08)
数秘術を内側から考えてるだけじゃダメだよ。
外側からも考えないとね。
内側が騒がしい「7」 (2014.9.19 21:07一部改変)
表面は静かでも心の中はガヤガヤワイワイと騒がしいのが「7」の性だから、それを如何に「2」の如く静かにできるかが鍵かもしれないね。
一生の旅は双方向 (2014.9.19 11:13)
ヒトの一生って「1(自己)」から「9(自然との一体化・遍在)」へと向かう旅でもあるし、「9(混沌と秩序の混在)」から「1(始原の混沌へと戻る)」へと向かう旅でもあるね。
なぜ必要かを考える (2014.9.19 10:57)
カバラや生命の樹の解釈論を学び続けるよりも、ヒトはなぜそれらを必要とするのかということについて学びたいし考え続けたいなぁ。
「0」だからわかること (2014.9.19 10:50)
お腹が空いている状態で冷たい飲み物をゆっくり飲むと、食道から胃へとその飲み物が消化器の壁面を伝いながらじんわり下りていくのがとてもよくわかる。
空っぽ(0)だからこそ、生々しい存在(1)を改めて感じることができる。
「9(充満)」が「0」でリセットされてこそ「1」が活きる。
飛べばわかるさ (2014.9.19 10:37)
高くジャンプするためには、その分強く大地を蹴る必要があるね。
ヒトの飛躍のためには、ヒトに大いなる安定をもたらす「4」たる大地に対して「5」たる反発を試みることが大切なんだ。
そうやって「4」を上から見ることではじめて「4」の偉大さを知ることができる。
飛べばわかるさ。
神智学的加算 (2014.9.19 1:16)
「QBL―カバラの花嫁―」にて「神智学的加算」なる単語があった。
何のことかと思ったら、数秘術で見られるところの「単数変換(減衰加法)」のことだった。
ムダにかっこいいな。
興味と目的の順番 (2014.9.19 1:06)
「興味が目的を生む」というのは奇数的な生き方だし「目的が興味を生む」というのは偶数的な生き方だね。
別にどちらを選んでもいいけれど、もし行き詰まったらその時は「逆」を選んでみようか。
興味と目的 (2014.9.19 1:02)
目的が興味を生むのではなく、興味が目的を生むんだ。
積読 (2014.9.19 0:52)
たぶん「積読」してるという時点で、その本は現在不要かあるいは大して面白くない本っていう判断でもいいのかもね。
本当に必要でかつ面白い本ならば入手した後に勢いで一気に読んじゃうだろうから。
そんな自らの「気分」をフィルターにして読む読まないを判断してもいいと思うよ。
宿題は出しません (2014.9.19 0:06)
そういえば僕の講座で宿題は出したこと無いなぁ。
まぁ宿題を考えたり添削するのがメンドーなだけなんだけどね。
でも質疑応答はいつでも大歓迎だよ。
つまりは受講者のヤル気さえあれば、何十万円のカリキュラムにも匹敵する内容をマスターできるという自画自賛自惚れアピール。
ゼネラリスト (2014.9.18 21:18)
「ゼネラリスト」という概念が「適材適所」を殺していくね。
美をもたらすもの (2014.9.18 21:14)
「6(美)」をもたらすのはいつだって「1(意志)」+「5(破壊)」なんだ。
頼り過ぎないで (2014.9.18 20:28)
自分をアゲてくれるものばかりに頼っていると、いつかそれ以上にサガる羽目になるから気をつけようね。
当てられ屋 (2014.9.18 18:24)
占い師のメンタルヘルス向上のために「当てられ屋」でも派遣しようかしら。
どんなに見当違いなリーディングであっても、提示された象意に自らの経験や感情を強引にこじつけまくり、ことごとく当てられた感を演出するという感じ。
つか俺が「当てられ屋」になればいいのか。
偏りによる意識の強化 (2014.9.18 17:30)
数の偏りにしても星の偏りにしても、それらが招くのはつまり「意識の強化」って感じなんだろうね。
過多となった要素はもちろんのこと、それによって反対側に生まれる過少の要素も意識しやすくなる。
過多でも過少でもなく平坦であれば、意識はむしろ弱化するね。
「4」+「1」=「5」 (2014.9.18 17:12)
四大元素という「4」はヒトも含めた万物の基礎であると同時に「4」たる法則性の中にヒトや万物を完全に閉じ込めてしまう。
そんな「4」的な閉鎖空間から脱兎の如く飛び出し、法則性からの解放を試みるのが「5」という知性を持ったヒトの性。
「4」に意志の「1」を加えてこそ「5」となる。
十字架と五芒星 (2014.9.18 16:53)
十字架という「4」に縛られている人類は五芒星(または五光星☆)という「5」によって解放されるというこじつけ。
偶数という「忍耐」 (2014.9.18 12:31他)
考え過ぎた挙句動かず様子見に徹する「2」は思考としての忍耐。
心身を鈍らせて気付かないふりをする「4」は感覚としての忍耐。
大好きな気持ちが暴走しないよう防ぐ「6」は感情としての忍耐。
自身の我慢で全てを良くしようとする「8」は直観としての忍耐。
さっきの偶数という「忍耐」についてだけど、「6」はこう書き換えておこうかな↓
大好きな気持ちを覚られないように隠し通す「6」という感情の忍耐。
偏らない思考 (2014.9.17 4:18)
極端な「7」がもたらす思考の暴走という混沌。
極端な「2」がもたらす思考の停止という秩序。
どちらにも偏らないように生きていきたい。
「1」を止めるもの (2014.9.17 0:43)
「1(ヒトの獣性)」を抑え得るのは「8(絶対的コントロールシステム)」なんだよなぁ。
暴走を止める偶数 (2014.9.17 0:20)
「7」の暴走を止めるのは「2」というたった一人の理解者の眼差し。
「5」の暴走を止めるのは「4」という自らの存在が許される居場所。
「3」の暴走を止めるのは「6」という社会の役に立っている充実感。
「1」の暴走を止めるのは「8」という世界を支配する絶対的な摂理。
カバラの花嫁 (2014.9.16 23:40)
今読んでいる「QBL―カバラの花嫁―」によって、生命の樹が少しずつストンストンと僕の中に入ってくる。
とは言っても僕は「逆数秘術」の体系をカバラ色に染め上げる気はない。
でも今まで意固地になっていたけれど、良い本に出会ったことで漸く固く閉じていた扉が少し開いた感じがするよ。
「学習」の順序 (2014.9.16 23:25)
数の順番で見てみると「学習」の順序としては「2」の如くまずは受動的に見聞きして真似て、その後に「7」の如く能動的に考えて問い質すというのが正しいのかもしれないね。
先に「7」から初めてしまうと思考の混沌に飲まれてしまい、抜け出せなくなるかもしれないから。
三つの三つ組 (2014.9.16 21:47)
「1」「4」「7」は「自のライン」だが、言い換えるなら「主動者の数」。
「2」「5」「8」は「他のライン」だが、言い換えるなら「対立者の数」。
「3」「6」「9」は「愛のライン」だが、言い換えるなら「調停者の数」。
主動(正)・対立(反)・調停(合)の三つ組が三つできる。
どちらも美しい (2014.9.16 21:26)
奇数というヌードも美しいし、偶数というベールを着けてもまた美しい。
混じり合うテーマ性 (2014.9.16 17:42一部改変)
誕生日の一ヶ月くらい前から少しずつ次の数のテーマ性が現れ始める。
ちょうど濃度の異なる液体同士が混じり合うような感じ。
二つの「個」 (2014.9.16 16:11)
他者を全く意識しない完全なる「個」であれば、ヒトは偶数の衣を脱ぎ捨てて奇数のまんまで生きるだろうね。
でもごくフツーに他者を意識している状態の「個」であれば、ヒトは偶数の衣をなかなか脱ぎ捨てられないんだろうなぁ。
前者は「個の中の個」だし、後者は「他の中の個」だね。
「6」の先の「7」 (2014.9.15 9:52)
表層の美を掘り下げ、その美の存在意義までをも追求していくのが「6(美)」の先にある「7(深遠)」なんだね。
DIY癖 (2014.9.14 23:59)
「4」の人で割と多いのが「DIY(Do
It Yourself)癖」を持つ人。
つまり全てをなるべく独力でこなそうと奮闘を重ねる癖のこと。
この「DIY癖」によって素晴らしい成果がもたらされることもあるけれど、逆に遅々として作業が進まなくなることもあるから功罪相半ばするね。
どの生年月日でも (2014.9.14 22:05)
正直言うと数秘術でその人の数を算出する際、実際の生年月日でも届出上の生年月日でもどちらでも、その人となりを表すことは可能なんだ。
そして更に言うと、その生年月日がたとえデタラメなものであったとしても、その人となりを言い表せるんだ。
出てきた数はどんな数でもその人の一部である。
フォールスメモリー (2014.9.14 21:47)
想像力豊かなヒトという種族はその想像力の豊かさ故に「フォールスメモリー(誤った記憶)」を生み出しやすいという。
占いが「当たる」ということも実はこの「フォールスメモリー」が一役買っているんじゃないかな。
占いの結果と実際の現実との間にある隔たりを自ら埋めようとするんだ。
誤り (2014.9.14 21:42)
自らの思考に誤りが無いと思えば思うほど、かえって致命的な誤りを起こすことになり得るというのが「7」という思考の混沌を表す数の裏表だね。
在るから在る! (2014.9.14 15:58)
自分自身、則ち「1」という存在が何故あるのか、などという理由は決してわからないしわかりようがない。
「存在する」ということを思考では定義できず、感情でも求められず、感覚でも捉えられない。
ただただ「1」という直観において「在るから在るのだ!」などと断言せざるを得ないのだ。
商うということ (2014.9.14 15:05)
高額な専門書を買い、読み進めて知識を深め、内容をカスタマイズした上で独自の講座を開き、購入資金を回収していく…以下その繰り返し。
高額な講座を受け、通い詰めて知識を深め、内容をカスタマイズした上で独自の講座を開き、受講料金を回収していく…以下その繰り返し。
畏怖は抱かない (2014.9.14 14:53)
なんだかんだで僕は怖がりなので「恐怖」の念は持つけれど、「畏怖」の念は全く持たない。
つまり自然災害等で僕の身体が危険にさらされればそれ自体に「恐怖」することはあるけれど、その危険を与えてくる存在に対して「畏怖」の念は抱かない。
あるのは「このクソったれが!」の罵詈だけだ。
「2」の集まり (2014.9.14 14:43)
社会はコントロールする側(8)とコントロールされる側(2)とで成り立っているけれど、実は「2」の集まり(2×2×2)こそが則ち「8」だったりする。
「2」には観察の意もあるけれど、相互に観察し牽制し合うことによって、「2」という関係性自体がコントロールシステムとなるんだ。
絆や愛という道具 (2014.9.14 0:13)
社会をコントロール(8)する際、最も効率的なのは網の目状の絆(2×2×2、則ち2の3乗)の構築。
相互の絆が互いを繋ぎ止め合うことで社会としての全体性を保っていける。
そしてその効果をより高めてくれるのは友愛という倫理観(6=2×3)。
絆も愛も道具に過ぎない。
信仰と検証の時代螺旋 (2014.9.13 23:45)
信仰(2)の時代と検証(7)の時代の螺旋ゲーム、最終的な勝者はどっちになるのかしらね。
納得の「9」 (2014.9.12 17:57)
「無の書」「カオスの書」の著者であるピート・J・キャロル(1953年1月8日生)の基本数が「9」という納得感。
「1」と「0」の間 (2014.9.12 17:48)
「1」なる願望や欲求を消していくも、完全なる無である「0」までには至らないよう、ほのかにそれらを残しかつそれらの存在を赦していく「9」的な境地。
「1」なる欲望の炎に焼かれることもなく、「0」なる真空に窒息することもなく、「9」という遍在の自然の中で生きていけるまでが大変だ。
悪口の平等性 (2014.9.12 14:54)
暴力的な復讐をしてはいけないということを前提に置くとして、僕は健常者と障害者とが互いの悪口を言い合えるようになるのが本当の意味での平等社会な気がするんだ。
「お前"目明き"なのに物の道理が見えてねぇなぁ!」とか「お前"五体満足"なのに大した人生送ってねぇなぁ!」みたいな。
「熱さ」はあるか? (2014.9.12 0:14)
なんかTLを眺めていて思うんだけど、占星術師ほどの「熱さ」を数秘術師が果たして持っているんだろうか、ってことがふと気になった。
システムとしての単純さは「熱さ」をも平べったくしているのかねぇ。
つーか「熱さ」が無くても何とかなっちゃうのが数秘術のザンネンさなのか。
多様性か小コロニーか (2014.9.11 21:32)
それぞれがそれぞれの違いを認め合い、多様性という全体の中で生きていく「9」的ライフ。
でももしそれに耐えられないのであれば、自分と等しい存在のみを認めて手を繋ぎ、小さなコロニーをそれぞれで形成していく「2」的ライフという選択肢もある。
でも時間が経つと序列化しがちだけどね。
昭和天皇のテーマ (2014.9.11 20:34)
昭和天皇(基本数「8」)の実録が話題だね。
新聞で概要をかいつまんで読んでいるけど、立憲君主を強く意識していた昭和天皇は政府や軍部に遠慮してしまい、結果として軍部の暴走を抑えることができなかったという。
「8」の昭和天皇のテーマが正に「8(コントロール)」だったわけだ。
発作的な変化 (2014.9.11 19:51)
基本数「4」の人が見せる逆数「5」的な変化や脱出。
「4」の特性を活かして耐えに耐え、なるべく動かないようにしてきたケースの場合、逆数「5」が発作的に発動しやすくなるね。
突然の家出・蒸発・放浪・逃亡…命と心を守るため、自らを蝕む環境からの脱出はいつだって突然なんだ。
自己保身(心) (2014.9.11 18:36)
基本数「5」の人が自分にとって都合の悪い現実や変化を受け入れないようにするため、逆数「4」をフル発揮して心や耳に壁を設けて聞かなかったことにし、自己保身(心)を徹底するケースを目の当たりにしている。
「5」は変化や自由の数だが、「5」だからといってそれらが得意とは限らない。
数に神秘はいらない (2014.9.11 16:28)
僕自身が大変にうさんくさい人間ではあるけれど、「数の神秘」という更にうさんくさい表現は用いないようにしているよ。
なにせ「神秘」性を与えているのは人間のエゴだからね。
「数」はただ「数」でしかないんだよ。
いろんな「カタチ」 (2014.9.10 23:36)
あるべき夫婦の「カタチ」。
あるべき母親の「カタチ」。
あるべき家族の「カタチ」。
これらの「カタチ」があることで幸せを感じられる人も中にはいるけれど、逆にこれらの「カタチ」に縛られることで大いに苦しむ人もいるね。
もし苦しかったら、こんな「カタチ」捨てちゃってもいいんだよ。
それぞれを為せ (2014.9.9 23:55)
「1」ならば後ろを振り返るな。
「4」ならばじたばたするな。
「7」ならば慌てて先走るな。
苦い薬の飲ませ方 (2014.9.9 14:40)
「7」という苦い薬の飲ませ方。
・オブラートに包んで飲ませる(逆数「2」)
・甘く味付けして飲ませる(補数「3」)
・効能を言い聞かせ飲ませる(隣接数「6」)
・「良薬は口に苦し」と無理やり飲ませる(隣接数「8」)
気まぐれ (2014.9.9 14:27)
「気まぐれ」は最高の贅沢さ。
「7」の毒と薬 (2014.9.9 13:58)
「7」の毒舌や毒批評は当人に「毒」の意識はほとんどなく、むしろ「薬」くらいに思っていたりもする。
問題なのはその「薬」の濃度が高過ぎて、受け取る側にはモロに「毒」となりがちとなる点なんだよね。
とはいえ、この「7」の「薬」は心の奥にズキンと突き刺さるから特効薬にもなるね。
9月9日 (2014.9.9 12:42)
9月9日という「多様性の海の中にみんな溶けちまえバカヤロー!」感。
「1」と「10」 (2014.9.8 17:10)
奇数であり動的であり混沌でもある「1」という始原。
数字根(単数変換後の一桁の数)は同じ1ながら、偶数であり静的であり秩序でもある「10」という終着。
タロットの数札から見えてくる「1」から「10」への物語と「10」から「1」への物語。
タロットの塔 (2014.9.8 10:02)
天にも届くばかりの巨塔を建て、万物を意のままに操るかの如く振る舞ってきた「8(コントロールする)」が、実際には天に操られるだけのか弱き「2(コントロールされる)」であることに気付かされるのがタロットの「塔(16=8×2)」なのかもしれないね。
瞑想の両性 (2014.9.7 16:21)
「瞑想」という行為の「7」というダイナミック(動的)と「2」というスタティック(静的)に思いを馳せてみる。
「違い」で理解する (2014.9.7 10:20)
ヒトは「違い」を知覚することで、初めてその対象を理解し得る。
奇数という存在があるからこそ、偶数が理解できるし、逆もまた然り。
奇数偶数の両極性が混じり合った状態かつ全であるところの「9」があるからこそ、極性無き状態かつ虚無である「0」が理解できるし、逆もまた然り。
デコントロール (2014.9.7 9:33)
端的に言うと、偶数は「コントロール」であり、奇数は「デコントロール(コントロールから外れる)」なんだよね。
オートマトン (2014.9.6 16:30)
「2」という他者重視の鏡反応。
「4」という無意識的反復行動。
「6」という世界への善性反映。
「8」という超禁欲的な自制心。
奇数性という混沌に飲み込まれぬよう、そして社会から逸脱せぬよう、人は偶数性という秩序を身にまとい、自らを「オートマトン(自動人形)」と化す。
対戦相手 (2014.9.6 13:29)
「神」なる存在が自らの偉大さや強大さを衆生に示そうとした時、一番手っ取り早いのは対戦相手を募ってバトルし比較させること。
その相手が強大かつ凶悪であるほどに、勝つ側である「神」の強大さや偉大さが強く印象付けられる。
この八百長バトルのために生み出されたのが「悪魔」なのかもね。
悪戯の神 (2014.9.6 13:21)
創造主としての「1」は正に混沌の至高であり、言うなれば「悪戯の神」という感じ。
しかしながら創造物としての我々から「1」を見ると、全てを完璧にコントロールする秩序の至高としての逆数「8」に見えてくる。
まるで作為なく戯れに創った作品を周囲が芸術の極みと褒めちぎるかのようだ。
全ては数か? (2014.9.6 12:01)
ピュタゴラスは「全ては数である」と言い、バリエッタは「全ては数であり振動である」と言ったとされる。
でもこれはあくまで「全ては数で表し得る」というだけの話(これもちと傲慢だが)であり、数そのものに万能性や根拠なきパワーをまとわせるのは少し違う気がするなぁ。
全て≠数だよ。
前世と来世 (2014.9.6 11:43)
「前世」なんてただの憧れだし、「来世」なんてただの慰みだよ。
創る「6」、滅ぼす「6」 (2014.9.5 23:43)
「キレイなものを創ろう!」と一念発起し、世界を「6」日間で創り上げるのも一つの「美」。
「汚れたものを消し去り、キレイを取り戻そう!」と一念発起し、世界を「6」日間で滅ぼすのもまた一つの「美」。
キレイを創るか、取り戻すか。
ひとつになる (2014.9.4 23:57)
対象と溶け合うも辛うじて朧げに個も他も残る「9」。
手繋ぎ抱き合うも溶け合うことはなく、それぞれが個として存在する「2」。
混じり合ったものを完全に自己として吸収する「1」。
混じり合ったものに完全に吸収され、自己が消滅する「0」。
「ひとつになる」もいろいろあるね。
全てを通過しよう (2014.9.4 13:52)
自と他の境界がおぼろげとなり、上下・前後・内外・左右などの概念すらもぼんやりする境地が正に「9」なんだけど、いきなりこんな境地になったならほぼ確実に発狂するだろうし、一気に逆数「0」のスイッチが入っちゃう。
そうならないためにも「1」〜「8」をきちんと経験しないといけないんだ。
学びの終着点 (2014.9.4 12:38)
僕は「占いを学ぶ」という行為の終着点は「過去も未来も、そして現在をも気にならなくなる」心境に達することという考え方を持っているけれど、実際には真逆に生きていく人も多いよなぁ。
自分の過去・現在・未来を知りたがるだけならともかく、他人のそれをもやたらと知りたがるのはしんどいね。
汚いものを探す (2014.9.3 2:36)
自らの心の美を目指せば目指すほど、自らの心の醜に耐えられなくなっていく。
いい人であろうとすればするほど、いい人ではない自分が嫌になっていく。
美や善を目指す「6」は醜や悪に気付く「6」でもある。
「綺麗にする」ということは「汚いものを探す」ということと同義なのだ。
面倒なフォーマル文化 (2014.9.2 14:11)
猛暑の最中、冷却ファンがついたYシャツや制服を見かけることがあるけれど、もっとシンプルにTシャツとかで涼を求めることができればいいのになぁ、と思っちゃうよ。
行き過ぎたフォーマル文化はヒトを実に生きにくくするよなぁ。
大事なのは連続性 (2014.9.2 13:18)
何かを毎日続けようとして、たまたま三日だけそれが出来なかっただけで落ち込み、継続そのものをやめてしまうのは極めてもったいない限りだね。
もしそれを十年続けたならば、その三日は実にささいなものでしかなくなるさ。
肝心なのは「必ず毎日続けること」ではなく「全体としての連続性」さ。
バトルは満腹 (2014.9.2 0:15)
互いのイデオロギーが仲良く融和しちゃったら面白くないから、ただひたすらにバトルを繰り返させて無理矢理に面白くしていく。
そういうのはもうお腹いっぱいなんだ。
夫婦というキセキ (2014.9.1 18:18)
夫婦関係を保つことって正にキセキの連続だよなぁ。
何もかもが異なる二人が一つ屋根の下で同じ物を食べて一緒の時を過ごすという大キセキ。
そんなキセキを起こしまくってる自分たちをまずは褒めてあげようか。
「そんなの当たり前さ」などと思っていると、一寸先の落とし穴にドボンさ。
やりがい生きがい (2014.9.1 18:09)
他人の嫌がることを率先してこなすことにやりがいを感じる「6」。
自分の好きなことを率先してこなすことに生きがいを感じる「3」。
「6」をやり過ぎて疲れたら「3」で心を癒し、「3」をやり過ぎて倦んだら「6」で気を引き締めよう。
好き嫌いをハッキリと (2014.9.1 14:54)
「好き!」をハッキリと表明すれば、同好の仲間が増えていく。
「嫌い!」をハッキリと表明すれば、同意する仲間が現れる。
好き嫌いをあいまいにするのも一つの処世術だろうけど、両者をハッキリと表明することで人生に素敵なメリハリが訪れるかもね。
「消える」と「満ちる」 (2014.9.1 14:43)
消える(0)からこそ満ちる(9)を感じられるし、満ちる(9)からこそ消える(0)を感じられるんだ。