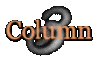
数秘術関連等ツイート(2014年5月分)
正解 (2014.5.31 22:41)
先に正解を教えてくれるのが「直観」であり、間違いを後から正解に変えてくれるのが「思考」だね。
だからどっちも大切なんだよ。
印籠 (2014.5.31 21:01一部改変)
これからもきっと「ユング」という紋所入りの印籠は半可通たち(私も含め)に使われ続けるんだろうな。
できることならその印籠の中身をじっくりと調べていきたいものだ。
便利な「ユング」 (2014.5.31 20:32)
「ユング」は実に便利だ。
しかし便利過ぎていけない。
「1」という才能 (2014.5.31 12:45)
「アンモニア水を作ってみたい」という考えを即実行に移し、庭先で実験を行った結果異臭騒ぎを起こしたのが基本数「1」の福沢諭吉とのこと。
「1」は自のラインの数だけど、自らの衝動や欲求を叶えるため「周囲を顧みない(=自分のやっていることだけを見る)」というのは一種の才能なんだ。
憧れかつ嫌悪の対象 (2014.5.31 12:37)
万事を如意に操る「8」を羨む「1」だけど、実際に「8」の立場となったなら途端に大人の面倒臭さを感じてしまう。
自らの衝動に素直に生きる「1」を羨む「8」だけど、実際に「1」で生きてみるとその幼稚さに愕然としてしまう。
逆数は憧れの対象であり、同時に嫌悪の対象ともなるんだ。
無駄を嫌う「6」 (2014.5.31 11:54)
「6」の持つ美意識の一つに「効率性(無駄を嫌う)」がある。
そのため他者に対して言動の効率性を求めることもあるのだが、問題なのはその刃が自らに向かう時。
「6」は無駄かつお遊びな部分(逆数「3」)を発揮してストレス軽減を図るけど、それにすら自己嫌悪を感じるという美意識の呪い。
「4」の長時間労働 (2014.5.31 10:47)
「4」には継続性とかコツコツなどの意もあるけれど、「4」の人って「長い時間働いている」ということに高い価値を見出していたりもする。
もちろんその価値観と実績とがきちんと結び付いていればいいんだけど、中にはただ継続性ばかりを重んじ、徒らに長時間労働を重ねる「4」もいるね。
批判 (2014.5.30 22:05)
自らの感覚に従い、対象を洞察せずに反発するのが「5」の批判。
自らの思考に従い、対象を洞察しつつ反発するのが「7」の批判。
「6」の喜びと呪い (2014.5.30 14:01)
現代数秘術において美や他者愛を表す「6」。
「人は人を愛すべき」という「6」的な美意識は人々に様々な喜びをもたらすこともあれば、絶望的な呪いをかけることもあるね。
もちろん愛することはとても美しいことだけれど、無理に愛さなくてもいいし、愛せない自分を責める必要は無いんだ。
無言に等しい語り (2014.5.29 22:05)
「逆数秘術」なんて代物を作っている僕は普段から「正」と「反」のシンメトリーを意識してつぶやいていたりするし、片方に偏らないような結論付けを心掛けたりもしている。
けれどもそういったつぶやきは結局のところ「何も語っていない」のと大差無いのではないかと、ふと考えたりもするから困る。
分かれ (2014.5.29 21:38)
どっかの政党が分党するようだけど、「分かれる」ということは則ち「くっついていた」ということなんだよね。
野性でくっつき、理性で分かれる。
理性でくっつき、野性で分かれる。
いずれにしても最善であれ。
見えない網からの逃避 (2014.5.29 20:32)
無意識的にいろんなものと繋がったり受け入れたりしてしまう「2」的な人は多い。
そしてそんな強制的に作られた「2」から離れるべく逆数「7」を発動し、自らの内側をどんどんと掘り下げ隠れる。
人々の視線、人々の声、人々の反応、それらによって編まれた社会の見えない網からの逃避だ。
セレモニー (2014.5.28 17:47)
セレモニーとはつくづく「分かれ(別れ)」だね。
繋がっていた線(2)と分かつ線(2)とがクロスする交点にも見える。
家の繋がりと分かつセレモニー。
命の繋がりと分かつセレモニー。
曖昧なままにせずはっきりと線引きすることで、再び現実世界を一歩ずつ進んでいけるんだね。
エールとお願い (2014.5.28 17:13)
奇数の人全てに言いたいのは「社会という偶数性に潰されるな!」ということだし、偶数の人全てに言いたいのは「奇数を見かけたらどうか大目に見てやってください」ということだね。
誰でも良かった (2014.5.27 10:32)
「誰でも良かった」という言葉。
「9(曖昧模糊)」の中で放った「1(衝動)」の矢だよなぁ。
今まで上手に「1」の矢を放つことができなかった人間は、まるで帳尻合わせの如く闇雲な「9」的空間へと己の「1」を解き放つ。
実に哀しきアーチェリー。
男性性と女性性 (2014.5.27 10:15)
現代数秘術では「1」を男性性、「2」を女性性と捉えるが、「0」の概念が未成熟であった古代において「1」は正に始原の神であり、通常の数扱いされていなかったんだ。
そのため数は「2」から始まり、「2」は男性性、「3」は女性性を表した。
生命の樹のコクマーとビナーもそうだね。
ひどい宣託 (2014.5.27 0:26他)
10面ダイスの宣託。
今の自分は何をすべきか?
→「7(もっともっと掘り下げろ)」
では何を「7」すべきか?
→「7(思考を更に掘り下げ、目に見えぬものの豊かな価値を知れ)」
あ、はい。
てなわけで先程の宣託にてダブルで「7」が出たため、これから先もしばらくは引きこもりに励みたいと思います。
異文化 (2014.5.26 1:02一部改変)
「もっと異文化を受け入れよう!」という意見には賛成なんだけど、かといって拙速かつ強制的にもたらされると反発したくなるのが人の性だよね。
自然に緩やかに、異文化が少しずつ自文化に染み込んでいくくらいが僕としてはちょうど良いや。
「世代」という単位で浸透していければいいかな。
「7」が求めるもの (2014.5.26 0:13一部改変)
本当に信じられる人との強靭かつ柔軟な関係性、信じ受け入れられるものとの豊かな繋がり(むろん強制的なものではなく)…
「7」が求めるのはこういった逆数「2」的なものだったりもする。
箱 (2014.5.25 23:52他、一部改変)
奇数は「箱から出たっていいじゃん!」と考えるし、偶数は「箱の中にキチンと入れなきゃダメ!」と考える。
でも偶奇両有である「9」の場合、そもそも「箱」の概念が存在しない。
出るとか入れるとか、そういったことにすら囚われていないんだ。
奇数は偶数(箱の中)を見るし、偶数は奇数(箱の外)を見るんだね。
箱にうまく入れない奇数はむしろ箱から出ていくことで、入れない自分を納得させようとする。
箱から中々出られない偶数はむしろ箱の中に居続けることで、出られない自分を正当化しようとする。
奇数は偶数に憧れ、偶数は奇数を羨むんだね。
信仰という「線」 (2014.5.25 23:35)
「信仰」という「2」的な線。
この線が適度な長さであればいいのだが、短過ぎれば「1」の如く信仰対象との合一や自らの絶対化を図ったりする。
かといって長過ぎれば「3」の如く信仰の素晴らしさの喧伝や信者集めに邁進したりする。
「2」の如く一人静かに信仰の豊かさを味わいたいね。
「7」の年の混沌 (2014.5.25 22:34)
2014年という「7」の年は、正に人間の心の底に渦巻く混沌について深く考えさせられる出来事を多く見かける。
そしてこの未分化かつ不分化な混沌を逆数「2」的に無理矢理分化して捉えようとする傾向も強まっているように見える。
そんな簡単に善悪や黒白は付けられないだろうに。
癌化とアポトーシス (2014.5.25 20:04)
体内において細胞が不死可し、無限増殖を繰り返す「癌化」。
個体の正常性維持のため、プログラム的に細胞が自死する「アポトーシス」。
前者は奇数(動的・混沌)、後者は偶数(静的・秩序)に喩えられる。
この両者の均衡が崩れることで「病」という状態へと移行していく。
諦めてこそ (2014.5.24 23:05一部改変)
「1(意志)」が静まり、「9(諦念)」に転じてうまくいくパターンってのもあるよね。
「1」と「8」の希望 (2014.5.24 22:26)
自らの行動で一点の「希望」を指し示すのが「1」。
会議室のプロジェクターに「希望」の全体像を映し出すのが「8」。
「9」の中で放つ「1」 (2014.5.24 21:13)
方向性が決まっているように見えても実はそうではない場合、ダイスで「9」がよく出るなぁ。
いまいちはっきりとしない様を表すのも「9」だけど、あらゆる可能性に満ちあふれている様を表すのも「9」なんだよね。
とりあえずは「1」の矢を放って、ひたすら真っ直ぐ進んでみようか。
「オカルト」を教える (2014.5.24 16:43他、一部改変)
オカルトに対する偏見を無くすためには、現代社会において「権威的」な何かがオカルトをきちんと教えていく必要があるよなぁ。
これだって立派な「文化」なんだからさ。
いつだって無知が偏見を産むんだ。
でも「権威的」な何かがオカルトについてきちんと教えることで、オカルトがオカルトでは無くなっていくのかもね。
後付けの欲求 (2014.5.24 11:12)
万事をコントロールしないと気が済まない「8」的な人は多いけど、そういう人って逆数である「1(欲求・意志)」を後付けで偽造したりするね。
元々欲しくもなく意志もなかったにも関わらず、全てをコントロールしないと気が済まないため、不要物をも「欲しい」と思い込み偽りの意志を発現させる。
あくまでも「説明」 (2014.5.24 0:26)
数値ではない象意としての「数」が人の性格に影響を与えているわけではなくて、人の性格の仕組みを「数」を用いて説明しているに過ぎない。
少なくても「逆数秘術」ではそうだ。
前を見たいんだ (2014.5.23 16:44)
未来はドンピシャで当てるけど過去はサッパリな占い師。
過去はドンピシャで当てるけど未来はサッパリな占い師。
多くの人は前者を選ぶんじゃないかな。
どんなに怖がっているように見えても、みんな前を見ているし、見ようと必死で頑張っているんだね。
ニヒル (2014.5.23 16:34)
ニヒル(虚無)を騙るのか、ニヒルを哀しむのか、ニヒルを怖れるのか、ニヒルを赦すのか、ニヒルを楽しむのか、ニヒルを喜ぶのか。
人生を歩む過程で様々な「ニヒル」に遭遇するだろうけど、どれもが同じ「ニヒル」なんだよね。
面白いね、「ニヒル」。
さよなら二元論 (2014.5.23 16:01)
僕の「逆数秘術」のように数に対称性を与えることで二元論的に理解を深めることはできるんだけど、実際の森羅万象は二元論では片付けられないからなぁ。
「二元論」から入って「二元論」から出て行く、そして最終的には「○元論」的なものにこだわらなくなればそれでいいのかもね。
熱中と冷静 (2014.5.23 15:05)
鉄を鍛える際は加熱と冷却を繰り返したりするけれど、学問でも似たようなことは言えるのかもね。
情熱を持ってその学習にハマり込む「熱中」と、学ぶにつれて客観的にその対象の価値をはかるようになる「冷静」の繰り返し。
深く深く掘り進める動的な「7」と静かに見定める静的な「2」だね。
健全な共依存 (2014.5.23 14:54)
「(広義の)共依存的な関係」を考えてみる。
二者間の繋がり(2)が強固となることで生み出される社会との隔絶(7)が得てして問題となりやすいけど、もし二人だけで健やかに生きていけるのならばそれは決して悪いことではないと思うなぁ。
もちろん狭義の「共依存」なら話は別だけどね。
数秘術の真髄 (2014.5.23 14:20)
象意をまとった「数」というフィルターに具象化された全てのものを通すことで一旦概念化し、そして再具象化させる。
これが「数秘術」というアートの真髄なのかもしれない、などという考えに至り始めた。
普遍と特殊 (2014.5.23 14:06)
「4(普遍)」の中に「7(特殊)」を見出し、「7」の中に「4」を見出す。
当たり前という不思議、不思議という当たり前。
「7」へ逃げ「2」に戻る (2014.5.23 12:16)
人を見て人と繋がり、家族を見て家族と繋がり、社会を見て社会と繋がる…こんな「2」を過剰に働かせる人は多い。
そんな「2」が逆数「7」へ反転し、周囲の雑音から離れ、独りの内なる静かで豊かな精神世界へと逃避を図るのは極めて自然なことだし、そうすることで無理のない「2」へ戻れるんだ。
「みる」か「みせる」か (2014.5.23 11:13)
「2」は見る(看る)努力、「3」は見せる(魅せる)努力だね。
どちらも大切だ。
距離を測らず (2014.5.23 1:15)
目指す目標までの距離をつい測っちゃうと、直後に目の前が真っ暗になっちゃうことがあるよ。
自転車での遠乗り(100〜200km)をやってる時とか特にね。
だからそういう時は道の長さを気にせず、ただただペダルを漕ぐことのみに意識を集中するようにしてる。
人生にも当てはまるかも。
ロープレ人生 (2014.5.22 14:40)
会社なんぞレベル上げ&ゴールド稼ぎのためのダンジョンに過ぎないさ。
本当の冒険は会社の外にある!
「9」と「不可解」 (2014.5.22 13:48一部改変)
「9」自らが世界や他者の不可解さよりも自分自身の不可解さにきちんと向かい合った上でそれを赦せれば、人生が大きく変わっていくんでしょうね。
「9」と「遊び」 (2014.5.22 13:30他、一部改変)
「9」の場合はおもちゃも箱も、そしておもちゃを動かす行為や楽しいという感情すらも内包している「遊び」そのものと捉えることができるね。
「9」は自らも含めた世界そのものが遊び相手だから、興味や集中ですらもそのお遊びのほんの一部分に過ぎないと捉えてみても面白い。
「数」を見つけよう (2014.5.22 12:35)
突如として発生(1)し、局所的に雨嵐をもたらし(5)、あっという間に消え失せていく(9→0)「雲」という曖昧模糊(9)な存在。
この自然現象の中にも実に様々な「数」が見えてくるね。
ある程度数秘術本で数の象意を落とし込んだら、傍らに本を置き森羅万象の中の「数」を見つけよう。
数秘術は「分けるツール」 (2014.5.22 9:56)
理解しようとする対象が余りにも巨大な場合、ヒトはその対象を細分化したりその一部分を切り取ることで、理解につながる観察や分析を容易なものにしてきた。
つまり「分かる」ために「分ける」ということ。
数秘術とは森羅万象を1〜9(0)に「分ける」ことで「分かる」に近づくツールなんだ。
恥を感じる「6」 (2014.5.22 9:16)
「自分は醜くて恥ずかしい」という思いの中には「人は美しくあるべき」という「6」的な価値観が存在する。
「自分だけ周りと違うから恥ずかしい」という思いの中には「みんな均しく同じであるべき」という「6」的な価値観が存在する。
だから僕は「6」に「恥を感じる」の意を与えているんだ。
愛の有償無償 (2014.5.22 0:33)
「6」の愛はいわゆる無償の愛に近いけれど、逆数の「3」が負で働く場合は「周囲に無償の愛を施している自分を褒め称えて欲しい」という有償性を求めてしまう。
「9」の愛は有償無償に囚われない言わば「愛を愛する」という愛だが、時にこれは逆数「0」へと反転し愛の意義を見失うこともある。
「創造」の仕組み (2014.5.21 23:28)
僕は「創造」の意を「1」ではなく「3」に与えているけど、「1」はあくまで創造する主であり創造という行為そのものではないから。
創造の主たる「1」が次の「2」の如く創造する物をイメージしたり、創造する場を見定めたりすることで、初めて「3」たる創造物の表出が可能となるんだ。
「本物」とは? (2014.5.21 22:26)
本物を凌駕するようなクオリティの偽物が出てきたら、本物は果たして本物で居続けられるのだろうか。
何せ「本物」という言葉には「オリジナル」の意と「ハイクオリティ」の意、両方が込められていたりするからなぁ。
しかもその両義がごちゃ混ぜになっていたりもするから実にややこしい。
嫉妬心と「8」 (2014.5.21 22:06)
自分が持っていないものを相手が持っていて、しかもそれが簡単には手に入らない場合、そして自分が持っているものを相手に奪われたと思い込む場合などにいわゆる「嫉妬心」というものが湧き上がってくるね。
つまり「嫉妬心」とは不健全な「8(支配欲・コントロール欲)」の増大という感じかも。
「9」から入ろう (2014.5.21 21:58)
集団の中にうまく入り込めず悩んでいる場合、その集団の中に奇数偶数の両イメージを併せ持った「9」的な人を介することでうまいこと中に入り込めるケースもあるんだね。
どんな人とも同じように分け隔てなく接する人であり、天然ともつかみどころが無いとも捉えられる人、それが「9」的な人。
「5」を騙る「4」 (2014.5.21 15:24)
普段ネットでは反社会的・反常識的・反伝統的・反道徳的な「5」的発言ばかりしているけれど、その実本当はビビりで大したことをしでかす勇気が無かったりする「4」とは僕のことです。
放送事故大学 (2014.5.21 13:04)
僕のフォロワーさんとか身の回りにいる英知を結集して「放送事故大学」でも開校しようかな。
ピー音が入りまくるようなトンがった講師陣が売りです。
ちなみに僕は数秘術の講師として「くたばれ!マスターナンバー論」と「森羅万象テキトーこじつけ学」と「丁半コロコロ占い」を受け持ちます。
信仰の対象 (2014.5.21 12:10)
偶数の「信仰」。
「2」は対象の姿形が見えずとも、強固に繋がり信じ抜く。
「4」は偶像や経典など姿形が明確に見え、触れられるものを信じる。
「6」は神々しさや愛などの美しさを求め、その美を信じ高揚する。
「8」は神話や理論体系、教団等の壮大さを価値とし、その威を信じる。
それぞれの「いいね!」 (2014.5.21 11:15)
それぞれの「いいね!」
1:「見た」
2:「最高です!」
3:「いい!イイ!ブフォw」
4:「可」
5:「(どーでも)いいね!」
6:「賛同ならコメントを」
7:「それホント?」
8:「僕のも「いいね!」してね!」
9:「(´Д`)(顔文字)」
0:「×(ブラウザ閉じる)」
五感で証す (2014.5.21 9:44)
「自らの五感でその存在を証す」というのは科学的証明とは対極にある方法だけど、それは方法論の違いなだけであって「非科学非科学ゥゥ!」てな感じであざ笑うことはできないよね。
霊感然り、放射線の健康被害然り。
両極端な芸術家 (2014.5.21 7:49)
ありのままを生み出し続ける「3」と完璧なまでに美しく整える「6」。
大量に作品を生み出すけれど、粗製濫造の感が否めない「3」オンリーの芸術家。
出来上がった作品に満足せず作っては壊しを繰り返し、結果作品が世に出ない「6」オンリーの芸術家。
「3」も「6」もほどほどに。
待ちの意識 (2014.5.21 7:34)
ある意味で「4」の正当化とは、「動かない」を「動けない」に脳内で書き換えるということなのかもね。
本当は動きたいし動かなければいけないことは重々承知しているんだけど、その反面で自らがわざわざ動かなくても周りの方が動いてくれるかもという「待ちの意識」が大いに足を引っ張るんだ。
「4」という箱 (2014.5.21 7:25)
僕はどうも「4」だけに一旦何かしらの形を作り上げるとそれに安心してしまい、自らという小さな小さな箱の中で小満足してしまう。
それを変えていくべく隣の「5」へ進み箱を壊せばむしろ箱の大切さを痛感し、もう一方の「3」へ進み箱から出せばむしろ箱にしまい込むことの大切さを痛感する。
サイコパス騙り (2014.5.21 0:30)
遠隔操作ウイルス事件で自らが真犯人であると認めた片山祐輔被告。
生年月日不明のため姓名数を出してみたら「4」。
自らを「サイコパス」であると語ったとのことだが、単に逆数「5」的な破壊性に憧れただけの「サイコパス騙り」に聞こえなくもない。
保身と正直、「4」がどちらに出るか。
普通か特別か (2014.5.20 23:41)
「もっと普通にしてなきゃいけないし、明らかに他の人とは違う鋭敏さも人前では出さないようにしないと…」という「4」の呪縛。
「そんなあなたはもっと『特別』であっていいし、その鋭敏さを活かせる環境や認め受け入れてくれる人々の中で生きていこう!」という「7」の解放。
権利と義務の平行線 (2014.5.20 22:02)
「1」の主張:「こんなん納得いきません!我々の権利をいったい何だと思ってるんですか!?権利が保証されてこその義務ですよ!」
「8」の主張:「権利だって!?やるべきこともせずに権利ばかり主張するなよ!義務を果たしてこその権利だろうが!」
「1」と「8」の逆数平行線。
四機能と動静 (2014.5.19 20:39)
直観を激しく動かす「1」と抑え鎮める「8」。
感情を激しく動かす「3」と抑え鎮める「6」。
感覚を激しく動かす「5」と抑え鎮める「4」。
思考を激しく動かす「7」と抑え鎮める「2」。
全てを遍く生かす「9」と全てを消し去る「0」。
「有名人」という偏り (2014.5.19 17:06)
「この星(数)の有名人の多くは未婚or離婚している」というデータのまとまりがあった場合、「有名人」であるという事実そのものが未婚率や離婚率を引き上げる要因となっている可能性は否めないよなぁ。
つまり「一般人」側のデータ(それも大量に)も欲しいな、ということで。
さようなら占い (2014.5.18 12:03)
「数秘術」に触れれば触れるほど、こねくり回せばこねくり回すほど、「占い」からどんどんと離れていく。実にめでたい。
かと言って、ピュタゴラス時代のそれに戻るわけでもないけど。
どうやら「数秘術」を思想ツールとして再構築しようとしている自分がいるようだ。実にめでたい。
表現の三様 (2014.5.18 11:55)
「3」は行為としての「表現」であり、それ自体を楽しむ。
「6」は成果としての「表現」であり、それ自体を愛しむ。
「9」は両者が合わさった全体としての「表現」であり、それ自体を味わう。
ヒトの強み (2014.5.18 11:35)
数字や図形や概念など本来何の力も外部に及ぼさないモノから、自らの意志を強化し得る力を引っ張り出せるのが、ヒトの持つ最大の強みなんだろうね。
責任転嫁 (2014.5.18 0:31)
「やらない」を「やれない」に変えてしまっている人は多いよなぁ。
一文字変えるだけで責任転嫁の出来上がり。
非人道的 (2014.5.17 23:46)
「非人道的」な何かが存在するのは「人道的」という枠組みがあるから。
そしてその枠組みを綺麗に調えれば調えるほど「非人道的」な何かは更に数を増していく。
「6」的な考えの人は自らの美学や倫理観によって、かえって「非人道的」な何かを増やすこともある。
所変われば人道も変わる。
「術」と「学」 (2014.5.17 23:20)
個から個へ、その技を以って伝え、そして深まっていく「術(アート)」は奇数的な響きがする。
衆の中で蓄積され調えられ、そして広められていく「学(サイエンス)」は偶数的な響きがする。
数秘術と数秘学。
どちらにしようか、混ぜようか。
疑うために信じる (2014.5.17 22:03)
何かを疑い検証を試みるという「7」的行為を行う際、その主体(法則理論・手段)に対しては逆数の「2」の如く全幅の信頼を置く必要があるね。
そうでないと検証過程すら疑う対象になっちゃう。
対象の深部まで潜り込み真実を探し求める「7」のダイバーには「2」という命綱が欠かせないんだ。
スピリチュアルと魔術 (2014.5.17 21:29)
受け容れるスピリチュアルは「2」で、掘り下げる魔術は「7」。
何となくこじつけてみた。
孤独を誇れ (2014.5.17 19:29)
自然数(0を除く)の内で唯一、素数でも合成数でもない「1」の孤独。
1〜9の内で唯一、全円(360°)を割り切ることのできない「7」の孤独。
独りで外なる世界を開拓する「1」。
独りで内なる世界を探究する「7」。
どちらも奇数(動的)として、独りを恐れず誇り高く突き進め。
「2」と「7」の両輪 (2014.5.17 13:02一部改変)
「疑う(7)」とはすなわち「検証する」ということ。
様々な情報を鵜呑みにするのではなくその都度その都度自らの知性を活かし、本当に信ずるべきものなのかどうかを確かめるという行為。
「信じる(2)」と「疑う(7)」の両輪が共に回ってこそ本当の知性が身に付くだろう。
偶然でも、必然でも (2014.5.17 12:20一部改変)
むしろ嫌いと感じる数だからこそ多く見かけてしまう(他の数は意識の外に消える)ことは多い。
それらの現象を偶然と考えて捨てるのも、必然と捉えて自分へのメッセージとして活かすのも自由なんだ。
被害妄想 (2014.5.17 11:00)
他人への強い猜疑心から生まれるのが「被害妄想」だけど、これって疑うという「7」的な行為によって生まれ出た妄想的概念を「2」的に信じ受け入れ、そして自らに強く結び付けることを意味しているんだよね。
つまり疑うこと(7)と信じること(2)、両者の負の融合なんだ。
「7」を「1」に繋げる (2014.5.17 10:10一部改変)
頑張ることをやめて静かになるとますます深々と考えてしまうのが「7」だったりする。
「7」をとことん極めると一気に反転して、事態をただただ観察するだけの「2」が訪れたりもする。
まずは「7」という内なる思考の歯車を「1」という実行の歯車に繋げてみよう。
「考えない」と「考える」 (2014.5.17 9:46)
「考えない」を考えるのが「2」。
「考える」を考えるのが「7」。
それが「2(動かぬ風)」と「7(動く風)」の違いだね。
埋もれるか、離れるか (2014.5.16 22:03)
「4」は自らと現状とを固着させ、不可分のものとしてしまい、そのことで苦しむケースも多い。
そしてそんな状態から逃れるため、自らの意識を上へと昇らせ、現状と固着した自らをも俯瞰する「5」へと変わることがある。
感覚に埋もれ固まる「4」と感覚からの遊離を果たす「5」の違いだ。
見ても見なくても (2014.5.16 0:08)
先程ツイッターにて今日が満月であることを知ったよ。
空を見ても見なくても、ヒトはそれなりに生きていける。
姿形を日々変える月に怯えることなく過ごせるなんて、実に現代は素晴らしい。
憲法9条 (2014.5.15 22:16)
憲法9条は「9」だけあって、玉虫色に曖昧にぼやかされて解釈されるんだなぁ、という独り言。
オーバーな「変化」 (2014.5.15 22:10)
「4」の人が既存の何かを壊そうとする際は逆数の「5」がオーバーとなり過剰破壊に繋がるケースがあったりするね。
「長らく守り続いてきたもの(4)を壊して新しくする(5)」ことへの意識が強過ぎてしまうんだ。
基本数「4」の安倍首相を見ていて、より痛感するよ。
失望か絶望か (2014.5.15 6:51)
「制限」に失望させられるケースは多いと思うけど、かと言って「無制限」となったら絶望するケースが多くなるんじゃなかろうか。
「制限」という促進剤 (2014.5.15 1:34)
字数制限のない文章が書けなくなって久しいけど、字数制限のあるツイッターでは今も盛んに数秘術ツイートに勤しんでいる。
「4(制限)」は「3(表現)」を導き出す促進剤となるんだね。
ホスピタリティ (2014.5.15 1:07)
「2」のホスピタリティは一人の人間に対して作用する。
「6」のホスピタリティは一人の人間のみならず、更にその向こう側に存在し得る人間に対しても作用する。
他者のみを見つめる「2」と、他者と関わる他者をも見据える「6」、それぞれのホスピタリティの違いだ。
オセロゲーム (2014.5.14 22:36)
自分が「うつろ(空ろ・虚ろ)」であることに苦しむ「0」的な人は多いと思う。
でも「うつろ」だからこそ、何でも好きなものを自由に入れることができる。
きっかけを与えられた「0」はすぐに逆数「9(満ちる)」へと反転していけるはずだ。
人生というオセロゲームを楽しもう。
ガンダムUC (2014.5.14 22:24)
ガンダムUCを観てて感じたけど、アムロとバナージは「1(生きる力・衝動)」、シャアとフロンタルは「8(統べる力・制御)」という対比に見えるな。
文化は「分化」 (2014.5.14 17:03)
我が国において「数秘術」は少しずつだけど着実に根付き始めているようだね。
一般的なチャートリーディングもあれば、僕の逆数秘術のように独自手法も存在する。
一つのカテゴリがその内部にて細分化されていくことそのものが「拡がりとしての文化」なんだろうな。
文化は「分化」なんだ。
影響力という満足 (2014.5.14 16:21)
コントロールの意を持つ「8」の人は、自らの存在が相手に多大なる影響を与えているという事実に満足することが多かったりする。
これは逆数に「8」を持つ「1」の人にも当てはまるけど、相手に影響を与えているという事実そのものを自らを縛る鎖と捉えてしまい激しい嫌悪感を覚えることも多い。
いいわけ (2014.5.14 12:21)
占い師の弁明
・吉事が当たった→こうなることは初めから分かっていたわ
・凶事が当たった→こうなることは初めから分かっていたわ
・凶事が外れた→あなたの努力で凶事を退けることができたのよ
・吉事が外れた→あなたが何もせず漫然と吉事到来を待つから来るものも来なくなったのよ
「1」の兵、「8」の将 (2014.5.14 0:01)
「1」の兵曰く「戦わぬ将は要らぬ」
「8」の将曰く「従わぬ兵は要らぬ」
「3」で人生を拓こう (2014.5.13 21:15)
「6(慎ましく調える)」的な考え方の持ち主は「これって話すとただの自慢にしか聞こえないかな…」とか「こんなの見せても恥ずかしいだけ…」などというように「3(ありのままを曝け出す)」的な行為にブレーキを掛けやすい。
でもね、意識して「3」することで人生が拓けていくかもよ!
「バカ」という言葉 (2014.5.13 18:34)
「バカ」という表現は他よりも劣ったものを蔑むためにも用いられるし、逆に他よりも優れた(他を逸脱した、際立った特徴を持つ)ものを褒めるためにも用いられるから面白いよなぁ。
言語とはつくづく相対的だね。
「6」への対処法 (2014.5.12 17:19)
出る杭を打って平らに均そうとする「6」への対処法。
・打たれないように引きこもる(7)
・その場から一目散に逃げ去る(5)
・打たれても平然としている(4)
・モグラ叩きゲーム的に楽しむ(3)
・むしろ平らに均されてしまう(2)
・のらりくらりとやり過ごす(9)
数の性 (2014.5.11 2:00)
常日頃から「変わりたい変わりたい」と思っていても、なんだかんだ理由をつけて結局はその場から動こうとしない「4」。
常日頃から「落ち着きたい落ち着きたい」と思っていても、なんだかんだ理由をつけて結局はバタバタと動き回ってしまう「5」。
数の性だねぇ。
未知か既知か (2014.5.10 18:05)
未知とのバトルを演じる「1」と既知とのバトルを演じる「5」。
生ける屍 (2014.5.10 16:10)
本当はもっともっと成功したいのにそんな本心をごまかしながら「今が満ちているし、今のままでいいのさ」などと嘯き飄々と生きる人。
「1(欲望)」を消して「9(無欲)」に生きるのは「1」が強過ぎるが故の苦しみには効果的だけど、「9」が強過ぎれば今度は「生ける屍」ともなりかねないね。
「仕組み」の説明 (2014.5.10 14:27)
占いで「○○の人は△△しがち」と書かれるケースは多いけど、それだけじゃなくてそのような行動をなぜ起こすのかという「仕組み」についての言及があるといいよね。
そういう意味で占いはただの予測だけではなく、人間心理が行動に及ぼす仕組みを補足解説し得る存在にシフトしているんだろうな。
宗教の三類型 (2014.5.10 1:05)
キリスト教の救済論におけるアラン・レイスの三類型。
特定の宗教を絶対視する排他主義は「1」。
他宗教の存在は認めるも自宗教の優越性を放棄しない包括主義は「5」。
あらゆる宗教の存在を認めて互いに共存していく多元主義は「9」。
このように数とこじつけてみてもいいだろう。
「8」と「9」の救い (2014.5.10 0:54)
遍く命を人為の限りを尽くして、半ば強引に拾い上げようとするのが「8」的な救い。
遍く命を同じく拾い上げようとするが、なるべく自然の摂理に委ねようとするのが「9」的な救い。
死を拒む「8」と死を容れる「9」。
でこぼこ (2014.5.9 17:51)
でこぼこを楽しむ「3」。
でこぼこを均す「6」。
でこぼこを気にしない「9」。
「正義」と「悪」の作り合い (2014.5.9 12:41)
「悪」が「正義」を作るけど、「正義」が「悪」を作ることも多いね。
それぞれがそれぞれの存在を担保しているんだ。
「正義」という大剣 (2014.5.9 11:49)
思い切り振りかぶった「正義」という名の大剣。
威力は絶大なんだけど、振りかぶった際に背後にいる味方をもぶった斬ることがよくあるね。
でも当の本人はそんな大剣を振り回す自分に自惚れているからとても厄介だよ。
「正義」を振り回すつもりが「正義」に振り回されているんだね。
「4」と「5」のスタイル (2014.5.9 9:01)
「自分」を保つためにあえて鈍重を貫き通し、単一な対応をするのが「4」的なスタイル。
それとは逆にあらゆるものに敏捷かつ反射的に反応し、そうすることで自らの中立性を保とうとするのが「5」的なスタイル。
動かぬ「4」と動く「5」の違いだね。
ニュース (2014.5.9 8:44)
ニュースを見るか、ニュースになるか。
えらい違いだ。
鞭毛 (2014.5.9 8:30)
精子などにある鞭毛。
自らが泳ぐ際に推進力を生み出す器官だけど、これって正に「1」だよなぁ。
そんな「1」な鞭毛をフルに動かして「9」の大海を泳いでいくんだ。
イモ欽トリオ (2014.5.9 8:12)
良い子「照応」
悪い子「こじつけ」
普通の子「関連付け」
双子の逆数兄弟 (2014.5.8 19:03)
全てのものに意味を見出し、愛を見つける博愛の「9」。
全てのものに意味を見出さず、愛を見つけられない虚無の「0」。
双子の逆数兄弟でもあり、一つ身の裏表でもある。
777の書 (2014.5.8 17:44)
基本数7のクロウリーが著した「777の書」だけど、タイトルだけ見ると「7」が3つ(7×3=21→「3」)あるから《深奥(7)の開陳(3)》って感じだね。
「4」と「7」 (2014.5.8 16:22)
「4(鈍麻・普遍)」に住まう人々は「7(鋭敏・特殊)」に住まう人々を変わり者と見、「7」に住まう人々は「4」に住まう人々を鈍き者と見る。
「4」は「7」に憧れ、そして弾き除ける。
「7」は「4」に安らぎ、そして侮り蔑む。
永久機関 (2014.5.7 15:35)
占い師を占った占い師がまた別の占い師に占ってもらうという永久機関。
頑張るな! (2014.5.6 22:23)
僕からの不埒なエール。
「頑張るな!死ぬぞ!」
明確が生む曖昧 (2014.5.6 11:08)
何かをただただ純粋に眺めている(2)間は「自分」というものが朧げとなり、ついには忘我(9)の境地へと近付いていく。
何かとがっしり繋がった(2)時、繋いだ主体の意識は主体から遠ざかり薄くなっていく(9)。
「2」という明確な線が「9」という曖昧を生み出し得るという対数性だね。
六割で (2014.5.6 2:50)
僕の持論。
「みんな六割幸せになろう」
無理なくみんなほどほどに。
「逆数秘術」のススメ (2014.5.5 23:47)
僕の「逆数秘術」をオリジナルのまま使ってもいいんだけど、既存の数秘術体系を補う形で取り入れてみても面白いよ。
数の象意の世界が大きく広がり、より様々な物語を紡ぐことができると思うから。
これはバリエッタ以降の現代数秘術における数の象意をベースにしているからこそできる芸当。
子供の「1」と「8」 (2014.5.5 22:35一部改変)
大人たちの「8(コントロール)」に抗う子供たちの「1(自我)」もあるし、逆に幼い頃より大人の目ばかり気にして「8(自制・我慢)」を徹底させる子供たちも見受けられるね。
こどもの日 (2014.5.5 22:20)
そういえば今日5月5日(5+5→10→「1」)はこどもの日でしたね。
子供が衝動の赴くまま突き進んでも(1)、指図に従わず反抗(5)しても、今日だけはどうか大目に見てやってください。
年に一度のこどもの日ですから。
「鈍感力」 (2014.5.5 19:10)
基本数5の渡辺淳一氏が書いた「鈍感力」。
「5」の果てにたどり着いた逆数「4」の究極形が正に「鈍感力」なのかもね。
うかつだった (2014.5.5 9:46)
「5月5日の午前5時に震度5弱の地震(破壊・5)が起きた!」とつぶやくことを忘れていたとは。
数秘術研究者として実に情けない。
対向星座こじつけ (2014.5.4 23:40他、一部改変)
対向星座こじつけ。
牡羊の蹄の一乗せが揺れ動く天秤の軽重を決する。
牡牛の歩みの地響きが獲物を定めた蠍を諦めさせる。
双子それぞれの助言が矢を放つ射手に冷静さを与える。
水辺を這う蟹を見て山羊は己の可能性を思い出す。
獅子の一吼えによって水瓶を持った少年は我に返る。
乙女の一瞥を投げられた魚たちは食される覚悟を決める。
「8」の苦、「9」の苦 (2014.5.4 14:22)
常に不足を感じ、がむしゃらに何かを得ようとするのが「8」の苦だけど、いざ充満すると今までのバイタリティが消え、全てがどうでもよくなる「9」の苦が襲ってきたりもするから実に人生は難しい。
広く深く (2014.5.4 0:50)
広く「知」を関連付ける「2」。
深く「知」を掘り下げる「7」。
どっちも大切なんだろうな。
何とかなるって (2014.5.3 23:19)
たとえば掃除をする日が「5」の日なら部屋を一新させるとこじつけ、「6」の日なら徹底して片付けるとこじつけ、「9」の日なら断捨離断捨離ィィ!とこじつけ、「8」の日なら買った物をしまい込むスペースを空けるとこじつける。
大丈夫。何とでもこじつけられるって。
人と地 (2014.5.3 20:15)
人は地を食い、地は人を食う。
オンプレミス (2014.5.3 17:47)
ハードウェアやソフトウェアを自ら調達し運用することを「オンプレミス(on premise)」といい、昨今流行りの「クラウドコンピューティング」の対義語となっているらしい。
数でこじつけるなら、前者は「8」で後者は「9」って感じだね。
衝動買い (2014.5.3 17:33)
自らの衝動(1)に従ってつい購入(獲得・8)してしまう行為が「衝動買い」。
この行為は何かを得る(8)ことによって自らの価値を高めようとする(1)ものとも言えるし、自らの原初的欲求(1)を消費(8)という代替行為で満たそうとするものとも言える。
目的でもあり手段でもあるんだ。
「しるし」の検証 (2014.5.3 10:53)
もし何かの「しるし」とアクシデント発生とを結び付けようとするならば、必要となるのはその「しるし」が無い時には果たしてどうなのかという検証なんだろうね。
事故と水星逆行 (2014.5.3 10:47)
2014年の水星逆行期間は2月7日〜28日、6月7日〜7月1日、10月5日〜26日とのこと。
韓国のフェリー沈没事故と地下鉄事故、そしてニューヨークでの地下鉄事故は水星順行時での発生。
これがもし逆行時の発生であれば見事水星逆行のせいにされていたかもしれないね。
辞書作り (2014.5.3 0:12)
国語辞書を作る際、新しい語を見掛けたらその都度「語釈」を書き溜めていくという作業。
僕の日々の数秘術ツイートもたぶんそんな感じ。
数の象意を柔らかく解したり、対称性を与えてわかりやすくしたりする作業。
思い付いたら忘れないうちにすぐつぶやく。ある意味「数秘術辞書」作りだ。
「3」と「6」の逆数訓 (2014.5.2 23:47)
社会で自分を活かす(6)ことができなくなったら、これからは人目を気にせずただただ自分のために人生を謳歌(3)していけばいい。
ただ自らを喜ばせる(3)ことに馴れたり飽きてしまったら、自らの存在を社会に活かす奉仕(6)の喜びに目覚めるといい。
これが「3」と「6」の逆数訓。
活用 (2014.5.2 23:15)
社会で自分が活用されることに喜びを感じるのが「6」。
自分の喜びのためフルに社会を活用するのが「3」。
「8」な言葉 (2014.5.1 18:43)
終戦の際「耐え難きを耐え、忍び難きを忍び」と玉音放送で述べたのは基本数8の昭和天皇だけど、この文言そのものが正に「8」だよなぁ。
何もしない「贅沢」 (2014.5.1 14:24)
もし「贅沢」という語を「限りあるものを惜しげも無く使うこと」と捉えるならば、何もせずにボーッとする行為は最高の贅沢になるね。
限りある人生における貴重な時間を非生産的にただただ無駄に消費しているんだもの。
でもね、そんな贅沢も人生には必要なんだよ。