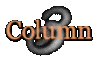
数秘術関連等ツイート(2014年3月分)
お笑いBIG3 (2014.3.31 20:52)
独自のしゃべり道を築いた基本数1の明石家さんま。
独自の司会スタイルを築いた基本数4のタモリ。
独自の軍団を築いた基本数4のビートたけし。
1も4も「自のライン」の数だけど、他に阿らず自らのスタイルを築き上げ、そしてそれを貫き続けるBIG3は偉大だよなぁ。
バケモノ (2014.3.31 17:18)
社会は個人の集合体ではあるけれど、それはもう人の姿を失ったバケモノなんだよなぁ。
社会勝手 (2014.3.31 13:01追記有り)
自分勝手よりも「社会勝手」の方が問題だろ。
なお「社会勝手」とは集団性を守ろうとする保守的な思想の暴走による個人の抑圧を指す言葉として用いている。
もっと敵を作ろう (2014.3.31 12:54)
まんべんなく味方を作ろうとするよりも、恐れずに敵を作っていく方を選ぶな。
そうすりゃ敵の敵が強力な味方となるだろうから。
お絵描き (2014.3.31 0:22一部改変)
数という絵の具と法則という絵筆で自由自在に人生を描いていこう。
「逆」を作ろう (2014.3.30 23:25)
「何か新しいものを生み出したい」と考えた際、一番手っ取り早いのは既存のものの「逆」を作ることだと思う。
そしてその「逆」はたった一つだけではなく、いくらでも存在し得る。
僕の数こじつけのようにね。
クレンジングオイル (2014.3.30 23:10)
「怒り」は幾重にも塗り重ねた心のメイクを一瞬にして落とす最強のクレンジングオイルだね。
性格と経験 (2014.3.30 22:01)
「性格が経験を作る」のか、はたまた「経験が性格を作る」のか。
まぁどっちもあるよね。
馬鹿を見よう (2014.3.30 12:17)
「正直者は馬鹿を見る」という言葉があり、そういう事例は多いよなぁと思いつつも「馬鹿を見てもいいから正直者でいたい」という欲求も自己責任の元で許してあげてもいい気がするなぁ。
強大なバックボーン (2014.3.30 10:28)
強気な人や弱気な人という表現があるけれど、それはそういった性格というよりも「強大なバックボーン」の有無の違いな気がする。
もちろん自分以外の何者かの存在やその権威も強大なバックボーンとなるけれど、自分という存在やそれに対する自尊の念も強大なバックボーンとなり得るよね。
囚われる (2014.3.29 21:25)
1・4・7の人は自らという存在や主観に囚われる。
2・5・8の人は他者という存在や客観に囚われる。
3・6・9の人は愛することや愛されることに囚われる。
人生とは「囚われる」ということ。
ネオ数秘と逆数秘術 (2014.3.29 21:02)
DASOさんの「ネオ数秘」は気になるなぁ。
「3」の人が編み出した「ネオ数秘」と、「4」の僕が編み出した「逆数秘術」。
あくまで謳い文句からの印象だけど、前者は「3」、後者は「4」って感じが確かにするよなぁ。
枠から出て遊び楽しむか、枠に入れて秩序立てるか。
「4」がキレる理由 (2014.3.29 19:39他)
4の人がキレる理由を考えてみたけれど数の象意に基づくのであれば、「自己領域を侵された時」や「ルーティンを妨げられた時」、はたまた「ルール違反を見かけた時」など要は「自身が勝手に定めた枠に収まらない事態が発生した場合」というのが一番こじつけやすいキレる理由だね。
じゃあ4の人と6の人はキレる理由が似てるんじゃないの?という声もあるだろうけど、4の枠と6の枠の最大の違いは6の枠はそれ自身に強い美意識や倫理観が根付いているということ。
4の枠は主観に基づくただの枠組みに過ぎず、一方6の枠は愛が根底にあるため強烈な正義性を持ってたりもする。
性甘説 (2014.3.29 12:10)
人間って性善でも性悪でもなく「性甘」だと思うな。自分に甘いの。
そしてそんな自分の甘さを徹底して否定されたり矯正されたりすると、反転して他罰的になったり自罰的になったりする。
ズルもしたいしサボってみたいし、甘めの設定で人生を生きていきたいという願望は「悪」とは異なるよなぁ。
前進か反発か (2014.3.28 19:23)
遮る遮らない関係無く一直線に進み続けるのが「1」。
遮られることで初めて爆発的に反発し始めるのが「5」。
獣性の扱い方 (2014.3.27 23:20)
誰もが持っている「1(獣性)」。
ムチと檻で徹底的にコントロールする(逆数8)か。
お腹を満たすことで獣性を薄める(補数9)か。
むしろその獣性を闘犬や猟犬のように別方向で活かす(対数1)か。
やり過ぎない程度に、お好きな方法をどうぞ。
消えた「1」の行方 (2014.3.27 20:33)
疲れた身体を背もたれに預け、足をこたつの中に伸ばしながらテレビをボケーっと観ていると、なんだか世界に奥行きがなくなっているような感じになるなぁ。
併せてツイッターをやってるとなおさらだね。
3次元から2次元へ。
消えた「1」はどこへ行ったのやら。
消極的な希死 (2014.3.26 19:31)
「積極的に死のうというわけではないけれど、まぁ死んだら死んだで別にいいや」病に対してどんな数をこじつけようかな。
なんか「9」でもあり「0」でもあるな。
二つの「中立」 (2014.3.24 10:14)
「5」の中立は武装中立。
支配せず支配されず、主権を脅かす存在に対しては徹底的に抗う。
「9」の中立は非武装中立。
硬軟併せた外交を駆使し、一時的な主権の侵害があっても柳の如くやり過ごすことで別方法での解決を図る。
対称性 (2014.3.23 13:15)
僕が全ての数に対称性を与えているように、全ての星座や惑星に対称性を与えている人ってたぶんいるんだろうな。
COLOR (2014.3.22 18:04)
ふと「COLOR」という文字が目に入ったからゲマトリアしてみたら3+6+3+6+9=27(3×3×3)→9となった。
3・6・9の愛のラインで彩られ、奇数も偶数も、動も静も、混沌も秩序も、皆が混じり合うことで無限の「COLOR」が顔を出す。
人々を豊かにする「COLOR」。
信じ過ぎる「7」 (2014.3.22 14:00)
7の人とか7的な人が人生において失敗する要因だけど、逆数2的な「人を信じすぎること」というのが大きかったりするね。
腐れ縁を切れなかったり、借金の連帯保証人になったり、信じた挙句おもいっきり裏切られたり、などなど。
それらの経験が自らの「7(検証・洞察・孤高)」を鍛えるんだ。
「1」は「2」を経て「3」になる (2014.3.22 11:39)
「1」というありのままは「2」という他者からの視線を意識することで、ごく自然に「3」という誇大表現やオーバーアクションを行ってしまう。
つまり「1」という自尊をより大きく他者にアピールしようとするのが「3」という露出的アクションなのだ。
笑っていいとも (2014.3.21 15:14)
今日は2014年3月21日、則ち「4」の日。
そんな「4」の日に基本数「4」のタモリが司会の番組に同じく基本数「4」の現役首相がゲスト出演したのか。
こりゃ「4(安定)」の逆数である「5(激変)」の前触れなんかいのぉ。
「3」の季節 (2014.3.20 21:24)
明日は春分の日。
僕の考案した「一年を9×9分割する暦」だと春分を挟む3/19〜22は「2-9」となる。
つまり春分を過ぎたら「3」に入るということ。
草木や花が萌え出づる、蓄えてきたものを放出せんとする「3」の季節だ。
「3」を教える人々 (2014.3.20 18:38)
ダウン症の人が持つ豊かな表現力についてテレビで取り上げていた。
21(→3)番染色体が3本あるために発現するダウン症。
もしかしたら人々に「3(表現・内側のものを素直に表に出す)」の素晴らしさを教えてくれているのかもしれないね。
後出しこじつけ (2014.3.20 14:31)
3/2にウクライナ情勢をダイスで観てみたら「5」「9」「0」と出たけれど、僕はズルい人間だから後出しで実際の情勢にこじつけてみることにしよう。
「5(クリミアの帰属変更)」
「9(ぼんやりとした曖昧戦争)」
「0(そして誰も見なかった事にする)」
なんかどっかで見た構図だ。
無用の用 (2014.3.20 8:33)
無駄なく隙間なく張り巡らされた「8(2×2×2)」というネットワーク。
それを円滑に運営し、かつ各構成員がゆとりある心で働き続けるためにも、「9」という冗長性(バックアップを設ける等のシステム上のゆとり)がやはり必要となるんだろうな。
「9」が教える「無用の用」だ。
アリストテレスの「愛」 (2014.3.19 14:51)
アリストテレスは「愛されるべきもの」を「快適なもの」「有用なもの」「善きもの」とに分け、これらについて生じる愛のさまざまな在り方を考察したという。
正に「3(快適なもの)」「6(有用なもの)」「9(善きもの)」の「愛のライン」だね。
明かすか捉えるか (2014.3.19 13:56)
「私はこう明かす」の集合体が科学だとしたら、「私はこう捉える」の集合体が哲学なのかも、などと考えている。
表裏と内外の存在 (2014.3.19 13:43)
奇数と偶数両方の性質を持つ「9」はそれそのものがぼんやりとした全体であるから、表も裏もわからず、内も外もわからない。けどわからないだけで存在はできる。
一方、奇数と偶数両方の性質を一切持ち合わせない「0」はそれそのものが虚無であるから、表も裏も存在できず、内も外も存在できない。
「2」と「9」が教える「リンク」 (2014.3.19 12:59)
明確な線で繋がったり分けたりする「2」と、曖昧な線引きのまま自他を混交させる「9」という対数関係。
相手にピントをはっきりと合わせる「2」と、ぼやけた視野のままでいる「9」という対数関係。
互いを足した数字根が「2」となる対数が教えてくれるのは、程良い自他の「リンク」。
奇数・偶数の捉え方 (2014.3.19 12:46)
混沌極まる状況下において、それを自由と感じるのが奇数的な人であり、それを不安と感じるのが偶数的な人。
秩序立った状況下において、それを息苦しく感じるのが奇数的な人であり、それを心地良く感じるのが偶数的な人。
「凶」というゴミ箱 (2014.3.19 1:01)
なんか「凶」の字が禍々しい人や物を入れるゴミ箱に見えてきた。
人々はそれらをよくよく調べもせずに「凶」というゴミ箱に入れ、社会から取り除いていき、美しくなったと嘯く。
「凶」というゴミ箱にただ入れただけなのに、それで禍々しさの理由証明を果たしたなどと大いなる勘違いをする。
病は気から (2014.3.18 22:19)
「病は気から」という言葉を生み出した人は、その言葉がむしろ現代人に苦しみを与えているという事実を知ったら果たしてどう思うのだろうか。
次元で考える (2014.3.18 21:43)
0次元は点であり、2^0=「1」
1次元は線であり、2^1=「2」
2次元は平面であり、2^2=「4」
3次元は立体であり、2^3=「8」
このように表記することで、それぞれの数と図形とがイメージしやすくなると思う。
「守る」の需要と供給 (2014.3.18 20:43)
「守りたい」と「守られたい」が一致しないケースは割と見られるね。
一方的な「守りたい」が「守られたくない」側の自負に傷を付けることもあるし、「守りたくない」と「守られたい」の関係も割と悲劇を生みがち。
「守りたくない」と「守られたくない」ならサバサバしてていいかも。
逆数0の症状 (2014.3.18 18:10)
基本数9の人や9的な人が自分探しに疲れ果て、ある日突然逆数0に襲われた時の症状は以下の通り。
・猛烈なリセット願望
・無感情、無関心、無反応、無行動
・不可視化能力発動(見えていても見えなくなる)
・透明なものへの憧れ
・自分という存在の(消極的)消滅願望
・時間が動かなくなる
7の年 (2014.3.18 17:48一部改変)
2014年という7の年は正に「7(検証)」がテーマであり、それを想起させる出来事として逆数である「2(突然の提携と離別)」が起こりやすい流れではある。
ここで肝心なのは「どうして結ばれているのか?」「なぜ離れるべきなのか?」ということについてしっかりと検証し尽すという態度だ。
愛を貸す (2014.3.18 16:55)
愛を貸す人は多いけど、与える人は少ないね。
愛を貸すということは、その分の愛(プラス利子)を返してもらうことが前提となるけど、もし相手が愛を返してくれなければ落胆し激怒してしまう。
まぁ相手から愛を求めたならともかく、中には押し貸しの愛もあるから、返せと言われても難しいよね。
矛盾 (2014.3.16 22:58)
矛盾を矛盾のまま己が心中に活かし続けるというのは、正に「9」的な境地だなぁ。
奇数でもあり偶数でもあり、動でもあり静でもあるという「9」。
そしてそんな「9」が一瞬のうちに「0」に反転し、心地よい虚無が訪れる。
やめておこうか (2014.3.16 20:02)
犯罪者や自殺者の数秘術的な統計研究。
昔の僕ならやってただろうけど、今はもうやらない。なぜなら誰も救われないから。
もし自殺者に多い「数」が浮かび上がったとして、その事実は該当者の自殺念慮を刺激するだけだし、こちら側もそんな意識で相手を見てしまうことを避けられないからね。
奇跡という名の偏り (2014.3.16 16:58)
人が奇跡や不可思議に驚き感銘する際、根底にあるのは確率論的思考。
つまり、ありとあらゆる現象は確率論的に発生するべきであり、占める割合や起きる頻度が著しく偏る場合、それらに奇跡や不可思議などの称号を与えるというもの。
でもそれらも確率論の中に含まれるから偏ることだってあるさ。
開き直り (2014.3.16 16:51)
他人の長所をむしろ短所であると貶め、自分の短所をむしろ長所であると嘯くのが、僕の考える「開き直り」。
人生はスイッチバックで (2014.3.16 15:02)
「前進は進化であり、後退は退化である」という捉え方はちと窮屈な気がする。
未練たらしく前を向きながら後退するから退化と捉えがちなのであって、きちんと後ろに振り返って前後を逆として進めばそれは則ち別方向への「進化」に形を変えていく。
スイッチバックで高山を登る要領で進もう。
分けると分けぬ (2014.3.16 14:20)
奇数(1・3・5・7)という動的混沌は「分けられぬもの」。
偶数(2・4・6・8)という静的秩序は「分けられるもの」。
偶奇両有(9)という混沌と秩序の混交は「分けられるし分けられぬもの」。
偶奇無有(0)という虚無は「分けるも分けぬもできぬもの」。
迷いと悩み (2014.3.16 14:05他)
「2」の思考は分けられた幾つかの選択肢の中から最適なものを選ぼうとする「迷い」。
「7」の思考は現在提示されている選択肢以外の最良解を求めようとする「悩み」。
「2」の「迷い」で苦しむ人には提示された選択肢以外の答えが想像できず、「7」の「悩み」で苦しむ人には放って置かれた選択肢の長所が見えてこない。
迷ったら悩もう。悩んだら迷おう。
自由 (2014.3.16 1:18)
ヒトが持つ究極の自由って「遺伝子リレー競争に参加しない自由」だと思うな。
オープンとクローズ (2014.3.16 0:31)
恥になることや都合が悪いことも全て開けっぴろげに打ち明け笑いに変える「3」的なオープン愛。
相手がショックを受けたり落ち込んだりするようなことを話さずに隠し通す「6」的なクローズ愛。
オープンでもクローズでもないどっちつかずの曖昧さで皆を自然に包み込む「9」的なごちゃ混ぜ愛。
大きな一つのもの (2014.3.15 17:34)
マクロコスモスもミクロコスモスもともに大きな一つの「コスモス」であることを「9(境の無い大きなまとまり)」が教えてくれているかのようだ。
愛について (2014.3.15 17:24)
数秘術的に「愛」を捉えると、エロス(性愛)は「3」、フィーリア(隣人愛)は「6」、そしてアガペー(真の愛)は「9」って感じかな。
3(自)<6(他)<9(全)というように対象が広がっていくイメージだね。
紡ぐか、解くか (2014.3.15 16:30)
なんか「自分」や「世界」という存在について考えれば考える(7)ほどに、綴じていた糸が解けてバラバラになる感じがするなぁ。
いっそ感じたままの「自分」や見たままの「世界」を信じて(2)生きていければ、それはそれで収まりがよいのかもね。
糸を紡ぐ(2)か解く(7)か。
厄介な存在 (2014.3.15 15:51)
社会倫理の大切さを説く「6」にとって厄介なのは、その倫理の是非を問い続ける「7」の存在。
組織という幾重もの枠組みの必要性を説く「8」にとって厄介なのは、そんな枠をやすやすと乗り越えてふわりと生きる「9」の存在。
社会人 (2014.3.15 15:45)
「社会人」の対義語を幾つか考えてみる。
未社会人:まだ社会人になっていない人
非社会人:社会人であろうとしない人
反社会人:積極的に社会に抗い続ける人
とりあえず僕は非社会人と反社会人の間くらいかなぁ。
最近の若者論 (2014.3.15 15:02)
「まったく最近の若者ときたら…」などという声は古代から現代に至るまで聞こえなくなったためしは無い。
でもそんな若者を生み出しているのは親や教育などに代表される「大人たち」であるわけだから、つまり上の言葉は「まったく最近の大人たちときたら…」と置き換えることも可能かもね。
教えるべきか否か (2014.3.15 14:13)
属する組織(8)の意に反し、己の正義を信じて英雄的・人道的な活躍をするヒーロー(1)の存在。
果たして我々は「1」になれと教えるべきなのか、はたまた社会維持のため「8」に服するべきと教えるべきなのか。
千年に一度 (2014.3.14 23:46)
「千年に一度」というものを確率論的に捉えるのか、はたまた明日起きてもおかしくないと捉えるのかで抱く危機感は雲泥の差となるね。
欠点の一般化 (2014.3.14 20:10)
なんかイギリスが料理不味い云々というステロタイプって、B型の人って云々というステロタイプと同じような臭いを感じるなぁ。
目立ちかつ分かりやすい汚点(っぽく見えるもの)のみ拾い上げてステロタイプ化し、それをdisってホッとしたいというヒトの心の何か。
786 (2014.3.14 19:04)
イスラム教では786という数が尊ばれているけれど、これはコーランの各章の初めに書かれている「ビスミッ=ラーヒッ=ラフマーニッ=ラヒーム(仁慈遍く慈悲深きアッラーの御名において)」というアラビア語に預言者「ムハンマド」を加え、文字を数字化(要はゲマトリア)したものとのこと。
枠を外そう (2014.3.14 12:01)
幸福というものに一定の「枠」を設けてしまうと、その枠外のものは不幸であると感じやすくなるね。
たとえば「結婚していることが幸福であり、そうでない人生は不幸である」という極端な幸福論とか。
そんな幸福枠なんて無くなればいいのにね。
人生も幸福ももっと自由でいいんだよ。
長続きの秘訣 (2014.3.13 22:34)
「4(固定・維持)」を続けるって本当に難しい。
ヒトってついつい「5(変化・改革)」に走りたがるし、そっちの方がなんだかカッコ良く思えるからね。
小さな「5」を重ねながらも全体としての「4」を崩さないスタイルが長続きの秘訣なのかな。
本当の深み (2014.3.13 11:31)
世の中「インスタントな深み」を求める人が多いけど「本当の深み」はそうやすやすと姿を現さないし触れさせもしないよね。
「本当の深み」は一生をかけて求めたとしてもたどり着けないかもしれない、そのくらいのところにあるものだろうし、そんなストイックな姿勢そのものが「深み」なんだろうな。
合う・合わせる (2014.3.12 22:46)
世の中「自分に合う相手がいい」などと曰う人が多いけど、「相手に自分を合わせていこう」と考える人は果たしてどれだけいるんだろうか。
そしてもう一歩進化して「自分は自分、相手は相手、それぞれ認め合って譲り合って思いやっていこう」と考えられればいいね。
先生という語 (2014.3.12 15:50)
大人になってから使う「先生」って二つあるね。
一つは自らの知識を深め視野を広げるような教えを与えてくれる人に対する敬称として。
もう一つは自らに著しい便宜を図ったり直接的な利益を与えたりする人に対するおべんちゃらとして。
手放し、再び掴む (2014.3.12 14:40)
掴んだ客体に対する強い意識(8)を未練なく手放し(9)、そして掴むという主体にクリアとなった意識を集中させる(1)という流れ。
肉を喰うということ (2014.3.12 12:44)
身体が肉を求めている。
肉汁溢れる肉を、己が血を滾らせる肉を求めている。
そんな肉にナイフやフォークをグサグサ突き刺して、己の攻撃性を存分に発露させてくるとしよう。
生き物は絶えず何かを殺しながら、己を存在させ続ける。
汚いは悪じゃない (2014.3.12 12:16)
自らの心中に蠢く負の感情や汚い言葉たちを「悪いもの」として忌避してばかりいると、いつか自分を殺しちゃうよ。
それらは決して悪者なんかじゃなく、ただの「自然な感情」なんだから。
まずはそれらに善悪をつけず、そのままの存在を認めてあげよう。
それすらも愛すべき自分なのだから。
天秤の2・5・8 (2014.3.12 10:31)
2・5・8は「他のライン」だけど、これらは「天秤による公正な判断」の各機能を表し得る。
2は天秤の皿に相当し、万象を二元化する事で判断可能にする。
5は天秤の支点に相当し、二元化されたもの同士のバランスを勘案する。
8は天秤の目盛に相当し、両者の軽重を計る事で制御下に置く。
再現不可な「奇跡」 (2014.3.11 19:00)
もしかしたら「奇跡」って再現不可なんじゃないかな。
もし再現可能だったら、それはもう科学になっちゃう。
希少性云々の前に再現不可だからこその「奇跡」なんだ。
意識したらアウト (2014.3.11 18:46)
さっきの地震予知とも捉えられるツイートだけど、当然ながら僕に地震予知なんぞできません。
地震の地の字も意識していなかったからあんなツイートができたんであって、予知しようとする意識が働いた時点で外しまくるだけ。
できるのはそんな「なんとなく」を無視しないこと位かな。
思い出す無意識 (2014.3.11 18:30)
3月11日を迎える度、震災当日の午前9:04に呟いたこれを思い出す。
いつもはこんな呟きなんかしないのに、この日に限ってこんなことを書いた。
僕の意識から出た答えは大して当てにならないけれど、無意識のそれは信じるようにしている。
https://twitter.com/gotsuo/status/5998490555387904…
ツイッターはすごい (2014.3.11 18:11)
ツイッターをやっていると「僕はホントに物知らぬアホだよなぁ」などと気付かされることが多いし、「僕よりアホなやつもいっぱいいるなぁ」などと気付かされることも多いし、「この人は物知りだけど人格はう○こだよなぁ」という人に出会うことも多いね。
かく言う僕は物知らぬう○こだけどね。
非黙祷 (2014.3.11 16:14)
「黙祷」とつぶやく行為の非黙祷感。
繋ぐ?繋がぬ? (2014.3.11 10:18)
「繋ぎたくなりゃ繋ぐし、繋ぎたくなけりゃ繋がない!」という3的な愛。
「みんなで繋がろう!一つになろう!それが美徳だ!」という6的な愛。
「繋ぐ?繋がない?そんなんどうでもいいしそれぞれでいいじゃん!」という9的な愛。
お好きな「愛」をどうぞ。
繰り返す阿呆 (2014.3.10 22:25)
「戦争の惨禍を繰り返さないためにも、悲劇は語り継がれなければならない!」という話は彼岸前やお盆あたりによく聞く。
そんな話を聞くたび、第一次世界大戦終戦から第二次世界大戦開戦までたった21年しか経っていなかったという事実を思い出す。
忘れる頭が悪いのか、滾る血が悪いのか。
「傷」を見る見ぬ (2014.3.10 20:24)
明日は東日本大震災から丸三年だけど、僕は今までと同じく地震発生時刻に黙祷もせず、普段通りに過ごす予定。
ある一点の時に刻まれた「傷」への思いは人それぞれ異なるだろうし、その「傷」 への処し方もそれぞれあっていいと思う。
「傷」を見返すもよし、「傷」を見向かぬもまたよし。
「3」と「6」で織り成す社会 (2014.3.10 19:19)
子を産み出す妊婦が「3」ならば、逆数の「6」はその出産を手助けする助産師だね。
「3」だけでは失われる命も多いし、「6」だけでも当然成り立たない。
「3」と「6」がそれぞれにそれぞれの役割を担うことこそが「9」という円なる社会を作り上げていく。
真の大量破壊兵器 (2014.3.10 18:33)
「混じり気なく純粋であることは善であり正しいことである」という思想こそが真の大量破壊兵器。
レイシズム考 (2014.3.10 18:26)
人種主義(レイシズム)による差別と、そんなレイシストを徹底的に断罪排除する行為。
一見真逆に見えるけど、排外主義という点では大差ないように思える。
人がレイシズムに至る背景。
そんなレイシストを排除する心理。
それらの根底にあるのは「分けることで齎される安心」かもしれない。
自己一致 (2014.3.10 17:13)
最近TLにて「自己一致」という言葉を見る。
なんでも「自己一致」とは、自己概念(そうであるべき自分)と自己経験(あるがままの自分)が一致している状態のことを指すらしい。
「8」という自己概念と「1」という自己経験の一致(8+1)、これが「9」という自己一致に繋がるのか。
哲学は「7」 (2014.3.10 16:59)
「哲学に専門があるとすれば、その一つは、固定化し狭量になりがちな専門性というものに疑問を投げかけ、息苦しくなってしまった思考に風を送り、頭を柔軟にすることである(学研刊・New哲学入門より抜粋)」
哲学とは正に「7」というカオスな奇数であり、そして「動く風」そのものなんだ。
絶対値 (2014.3.10 15:10)
小さなマイナスは小さなプラスを生み、大きなマイナスは大きなプラスを生む要因となり得る…などと考えてみると、人生で大事なのはプラスとかマイナスではなくて「絶対値」、つまりゼロというフラットラインからどれだけ離れているのかということなのかな、などと思ってみたりもする。
「6」だらけの観音 (2014.3.10 12:54)
Wikipediaで観音菩薩の項を読んだけど、衆生救済のため「33」の姿に変身すること(三十三間堂はここから)、六観音や六道輪廻の「6」、十五尊観音の「15」、千手観音の「42」本の手…これらの数の数字根(単数変換後の数)は皆「6」となるのが面白いから何かこじつけに使えそうだ。
二つの愚 (2014.3.9 13:15他)
個々人の悪性を所属民族全体にまで投影させる愚。
まぁ特定の民族に対する抽象的嫌悪感を特定の個々人に投影するのも同じく愚だけどね。
「占い」と「5」 (2014.3.9 11:16)
「占」という字は5画。
「5」には自由・変化・人間・俯瞰などの意がある。
当て推量や比較分析などではなく、人間を固定観念から自由にし、人生に建設的な変化を与え、そして全ての物事を俯瞰して捉えられるようにするのが「占い」という行為なのかな…などとこじつけてみた。
「7」の条件 (2014.3.9 0:25)
健全な「7(思索・洞察)」は丁寧な「2(関連付け・観察)」があってこそ。
「2」が疎かになれば、当然「7」も歪んでくる。
課題は「8」 (2014.3.9 0:17)
僕の逆数秘術は「○○は▲▲である」という程度の2的な線を幾つも幾つも呟くことで発展させている。
それを特に整理もせずサイトに載せているのは4(2×2)的な線の蓄積という感じか。
でもそれらを編み上げて立体化する8(2×2×2)的な作業が大きな課題として立ちはだかっている。
「1」の不安と足掻き (2014.3.8 23:53他、一部改変)
「1」というありのままの自分自身でいることに不安を覚えるあまり、諸々に手を伸ばし掴もうとする逆数「8」の過剰なまでの足掻き。
「1」も「8」も共にバランスが取れれば「9(緩い統合・心地よいカオスモス)」になるんだが。
助け舟も落とし穴も隣 (2014.3.8 23:48)
自身の基本数の前後の数は苦境から逃れるための助け舟にもなるし、油断を招く落とし穴にもなる。
前後の数を利用こそすれ、足を引っ張られることの無いよう心掛けたい。
逆転する殺意 (2014.3.7 11:05)
社会を憎み誰かを殺そうとしている人は結局自分を殺したがっているし、自身の将来に絶望し駅のホームの端に立つ人は社会や傍観者を殺したがっていると思ってしまう。
ビミョーな「9」 (2014.3.6 22:43)
ビミョーな差異しかない二者択一問題をダイスで占う時に限って「9(どっちでも大差無いって!)」が出ちゃうんだよねぇ。
隠し包丁 (2014.3.6 17:26)
人生において一種の「味」を自らに染み込ませるためには遠大な時間が必要となるが、種々の体験や学習などの「隠し包丁」で自らを刻むことで「味」の染み込みを短縮化できる。
でも「隠し包丁」が入り過ぎてしまい、自らがバラバラになることもあるから気を付けたいところだ。
時間泥棒 (2014.3.6 17:02)
最強最悪の時間泥棒って「時間」という概念そのものだよね。
だって「時間」を認識しなければ、初めから「時間」は奪われないわけだから。
賢者の石 (2014.3.6 16:32)
ミヒァエル・マイエル『化学的研究』の中に「男女より一つの円を作るべし。円より四辺形を、四辺形より三角形をひくべし。さらに円を作るべし。なんじ、賢者の石を手にせん」とある。
男女はペアなので2、円は9とし足すと、2+9+4+3+9→27→3×3×3(3^3)が賢者の石となるのか。
マンダラ (2014.3.6 16:03)
マンダラをわざわざ紙や壁に描かずとも、自らという筆を動かし続けることで世界にマンダラを描くことができるんじゃなかろうか。
車輪と車軸 (2014.3.6 15:59)
円の「9(全体)」が車輪だとすれば、棒の「1(自己)」は車軸。
「1」の無い「9」は回らぬただの大きい円でしかないし、「9」の無い「1」は無益な一本の棒に過ぎない。
「1」と「9」が合わさって初めて世界が動き回りだす。
「奇跡」とは (2014.3.6 13:43)
もし運命論の立場で考えるなら「奇跡」ですらも必然であり、予め決められていたということになるね。
でもそうなると「奇跡」の持つ奇跡性が失われるような気がする。
もちろん運命論的な世界の内側から見れば「奇跡」のままだろうけど、もし俯瞰できたならそれはもう「奇跡」じゃないよね。
「1」から「9」、そして「1」へ (2014.3.6 10:15)
「1」という自意識や自我からスタートして最終的に無我・忘我の「9」へと達し自意識を溶かしていくというのは、人が歩むべき道程としては悪くないと思う。
但し「9」で満足し留まってしまうと、ただの「いい人」で終わりかねない。
「9」で溶かした自意識を次の「1」で新たに構築しよう。
「9」と「2」の苦しみ (2014.3.6 9:24)
自他の境界線がぼやけたり、他者や自分自身との繋がりすらもぼやけたりすることで生まれる「9」の苦しみ。
自他の境界線をはっきりと引き過ぎたり、他者や自分自身との繋がりが強くなり過ぎたりすることで生まれる「2」の苦しみ(逆数に「2」を持つ「7」も同様の苦しみを味わう)。
「9」が生きにくい理由 (2014.3.6 8:21)
「9」が現代社会で生きにくい理由は「自他の境界線が曖昧で他者や環境の影響をダイレクトに受ける」ことと「全ての数を内包しているため軸無く彷徨いやすい」こと。
明確な境界線を引く(対数2)、無理にでも方向性を作り実行する(補数1)、そのままの自分を赦す(逆数9)などの対策がある。
充てる (2014.3.5 23:49)
何かを「当てる(的中)」よりも、その人の心に染み入る言葉を「充てる(充当)」ことを大切にしたいよね。
繋がっても離れても (2014.3.5 20:38)
皆が繋がり合うことは生きる上でとても大切なことなんだけど、だからと言って繋がり合うことを強制するのはちと違うと思うし、一度繋がったら離れるべきではないという価値観もいかがなものかとは思う。
「繋がる」と「離れる」、この二つに本質的な善悪は存在しないと思うんだ。
数秘術は答えない (2014.3.5 18:59)
数秘術は不思議を目に見えるようにはしてくれるが「なぜそのようになるのか?」という問いには残念ながら答えてくれない。
数秘術はただのツールに過ぎないからだ。
繋ぐ、切る、「7」 (2014.3.5 18:38)
7の人や7的な人が孤独を避けるあまり、逆数2を駆使して多くの人や社会と繋がろうとする(繋ぐ線)。
しかしそれらの線が増えることで不快な思いをしたり煩わしさを感じるようになり、ついには自らを守るためにその線を切ろうとする(分ける線)。
繋いでは切り、切っては繋ぐ「7」。
箱 (2014.3.5 15:11)
何かを手に入れた後でそのものを入れる「箱」を用意する人。
何かを手に入れる前にそのものを入れる「箱」を用意する人。
前者の希望は無限大だが、後者の希望はどうしても前もって用意した「箱」という存在が制限となってしまう。
事前に「箱」など用意せず、まずは思うままを願い望もう。
鑑定はまるで湯葉作り (2014.3.5 13:28)
なんか時間制限のある中でリーディングするという行為がまるで湯葉作りのように思えてきた。
リーディングする度に湯葉という表層が取り払われていくけれど、ドロドロの豆乳はまだまだ残ったまま。
この豆乳ににがりを加えて一気に固めたいところだけど、現実にはなかなか難しいよなぁ。
もし一日ずれていたら (2014.3.5 13:14)
大人になって「実はお前の誕生日は一日前だったんだよ」などと親から言われたらそれでその人の性格は変わるだろうか。
もちろん一日ずれれば数秘術の結果も変わってくるし、占星術でも太陽星座が変わるかもしれない。
でもそれはあくまでその人の性格をこじつける材料が変わったに過ぎないんだ。
「5」の末の「4」 (2014.3.5 13:00)
僕の逆数秘術は一見すると長年の研究の末編み出された4的な存在に見えるかもしれない。
でも実際は既存の数秘術に対するアンチテーゼの集合体とも呼べる5的な存在であり、5を目指した結果辿り着いた4だったりする。
そしてこの4が硬直化すれば、今度は他者から5の対象とみなされるわけだ。
「8」の中の「1」 (2014.3.5 12:50)
「8」という人工のシステムの中に生きれば生きるほど、組み込まれれば組み込まれるほど、「1」という個が弱くか細くなり、やがて失われていく。
そんな「8」が大きく崩れ立ち行かなくなって初めて、「8」というシステムは「1」という個の集積によって成り立っているのだということに気付ける。
マスターナンバー解釈法 (2014.3.5 12:40)
マスターナンバーの解釈法は大きく分けて三つ。
・「11」や「22」を単体の新たな数として捉え象意を与える
・それぞれの数字根(11なら2)を考慮し、それのパワーアップ版として捉える
・それぞれを構成する数(11なら二つの1)を考慮して象意を与える
とりあえずの答え (2014.3.5 10:35)
「有る」ということと「無い」ということを哲学(7)的に突き詰めていくと、結果的には「有るは無い、無いは有る」などという9的な暫定解にたどり着かざるを得ないのではなかろうか。
「7」というスコップ (2014.3.5 1:08)
様々な問題や自らの内側に至るまで、あらゆるものをその鋭利な知性で深く深く掘り進めていく「7」という存在。
掘り進められるという幸と不幸。
掘り進むという優越感と劣等感。
そんな知性のスコップを放り投げられればどれだけ楽なことだろう。
でもそのスコップこそが「7」の存在意義。
自由意志論と運命論 (2014.3.5 0:42)
自由意志論者たる奇数人は逆数である偶数的運命論に救いを求める。
運命論者たる偶数人は逆数である奇数的自由意志論に憧れを抱く。
道具の存在も良し悪し (2014.3.4 23:26)
僕は「7」に自身の内側を掘る・潜るなどの意を与えている。
昔と今の7の人を比べた際、今の7の人は自らの心を掘り進めたり潜り込んだりする道具が昔よりも多く与えられているような気がする。
その道具によって答えにたどり着くこともあれば、逆に無限に掘る潜るを繰り返すこともありそうだ。
緊迫スリーセブン (2014.3.4 23:11)
ウクライナの独立日(1991年8月24日)から基本数出すと「7」で、ロシアのプーチン大統領の基本数も「7」で、今年(2014年)は「7」の年という緊迫スリーセブンはたぶんどこかの数秘術師が既にネタにしているに違いない。
「我」のいろいろ (2014.3.4 21:35)
数ごとの「我とは?」
1:故無くただ我有り
2:我見る故に我有り
3:我話す故に我有り
4:我在る故に我有り
5:我動く故に我有り
6:我愛す故に我有り
7:我思う故に我有り
8:我求む故に我有り
9:皆在る故に我有り
0:皆無く故に皆無し
笑うオリジナル (2014.3.4 14:55)
オリジナルを真似た者がオリジナルを真似た物を更に真似た者を笑うという滑稽をたまに見かけるね。
そしてどちらもオリジナルを作りし者に笑われるんだ。
奇数の「生」、偶数の「死」 (2014.3.4 13:36)
「生」は5画(奇数・混沌・動性)。
「死」は6画(偶数・秩序・静性)。
「生存」は11画→2(はっきりと見える繋がり)。
「死亡」は9画(繋がりがよく分からないぼんやりした状態)。
人と繋がり動き動かすのが「生」。
人との繋がりが認識できずに止まり続けるのが「死」。
「生」と「死」という漢字 (2014.3.4 13:17)
漢字辞典を見ると「生」という文字はセイ、ショウ、いきる、いかす、いける、うまれる、うむ、おう、はえる、はやす、き、なま、うぶ、なる、なす、と数多くの読み方があるけれど、「死」という文字はシ、しぬ、の二つだけであり、実質上一つだけとも言える。
「生」は多様、「死」は一様。
百を調べて一を知る (2014.3.4 10:56)
「一の事実で百を語る」人よりも「百を調べて一を知る」人になりたいなぁ。
9×9×9分割 (2014.3.3 20:54)
自身のサイトにも載せているけれど、以前に作った「365日の9×9分割法」を見直している。
これに西暦年の数字根を合わせることで、その人の生年月日から均一に3つのルートナンバー(1〜9)を導き出せる。
もう少し温めてみるか。
それぞれの教育 (2014.3.3 15:13)
考えるよりも覚えることを重視する偶数的な教育。
覚えるよりも考えることを重視する奇数的な教育。
それぞれの良し悪しはあるだろうけど、日本の教育はやはり前者に大きく偏っているよなぁ。
ウクライナをダイスで見る (2014.3.2 23:03)
昼間にウクライナ情勢についてダイスを転がしてみたら(特にアレンジメントは決めず)、「5」「9」「0」と出た。
読み解かないでおこう。
プラスよりマイナスで (2014.3.2 20:38)
マイナスドライバー(−)でプラスのネジ(+)を回せることはあるけれど、プラスドライバー(+)でマイナスのネジ(−)は回せないね。
過ぎるよりも足りぬ方が使い勝手が良いのかもしれないね。
ドライバーも、人生も。
「1」だからこその我慢 (2014.3.2 14:25)
「1の人の悪いところは自分勝手でわがままなところ」などと書かれている数秘術本もあるけど、実際は逆数8への反転に伴い最も我慢強くなる数でもある。
若い頃に1の自尊や衝動で恥ずかしい思いをした人ほど逆数8への反動は大きくなり、我慢すべきでないことまで我慢するようになってしまう。
それぞれの愛の行方 (2014.3.2 11:44他)
3・6・9は愛のラインだけど、奇数の3は混沌愛、偶数の6は秩序愛、偶奇両有の9はさしずめ統合愛かな。
3は楽しむ愛であり自己満足愛、6は教える愛であり他者満足愛、9は全てを赦す愛であり全体満足愛。
3(自己愛)の人が愛をこじらせると逆数6へ反転し、犠牲的な愛に走り自らを傷付け続ける。
6(他者愛)の人が愛をこじらせると逆数3へ反転し、身勝手な善意を押し付け激しく見返りを求める。
9(全体愛)の人が愛をこじらせると逆数0へ反転し、自分にも他人にも興味を失い愛せなくなる。
枠 (2014.3.2 1:08)
占い(特に運命論的な)という行為は見えない「枠」を見えるようにすることなのか、はたまた初めから存在していなかった「枠」をあえて作り上げることなのか、一体どっちなんだろうね。
プーチンの武力行使 (2014.3.2 0:45)
ロシアのプーチン大統領(1952年10月7日生・基本数7)がウクライナへの武力行使を決断とな。
2013年10月7日〜2014年10月6日の個人年数は5、2月7日〜3月6日の個人月数は9。
4→5の小嵐の中、9→1の大嵐を迎えるのか。
人の和 (2014.3.2 0:33)
「天の時は地の利に如(し)かず(=及ばず)、地の利は人の和に如かず」という言葉があるが、大震災などの大規模災害を目の当たりにするとどうしても「人の和は地の利に如かず、地の利は天の時に如かず」などと考えてしまう。
それでも人は天の時にも地の利にも負けじと和する努力を重ねるんだ。
神秘か日常か (2014.3.1 22:06)
数秘術における数の捉え方は大きく分けて二つあると思う。
一つは数という存在をとてつもなく不思議なものとして捉え、その不思議を追い求めるスタイル。
もう一つは数そのものをごくありふれた「イメージを持たせた言語的概念」と捉え、日常生活の中で活かしていくスタイル。
僕は後者。
「逆」もあなた自身 (2014.3.1 15:06)
何かをやりたい(1)のに、つい我慢しちゃう(8)逆数性。
人を信じたい(2)のに、つい疑っちゃう(7)逆数性。
素直に自分を出したい(3)のに、つい取り繕っちゃう(6)逆数性。
ただ普通に生きたい(4)のに、つい逆らい抗っちゃう(5)逆数性。
そんな逆もあなた自身。
足し算と掛け算 (2014.3.1 12:17)
世の中の人は「足し算思考」の人と「掛け算思考」の人とに分かれるんじゃないかな。
途中過程で一時的に成果が「0」となるような経験をした場合、足し算思考の人はただ足踏みするだけで留まるけれど、掛け算思考の人は今までの成果に「0」を掛けて無にしてしまう。
人生ゆっくり足していこう。